円卓が招くは翼持つ戦士たち
円卓が欲するは戦士たちの血
円卓に散った戦士たちの魂は、次の戦士たちを誘う
ここに血が流れなくなる、そのときまで
「ま、かけてくれたまえ」
上官の言葉に敬礼し、そして男はソファに腰を下ろした。急ごしらえで色々なものが運び込まれた基地の中には、この手の「応接」物資もそれなりに届いているとは聞いていたが、こんな上等なソファまであるとは彼の想像外だった。これを部隊の傭兵連中が見たら、きっと待遇改善のデモ行進が始まるだろう。先の戦闘で初出撃となった例のおしゃべり――ガイア・キム・ファン辺りが戦闘でメガホンを持っていたらさぞ似合うことだろう、と男は笑った。
「どうですか、傭兵部隊の指揮を執るのは?マッケンジー少佐」
「正規兵に命令するようにはいきませんな。何しろ、腕前が違い過ぎる。下手な指揮をすることが無いよう、緊張の連続ですよ」
「確かに、第6師団に来た連中は噂以上の猛者揃いですからねぇ」
階級が上がっても一向に軍人らしく見えない先任士官――マゴイチ・イマハマ中佐の顔を改めてしげしげと見ながら、彼はコーヒーを啜った。彼は昔からこうだった。士官学校にいたときも、他の連中が早くも命令調の話し方をする中で、この先輩だけはいつも同じ口調、同じ雰囲気。体格も他の猛者たちと比べれば二回りも小さく、体力訓練などでもひいひい言いながら、しかし決して屈しない様子に驚かされたことを男――空中管制機「イーグルアイ」において、傭兵たちを指揮する場にあるジェイクリーナス・マッケンジー少佐は思い出していた。その先輩が、ほとんど唯一私物としてどんな場所にでも持ち歩いていたのが、手挽式のコーヒーミルと豆だった。味の良し悪しはそう分からないが、上等な豆を使っているのであろう芳醇な香りが鼻腔をくすぐる。客人を迎えるときに、いつもニコニコしてコーヒーを入れるのが、不思議な先輩士官の癖であった。
「ところで、話を変えますが、マッケンジー少佐、ここへ来てもらったのは、次の作戦実施に関して君の意見を聞いておこうと思ったからです。前線の現場を仕切る、強面指揮官殿のね」
イマハマ中佐はソファ脇に置いたアタッシュケースのロックを外し、中から作戦実施に係る計画書の束を取り出した。几帳面に付いているポストイットの色が鮮やかだった。
「詳細は後ほど読んでもらうとして、その青い付箋を付けたところ、そこを見てもらえますか」
マッケンジーはそう指示されたページを開き、そして目を疑った。いや、これを見れば誰でも疑いたくもなるだろう、と彼は思った。作戦計画書はこう言っているのだ。"本作戦成功のためには、ベルカ軍の目を引き付けるための効果的な陽動作戦が必須である。よって、最前線に近いウスティオ空軍ヴァレー基地から、陽動作戦のため、ベルカ絶対防衛戦略空域「B7R」へ航空戦力を投入する"――と。
ベルカ絶対防衛戦略空域「B7R」。
それは連合軍の戦闘機乗りにとって、忌まわしき悪夢を伴う戦闘空域の名前である。隆起地形が円状に広がる、直径400kmの広大な地域。 ベルカ公国とウスティオ共和国の国境線上に位置し、古の時代から、国境線が幾度も引き直された地でもあり、その豊富な鉱産資源を巡って幾度も争いが起こった地。ベルカ戦争初期段階においても 激しい制空権争いが頻発した空域であった。結果として空域を手中に収めたベルカ軍は、この空域を本土防衛の極めて重要な防衛線と認定、空軍の中でも選りすぐりのエース部隊を含めた、大規模な航空戦力を常駐させていたのである。南部防衛線ハードリンアン線と合わせ、連合軍がベルカ本土を攻略するためには突破しなければならない難所の一つ。それに対し、連合軍――否、オーシア軍は僅かな航空戦力しか持たないヴァレー基地に、生贄を捧げろと言っているのだった。
「……命令なら致し方ありませんが、うちの亡命政府もこんな話を良く飲んだものですな」
「所詮はオーシアの後ろ盾がなければ、今日の食事にも困るような連中です。まして、ここにいるのは傭兵ばかり。代わりの傭兵はいくらでもいると思っているんでしょう。……困ったものです。ベルカ軍に抵抗する気もない国軍なんかよりも、余程この国のために戦っているのが誰なのかをもっと考えて欲しいものですよ」
もっとも、オーシアがこんな話を切り出したのには、皮肉にも第6師団の活躍が聞こえだしたせいもある。ヴァレー空軍基地に向けられた大規模な爆撃部隊が壊滅したというニュースは、敗戦ばかりが続いていたオーシア・ウスティオ・サピンにとっては久方ぶりのグッドニュースだったのだ。だがそれは同時に、手柄をまんまと奪われた大国オーシアの嫉妬の対象ともなった。即ち、それだけの腕前があるなら、B7Rくらい自力で抑えてみろ、というわけだった。
「私の質問はね、この難しい任務を誰に任せるか、ということなのです。私は実際に彼らと飛んでいるわけではないので、手元に届けられた戦闘記録を見るしかない。その点、君は現場でそれを見ている。……難しい、実に難しい作戦です、これは。しかも、陽動であることは極力彼らにも伝えたくない。生贄と知って、真面目に飛ぶ連中ではないでしょうからね」
「あくまで個人的な意見ですが、ここはやはり66小隊――ガルム隊を当てるのが適任でしょう。片羽も相当なものですが、サイファー、彼のずば抜けたセンスには脱帽物です。実のところ、私よりも遥かに彼は戦場を把握している。……彼らなら、やり遂げてくれるものと思います」
イマハマ中佐は、わが意を射たり、という表情で何度も頷いた。
「私の意見も同じです。ディンゴ隊では柔軟な対応は無理、マッドブル隊ではあまりに危険……となれば、適任はやはりガルムしかいない、というのが私の見解です。もっとも、司令官殿にはもっと別の考えがあるみたいですがね」
そう言って、彼はマッケンジーが初めて見る表情――苦笑を浮かべた。ヴァレー基地にとっても欠かせない戦力であるガルムの2人、サイファーとピクシーを生還させるために何が出来るだろう?今回もまた胃が痛くなる指揮を執らされそうだ、とマッケンジーは苦い思いをコーヒーで奥に流し込んだのだった。
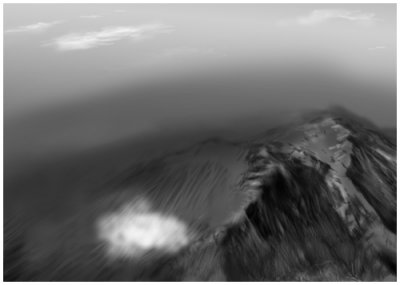 地下に眠る鉱産資源の影響なのか、それとも気候の影響なのか。眼下に広がっているのは、草木もろくに生えていない、岩むき出しの大地。音速の速さで通り過ぎていくその大地は、日の光を受けて赤く輝いていた。この先に広がるのが、「円卓」――ベルカにとっての絶対防衛戦略空域。そして俺たちにしてみれば、ベルカへと攻め込むためには必ず通過しなければならない関所。俺たちに下された指令は、ウッドラント大佐による作戦、というものではなく、その上に乗っかる連合軍――オーシア軍首脳部によるものだった。"B7Rを強行偵察せよ"、と言ってもこんなところで何を偵察して来いというのか。上を飛んでるベルカ空軍機のパイロットと記念撮影でもして来いというのだろうか。俺たち傭兵の契約書には、意にそぐわない作戦、明らかに死を求められるような作戦に対する拒否権が認められている。が、その条項には但し書きがあり、"基地の存亡に係る緊急事態発生時においては、限定的ながら基地司令官職の命令に服従することが出来る"と書かれていた。その但し書きを持ってきて、これまたおよそ軍人らしからぬイマハマ中佐にしぶとく粘られては、渋々受け入れざるを得ないというものだった。お人よしは長生きしないぞ、とラリーに言われるのも無理はなかった。
地下に眠る鉱産資源の影響なのか、それとも気候の影響なのか。眼下に広がっているのは、草木もろくに生えていない、岩むき出しの大地。音速の速さで通り過ぎていくその大地は、日の光を受けて赤く輝いていた。この先に広がるのが、「円卓」――ベルカにとっての絶対防衛戦略空域。そして俺たちにしてみれば、ベルカへと攻め込むためには必ず通過しなければならない関所。俺たちに下された指令は、ウッドラント大佐による作戦、というものではなく、その上に乗っかる連合軍――オーシア軍首脳部によるものだった。"B7Rを強行偵察せよ"、と言ってもこんなところで何を偵察して来いというのか。上を飛んでるベルカ空軍機のパイロットと記念撮影でもして来いというのだろうか。俺たち傭兵の契約書には、意にそぐわない作戦、明らかに死を求められるような作戦に対する拒否権が認められている。が、その条項には但し書きがあり、"基地の存亡に係る緊急事態発生時においては、限定的ながら基地司令官職の命令に服従することが出来る"と書かれていた。その但し書きを持ってきて、これまたおよそ軍人らしからぬイマハマ中佐にしぶとく粘られては、渋々受け入れざるを得ないというものだった。お人よしは長生きしないぞ、とラリーに言われるのも無理はなかった。「イーグルアイより、ガルム隊。円卓は間もなくだ。空域の偵察行動を開始せよ。なお、敵航空部隊と接敵した場合には速やかに敵戦力を攻撃、排除せよ。検討を祈る」
「祈ってる方は楽でいいよなぁ。……サイファー、必ず生きて帰ろうぜ。祝杯を挙げるのに丁度良いラムがあるんだ。ホットでいくか?」
「それだけ上等な奴なら、一杯目くらいストレートで行こうぜ。祝杯ってのはそういうもんだろ?」
「違いない」
円卓の上空は、円卓近くに存在する鉱物資源の影響か、強い磁力による電波障害が発生している。この天然のECMと言うべき障害自体も十分に厄介だった。高度は8,000フィート。ピクシーと2機並んで、俺たちは円卓へと空を駆ける。だが、あのベルカが上空を守る航空機だけに対空防衛網を任しているものだろうか?これだけ広域に至る空域をカバーするからには、地上にカモフラージュしたレーダーサイトがあってもいいのではないか――そんな俺の不安が的中したかのように、敵の交信が聞こえてきたのは間もなくのことだった。
「IFFの故障?機影が2機、包囲120より接近。そっちはどうだ?」
「故障じゃないぞ。ウスティオのIFF反応、機影2。……こいつら、円卓を知らないのか?」
レーダーの敵戦闘機がターン。俺たちの方向に機首を向けて接近する。
「ばれたぞ……やるか?」
このまま180゜ターン、全力で加速すれば敵に捕捉されることなく脱出は可能かもしれない。だが、別の基地にでも連絡されて先回りでもされれば、俺たちに帰る術は無くなる。……ウッドラントの奴め、まんまと俺たちに貧乏籤をひかせやがったか。長々と考えている時間は無かった。ならば、1%でも生存確率を高めるために、敵を排除するしかない。素早く交戦を宣言し、全兵装のセーフティ解除。武器選択モードは長射程AAM。イーグルアイからのサポートを受け、前方から接近する敵戦闘機を捕捉。俺の目にはまだ敵の姿は見えていないが、愛機はレーダー情報から敵機を捕捉、ロックオンしたことを告げる電子音を鳴り響かせた。接近する敵機は2。ピクシーに一方を任せ、もう一方に対して攻撃開始。
「ガルム1、フォックス3!」
発射したAAMの残した白煙の中をかき分けるように、敵機に対してヘッドオン。ガンモードを選択して2次攻撃に備える。数秒後、俺たちの前方で火球が二つ炸裂し、そしてあっという間に俺たちの後方へと過ぎ去った。
「メイデイメイデイ、くそっ、機体が言うことを聞かない!」
「敵機侵入!繰り返す、敵機侵入!今までの連中よりも速い、気をつけろ!」
「上も下も右も左も敵か!同士討ちの心配をしないで済むのが唯一の救いだぜ。……クソっ!」
ピクシーの後方に、Mig-21bisがへばり付く。失速反転からパワーダイブ。高G旋回で敵のレーダーロックからピクシーがジンク。が、さすがは円卓の鳥。同様に高G旋回で距離を縮めながらその後背を追う。と、その刹那、ピクシーのF-15Cのエアブレーキがフルオープン。急減速した機体に衝突寸前で敵機がブレーク。直後、ピクシー機からAAM発射。至近距離から狙われた敵機が必死の回避機動を始めるが、加速するミサイルに追い付かれ、機体後部を吹き飛ばされる。キャノピーが弾け飛んで、中からパイロットが射出される。複雑な飛行機雲とミサイルの白煙、そして機関砲弾の飛び交う空を、ゆらりゆらりとパラシュートが舞い降りていく。
「ナイスキル、ピクシー」
「心臓に悪い。早くこいつらを潰して帰りたいもんだぜ」
6時方向、12時方向双方から敵のレーダーロック。ミサイルアラートが断続的に鳴り響き、聴覚神経を飽和させていく。バレルロール、急旋回。キャノピーの上を、何本かのミサイルの白い煙が通り過ぎていく。ヘッドオンで急接近した敵機と高速ですれ違う。コクピット内にまで響くような轟音を聞きながら、アフターバーナーON。機首下げ。心地よい加速を得た愛機が地表目指して急降下。次いで後方の敵機もダイブ。高度計がコマ送りで減っていくのを視界の片隅に確認しつつ、見る見る間に迫る地表を睨みつけて3つ数える。1……2……3!思い切り力を込めて操縦桿を引き、スナップアップ。身体全身がシートに押し付けられるような高Gで一瞬ブラックアウト。首を振って無理やり視界と意識を回復させてすかさず急旋回。身体と機体の限界に挑むような機動を繰り返す。我に返って振り返ると追撃機の姿は無く、代わりに赤い岩肌の一角を吹き飛ばすように爆炎が吹き上がった。そのまま機首を引き上げて垂直上昇する俺の目前を、別の敵機が通過。加速しながら水平飛行に戻し、レーダーロック。AAMを発射して右旋回。俺たちのケツを舐めに来る敵機から逃れるべく、空域を俺たちは縦横無尽に駆け回る。レーダーからまた一つ、敵の姿が消える。離れたところから包囲されて長距離AAMの雨あられを降らされた日にはたまったものではなかったが、ベルカ空軍の連中はどうやらそのプライドが災いしているらしい。俺たちとドッグファイトで雌雄を決するべく、結果として乱戦状態を自ら作り出していたのだった。
どんなに高性能な戦闘機でも、使いこなせなければ意味が無い。その点、俺の機体は決して新型ではなかったが、ナガハマ曹長らの"愛情"こもった整備に間違いはなく、新品でもこうはいかないだろう、というフケの良さでエンジンが咆哮をあげる。かなり無茶な機動にも機体は応え、俺たちは次々とベルカ空軍機を葬っていった。ある者はコクピットを潰され、ある者は翼をもがれて虚空をパラシュートに引かれて漂う。飽和状態になった空は、しかし一機が撃ち落されるたびに確実に広がっていく。俺たちはついに包囲網の網を食い破った。
「こちらプサルト6、こいつら化け物か!?」
「くそ、ここは我らの聖域なんだぞ。飛び方も知らない連中に翻弄されるとは……!」
包囲網を突破した俺たちは、フル加速で敵機からの距離を稼ぐべく、南東方向へと機首を向けた。残存の敵部隊は旋回を繰り返しているだけで追撃してこない。コクピットのディスプレイに視線を移し、素早く残り兵装を確認。AAMよし、長射程AAM残弾2、機関砲弾、まだ大丈夫。燃料残、帰投途中タンカーを回してもらえばもう一往復出来るくらいは大丈夫。よし、コンディショングリーン。被弾も故障も無く、愛機のエンジンは心地よいサウンドを奏で続けていた。
「ガルム2より1、こっちは問題なしだ。もう一当たり、十分いけるぜ」
「こっちコンディショングリーン。どうにか円卓の鳥と渡り合っているみたいだな、俺たち」
「どうせなら、渡り合うんじゃなくて凌駕したいところだな、相棒」
「同感だ……よし、行くぞ!」
ようやく決心がついたのか、のろのろと俺たちの後を追い始めた敵の光点が、チェックシックス、6時方向から迫る。戦域にもともと広がるように飛んでいたベルカの鳥たちは、今となっては俺たちを追撃すべく一所に集まっていた。今頃上空ではイーグルアイが円卓の情報収集に勤しんでいる頃だろう。今日ここで得られた情報は、再びこの上で戦うときに大きなアドバンテージになることは間違いない。そのためにも、生きて帰ることだ――!大きくループを描き反転した俺たちは、ヘッドオンで相対することとなった追撃機たちを狙う。最も至近の第一群は3機。ピクシーが先行してAAM発射。白い排気煙が俺を追い越して、敵機めがけて伸びていく。ラダーペダルを軽く踏んで針路を微調整。HUDに映る照準レティクルを睨み付ける。ピクシーの放ったミサイルを察知した敵機が編隊を解き、回避機動。ミサイルを避けるべく上昇しようとした1機が照準内にぴたりと収まる。反射的にトリガーを引き絞る。機関砲弾の残弾カウンターがコマ送りに減少するごとに、光の筋を引く20ミリの弾丸が獲物めがけて襲いかかる。どてっ腹をぶち抜かれた敵機が、黒煙を吐き出しふら付きながら上空へと逃れていく。もう1機がピクシーのミサイルをまともに食らった火球と化し、虚空に残骸をばら撒く。かろうじて攻撃を回避した敵機を無視し、その後続隊に対してさらに攻撃を食らわす。ヘッドオンから放ったAAMが正面から突っ込んできたF-4Eのエアインテークに突き刺さり、全身を炎に包んだ敵機は大爆発を起こして跡形も無く消し飛ぶ。危うくその炎の中に飛び込みそうになり、バレルロール。弾け飛んだ敵機の細かい残骸がいくつか機体と衝突し、金属音をあげる。
「くそ、駄目だ!こいつら強すぎる。俺たちの手には負えん!」
「一時撤退だ!早く、早く!」
生き残った敵機は仲間たちの仇を討とうともせず、我先にと戦闘空域外へと逃れていく。
「イーグルアイよりガルム隊、好機だ!B7Rに侵入し、作戦行動を開始せよ」
「強行偵察というよりも強行殲滅作戦だけどな……ガルム2了解。さて、いよいよ「円卓」か!」
俺たち戦闘機乗りに与えられた舞台――所属も階級も、そして上座も下座も無い、ただ己の力だけが頼りとなる闘技場。その門戸が、ようやく俺たちの前に開かれようとしていた。
「先導部隊、壊滅状態で撤退中です」
あれが部隊と呼べるものならば、のことだが――。侵入してきた敵航空部隊、ウスティオ空軍の2機は数的劣勢を完全に覆し、ついにその重囲を破って同胞を敗走せしめることに成功していた。全く、大したものだ――男は、素直に敵の力量を賞賛した。開戦から今日まで、これほどの腕前を持ったエースが果たして幾人出会っただろうか?自分たちの抱える槍に貫かれた葬られた敵国のパイロットの数は相当なものになるだろうが、彼らが苦戦したことはごく稀であっただろう。北の谷に封じ込められようとしていた同胞たちを救済するため、その尖兵として戦場を飛ぶことは彼らにとって誇りであり、何よりの喜びだった。そこに立ちはだかるというのならば、部隊の誇りにかけても彼らを滅するだけのこと――男は、一分のズレも無く編隊を組む部下たちに視線を移した。
「どうやら、敵部隊はこれまでの相手とは一味違うようだ。この空域に移ってきて早々、倒しがいのある敵と出会えたことに感謝しよう。……なに、いつも通り、我々は我々のやり方で飛べばいい。それが勝利をこの手に掴むための、最善の手段だ」
「インディゴ4、了解!」
「分かっております、インディゴ2、了解!」
4機のJAS-39C、グリペンはトライアングルを組んだまま、戦闘機乗りたちの戦いの舞台へと足を踏み入れる。目標は、祖国にとって守らねばならない聖域に入り込んだ、ウスティオの戦士たち。音速の騎馬を駆る藍色の騎士たちは、手綱を握りそして槍を構え直した。
「全機、攻撃開始。行くぞ!!」
――「藍色の騎士団」、到来。