そこに、勝者はいなかった。
そこは、何もかもが焼き尽くされ、何もかもが死に絶えた大地。
兵士たちは自分に問うた。――何のために戦うのか?
それでも、命の浪費は終わらない。
『OBCのニュースロゴに続いて、ベルカ軍の最終集結地スーデントールへ向けて出撃する戦闘機部隊の映像が大写しになる。キャノピーの下、破れたハートのエンブレムを描いたF-14Dが轟音をあげながら離陸していく』
――おはようございます。OBCニュース、デイビット・サイモンがお伝えします。世界中を震撼させたベルカによる一方的な侵略行為から2ヶ月が経ち、ついに連合軍はベルカ軍をバルトライヒ山脈の麓まで追い払うことに成功しました。そして、未だに戦意をむき出しにし、開発が進められているという核兵器の使用まで国際会議の場で発言したベルカに降伏を迫るため、連合軍による最終攻撃が開始されました。今日は時間を拡大して、ベルカ戦争関連のニュースからお伝えしたいと思います。ドレッドノートさん、そちらの状況はいかがですか?
『先ほどの航空基地のロングスパン映像。滑走路に集結した戦闘機、爆撃機たちが次々と離陸していく姿が映し出される。中年の記者が、ジェット戦闘機の離陸によって吹き荒れる風に翻弄されながら、マイクを握り締めている』
――はい、こちらエドモンド・ドレッドノートです。既に映像でもご覧頂いておりますが、連合軍の最精鋭の戦闘機部隊が、スーデントール市目指して出撃を続けています。先日、ベルカの強さの象徴でもあったエリアB7R、「円卓」の制圧に成功したのも、彼らの活躍があってのことです!既にベルカ軍は相当の戦力を喪失していることに違いなく、出撃するパイロットたちも、このスーデントールがこの戦争最後の決戦地になるだろう、と話していました。連合軍の勝利は確実なものとなった今、無益な抵抗は戦死者を増やすだけだ、というメッセージをベルカの兵士たちに伝えることが大切だと思います。
――ドレッドノートさん、引き続き取材を続けてください。では、スタジオに戻りまして、オーレッド戦略研究所のケンウッドさんにお越し頂いております。
『画像がスタジオに戻り、アナウンサーの脇に座ったダークグレーのスーツの男にカメラが向く。銀縁の眼鏡をかけた男が、咳払いをしながら座っている。アナウンサー、にこやかな笑顔を浮かべながら男と握手を交わす』
――ケンウッドさん、よろしくお願いします。さて、問題となっているベルカの核兵器ですが、ベルカは今どのような兵器を開発しているのでしょうか?
――情報は色々と錯綜していますが、MIRV、即ち、多弾頭の核ミサイルである、という情報が正確な模様です。射程は数千キロ。ですので、オーシアだけでなくユークトバニア、或いはユージアまでも射程内に捉えることが出来ることになります。
――それは大変な話ですね。これに対し、国際社会はどのような対応を取っているのでしょうか?
――これにつきましては、先日来開催されている国際会議において、ユークトバニア・オーシア両大国が協調してベルカに断固たる姿勢を示しておりますし、現在のところベルカに同調するような国家は一つもない状況です。現在行われているスーデントール市に対する総攻撃には、依然として強硬な態度を取り続けるベルカに対する制裁の意味もある、というわけです。
――なるほど、核査察を頑なに拒み続けてきたのが何よりの証拠である、と?
――そういうことになりますね。先日、ホフヌングというベルカの大工業都市を、ベルカ軍が自らの手で焼き払うという悲劇が引き起こされたのですが、ホフヌング自体が核生産拠点であった、と連合軍司令本部は発表しております。回収された資料は少ないようですが、ベルカの核開発疑惑はこれで証明されたとする専門家もおりますので。
――分かりました。では、CMに続きましてケンウッドさんには現在の戦況を解説して頂きます。
連合軍の侵攻作戦は風雲急を告げる。ホフヌングの焼き討ちを進める一方で、連合軍は保有する戦力の相当数を、ベルカの残存軍が篭城するスーデントール方面へと進撃させていたのである。さらに、海兵隊や陸戦隊といった猛者どもを中心に構成された別働隊が組織され、この部隊はスーデントールを迂回してバルトライヒを越えるべく、それぞれの目標地域へと進撃を続けているのだった。先日のホフヌング焼き討ちは、連合軍司令本部にしてみれば、スーデントールへと戦力を集中させるための作戦の一つだったのだろう。戦略的には成功かもしれないが、あんなやり口は人の憎しみをかきたてるだけだ。つくづく、戦争ってのは前線にいる兵士ではなく、後ろにどっかりと座っているお偉方がやってるものなのだ、と痛感させられる。そんな気分での出撃ほど嫌なものはない。これも、戦争を早く終わらせるためだ――そう、自分の心を納得させて、俺は飛んでいる。それで傷ついた心が癒されるわけではないが。だが、そんなことを考えている時間もないくらい、忙しい日々か通り過ぎていった。スーデントール方面は、連合軍の主力部隊であるオーシアがどうしても陥落させたいらしく、俺たちに出撃要請がかかることは無かった。代わりに、バルトライヒ向こうへの強行偵察だの、進撃する別働隊の上空支援といった突発的なミッションが舞い込んできて、俺たち傭兵は走り回る羽目となった。
「イーグルアイより、各機へ。ポイント203までの間に敵勢力の機影無し、ランデブーポイントまで警戒しつつ飛行せよ」
「マットブル隊、了解」
「クロウ隊了解!」
バルトライヒの山を越え、いよいよベルカの内側の空を俺たちは飛んでいる。俺たちに下った命令は、スーデントールへと侵攻する陸上部隊の上空支援。つまり、この数日課せられてきた任務と同様というわけだ。このままバルトライヒの尾根沿いに飛んで、スーデントールの西側から攻撃に移る――その作戦命令に従いながら、俺たちはバルトライヒの上を飛んでいる。足元には、緑の萌えるバルトライヒの山々が連なり、その美しい光景を一望できるように、と湖の畔には古城が立つ。この北の谷の国家を長らく統治してきた王族たちの居城の一つだ。今でもその血筋に連なる人間が生活する城砦。だが、その光景は、恐らくバルトライヒの最も美しいであろう緑と調和し、ある意味幻想的な光景を醸し出す。だからこそ、この城の風景が世界的にも有名な「美しい」景色の一つとして写真に収められたりするのだろう。なるほど、俺たちはその美しい景色にケチをつける物騒な鳥たち、というわけだ。俺は何気なく左を向き、そこにいつもならいるはずの相棒の姿がないことに気が付く。レーダーを見ると、俺からやや遅れた位置にポツンとラリーの機影が追ってくる。
「イーグルアイより、ガルム2。どうした?遅れているぞ?」
「こちらPJ、機体の故障っすか?」
「いや……大丈夫だ。すぐに追い付く」
ラリーの声が暗い。ホフヌング焼き討ちは、ヴァレーの傭兵たちの心に深い傷跡を残していたが、とりわけラリーには堪えたらしい。快活さは姿を消し、無口で沈痛な表情を浮かべながら煙草をくわえているか姿が、どこか寂しげであり、どこか虚ろな空気を漂わせているようだった。それは多分俺も同じだったのかもしれない。だが、ここで戦うことを止めれば、さらに長く凄惨な戦いが続くかもしれない。だから、戦う。戦闘機乗りとして、傭兵として。戦争の道具として使われる後ろめたさに、ただ理由付けをして言い訳しているだけかもしれないが、それが今の俺の覚悟だった。朝の光が、ゆっくりと山脈の緑にコントラストを織り成し、空が明るくなっていく。仲間たちの機体が朝日を反射して、煌く。これが戦場へ向かうフライトでなければ、どんなにか楽しいだろう。目の前に広がる美しい風景に気を取られていた俺だが、そんな気分はイーグルアイからの緊急通信でかき消されることになる。
「こちらガルム1。どうした、何があった?」
「イーグルアイより各機へ。緊急事態だ!ベルカ領内より、核爆弾を搭載した爆撃機編隊が飛び立った。連合軍からの情報では、こいつらの目標は我々の家――ウスティオだ。何としても、ここで食い止めろ。敵編隊の位置は方位0-0-0。君たちの現在地から北方およそ15マイル。急げ!!」
「おいおいおいおい、マジかよ。冗談じゃねぇぞ!!」
まだ俺たちのレーダーに目標の姿は捉えられない。イーグルアイの伝えた方向に旋回、高度を上げながらスロットルを押し込んで加速。ヴァレーの傭兵部隊も次々と加速。コンバット・フォーメーションを組んだ鋼鉄の翼の群れが、轟音を発しながら山脈を飛び越え、ベルカ領内の更なる深部へと突入していく。
「絶対に食い止める。核は使わせない!」
「もちろんだ、シャーウッド。オブライエン伍長を守るためにも、ここは食い止めよう!」
「了解!!……あ、いや、PJ、オブライエン伍長だけじゃなくてだな……そう、ヴァレーの皆を守るために!!」
「素直じゃねぇなぁ、はっきり言やいいのによ。まあいい、おい、野郎ども!!1機残らず撃ち落すぞ。気のいいヴァレーの連中のためにも、俺たちの手で解放したウスティオのためにも、ベルカの野郎どもを通すわけにはいかないからな!」
傭兵たちが口々に応じる。そう、ヴァレーは俺たちの家、俺たちの帰るべき、そして守るべき巣。それだけじゃない。戦争による占領下からようやく解放されたばかりの無数の市民たちのためにも、ベルカの攻撃は絶対に食い止めなければならなかった。
「敵部隊までの距離、あと8マイル!君たちの真正面、針路変更無し!!」
もう美しい風景に目を奪われている余裕は無い。HUDを睨み付け、操縦桿を握り締め、激しい加速に震える愛機を必死で飛ばす。敵機までの距離と時間がもどかしい。レーダー上、俺たちの真正面に敵部隊の姿が映し出される。爆撃機、戦闘機、多数。イーグルアイの指摘通り、針路変更なし。このまま進めば、俺たちヴァレー組と真正面で激突する。素早くコンソールを操作して、全兵装セーフティ解除。中距離ミサイルを武装選択。
「あと5マイル!!」
「……いっそすべてを吹き飛ばしてくれれば、すっきりするんだろうな」
「マッドブル1よりガルム2、すっきりしすぎて却って後味悪いだろうぜ」
「フッ……確かにな」
もう敵部隊にも俺たちの姿は捉えられただろう。敵戦闘機編隊、爆撃機に先行して突撃体勢。複数のトライアングルが俺たち目掛けて突出してくる。互いの彼我距離、急速に縮まる。
「あと2マイル!」
「ガルム1よりイーグルアイ、ミサイルの誘導、任せる!」
中距離ミサイルのレーダーロックを起動。真正面から接近する3機編隊を狙う。ロックオンと同時に、2発、ミサイル発射。ラリー機、同様にミサイル発射。マッドブル隊、クロウ隊それぞれ、長射程のミサイルを抱えてきた連中が一斉に攻撃開始。狙いは敵も同様。ロックオンの電子音は、レーダー照射を受ける警告音に切り替わる。各隊、上昇、旋回、或いは下降で回避機動。こちらもバレルロール、少し大きめの楕円を刻んで攻撃を回避。頭の下を敵の放ったミサイルが通過し、次いで真っ赤な炎と黒煙が炸裂するたびに部品を撒き散らして分解していく敵機の姿が通り過ぎる。俺とラリーの放ったミサイルが、敵護衛機――F-15Eの機体を引き裂いて、虚空に火球を出現させる。戦闘機たちが互いに噛み合い始めた空を、爆撃機がゆっくりと、通り過ぎていく。くそ、戦闘機に関わっている余裕は無いんだ!!だが、敵戦闘機部隊も必死だ。しかも、腕も悪くない。俺たちを爆撃機の方向へ行かせないよう、連携して俺たちの針路を阻む。強引に包囲網を突破して、手近の爆撃機を捕捉する。後方からレーダー照射警報。手早くミサイルを発射して、次目標を捕捉、再攻撃。操縦桿を思い切り引き寄せて、スナップアップ。跳ねるように反転し、俺を追う敵機に対してヘッドオン。敵機、ミサイル攻撃を諦めてガンアタック。機体をローリングさせて回避、すれ違う。再び高Gをかけてインメルマルターン。敵機の後背に喰らい付く。兄弟機といってよいF-15Eの後姿を追うのは不思議な感触だ。敵機、右方向へ倒して急旋回。ややオーバーシュート気味にこちらも旋回、相手との距離を一気に詰める。敵機が水平に戻す一瞬のタイミングを狙い、ガンアタック。機体左側から直撃弾を食らった敵機が黒煙に包まれる。次の獲物を探して、首をめぐらす。
「……爆撃機、3機やられたか。だが、1機だも突破できればいい。針路は変えるな、前進せよ」
敵の戦意は折れない。連中、死ぬ気か。初めから帰ることなど考えずに戦おうとする敵ほど嫌なものはない。そんな状態に兵士たちを追い込む上の人間にはもっと虫唾が走る。彼らにだって、帰るべき家、帰るべき故郷があるだろうに――!俺たちは、そんな悲壮な覚悟を決めた敵を相手に、戦わなくてはならないのだ。求めるものは、平和、ただそれだけのはずなのに。戦わないで済む世界のために、戦う、これほど悪質な皮肉は無い。3機目のF-15Eを葬って、ようやく護衛機のいなくなった空間に浮かぶ爆撃機隊を捕捉する。先発がいて、爆撃機にガンアタックを仕掛けている。が、それは直撃を敢えて避けるように放たれたものだった。そこにいたのは、友軍機ではなく、ベルカの記章をつけたMig-31。
「同胞に告ぐ。こんな作戦に何の意味があるのか!?直ちに攻撃を中止し、基地へと帰投せよ。さもなくば、攻撃する!」
「祖国の裏切りものどもめ。構うな、前進を続けよ。どうせ、何も出来ない連中だ」
「……もはや、語る言葉は無いか。お前たちなど、同胞ですらない!!」
Mig-31の放ったミサイルが爆撃機に突き刺さり、その巨体を引き裂いていく。乗組員たちの断末魔の絶叫のように、内部から炎を吹き出した爆撃機が、木っ端微塵になってバルトライヒの山へと落ちていく。友軍爆撃機を葬ったMig-31の1機が、F-15E部隊の集中砲火を浴びて大爆発を起こす。突如として始まったベルカ軍同士の戦いに乗じない手は無かった。指揮系統に混乱をきたした敵部隊に、先程までの連携は無い。
「イーグルアイより、各機へ。敵部隊が同士討ちを始めている。一気にたたみかけろ!!」
「クロウ1、了解」
「こちらクロウ2、乗じない手はないさ。うまく利用させてもらう!!」
巨体を傾けて回避機動を続ける爆撃機にトドメの一撃。胴体はそれでも頑丈に出来ているから、狙いはそこではなく、簡単に粉砕できる翼!俺の放った機関砲弾は、爆撃機の翼を紙を裂くようにいとも簡単に粉砕し、根元を残して切り取った。機体を引き起こすことが出来ず、そのまま裏返った爆撃機が、そのままぐるり、と回転しながら地上へと落ちていく。くそ、あと何機だ!?クロウ隊が大回りで敵部隊の真正面に回りこみ、進路を阻む。旋回しようと向きを変えた爆撃機に、マッドブル隊がトドメを刺す。そのまま加速したガイアたちは、クロウ隊同様に回り込んで、敵戦闘機部隊と相対する。敵部隊の反撃も熾烈だったが、それも徐々に散発的なものになり始めていた。よし、もう少しだ!かなりの損害を出しながら、尚もウスティオを目指す敵機を追うために、俺はスロットルを押し込んだ。
緑に萌えるバルトライヒの空を、ハゲタカが行く。敵だけでなく、友軍でさえ恐れる督戦隊である彼らの機体は、決して見栄えが良いとは言えないカラーリング。まさに、死屍に群がるハゲタカそのもの。そんな部隊を率いる男、ドミニク・ズボフは彼らに向けられた非難や不満を平然と受け止め、決して歴史の表には出すことの出来ない任務を淡々と、しかし確実にこなしている。ベルカの嫌われ者の代表格ではあったが、少なくとも彼が腕の悪いパイロットでないことは、部隊の新米であるハイライン・ロッテンバークも認めざるを得ない事実であった。同時に、彼としては復讐を果たすためにも、そんな男の走狗となって味方を熱心に殺す以外の選択肢は無く、気が付けば部隊の面々からも認められる存在となりつつあった――冷酷非道な味方殺しの一員として。そして、8機のハゲタカが向かっている先は、勿論今日の晩餐の在処だった。どの基地のどこの部隊の誰なのか、それは隊長たるズボフしか知らない。隊員たちは、彼の命令に従って、祖国の裏切り者を刈り取れば良かった。この方向は、もしかしたらヒルデスブルグの方角だろうか――そう、ロッテンバークが首を傾げていると、珍しく普段は何も語らない隊長機からの通信が聞こえてきた。
「今日の獲物はちと特別だ。格別のご馳走だから、お前たちにも先に伝えておく。俺たちの向かう方角にある基地といったら、どこだ、若造?」
唐突の指名に、ロッテンバークは息を呑む。だが、沈黙することは許されない。例え間違えて笑われるとしても、そんなことは些細なことでしかない。どこの誰であろうと、復讐を果たすまでは単なる障害物でしかないのだから――彼は、そう思い極めているのだった。
「バルトライヒの連なりからして、東部戦線方面と思います。方角としては、ヒルデスブルグではないかと考えられますが、あくまで新入りの想像です」
「全然謙虚に聞こえねぇぞ、自信たっぷりに答えやがって。まあいい、正解だ。俺たちの目標は、ヒルデスブルグ所属、302飛行戦隊――そう、あの"フッケバイン"率いる化け物部隊だ。ヒルデスブルグに叛乱の気配あり、事実なら速やかに"処理"を完了しろ、との命令だ。全く、あの"フッケバイン"が相手かもしれないのに、簡単に言ってくれるもんだ」
ロッテンバークだけでなく、他の隊員たちもさすがに驚いているらしい。"フッケバイン"と言えば、ベルカ空軍のエースの中でもトップエースと呼ばれる戦闘機乗りの一人であり、彼の率いる戦隊は連合軍に甚大な損害を強いてきた、まさに祖国の英雄という呼び名が相応しい男。祖国の若者たちが憧れる英雄の一人。――そんな英雄ですら、もう祖国を見限るのだとしたら――ロッテンバークたちに命令を下すお偉方の魂胆が見え透いて、彼は思わず笑ってしまった。全く、祖国を裏切る英雄も英雄だが、これまでさの英雄に散々世話になってきたにもかかわらず、その存在を自分たちの保身と目前に迫った敗戦からの隠れ蓑にしようとするお偉方の厚顔無恥ぶりには、もう笑うしかない。一体どっちが祖国の裏切り者だ。これを笑わずして、何というのか。
「随分と楽しそうじゃねぇか、若造。英雄相手にブルって気でも狂ったか?」
「は、申し訳ありません。でも、反逆しようとする英雄と、英雄を謀殺しようとするお偉方、一体どっちが祖国にとって裏切者なのか、と考えたら可笑しくなってしまっただけです」
「フン、確かにそのとおりだ。ま、俺たちは金を払ってくれるほうの味方だ。というわけで、"フッケバイン"を刈るぞ。気合入れてけよ。まともにやり合って勝てる相手じゃねぇからな」
「ヘヘ……了解だぜ」
「勝てば官軍、という奴ですな、隊長?」
足元を見れば、湖畔にせり出したシュティーア城とその広大な城下町が広がっている。この高度で飛ぶロッテンバークたちの姿を肉眼で捉えて「それ」と認識できる市民などいるはずも無いが、連中が頭上を飛ぶ部隊の正体に気付いたら、一体どんな顔をするのだろう。侮蔑の笑みを浮かべるのか、それとも恐怖で引きつった顔になるのか、それとも無視するだけか――ロッテンバークは凄惨な笑みをマスクの下に浮かべた。彼にとって、そんなことはどうでもいい瑣末な物事でしかなかった。仇――レオンハルト・ラル・ノヴォトニーの首を取るためなら、どんなことでもやってみせる。その信念が、復讐鬼の心を突き動かす。だが、彼は知らない。そんな彼ほど、ドミニク・ズボフにとって扱いやすい駒は無いのだ、ということを。
決死の突撃を続けていた爆撃機の最後の1機が、炎に包まれて落ちていく。敵護衛戦闘機をシャーウッド、PJ若手二人のコンビが始末している間に、マッドブル・ガイアが仕留めたものだ。全身を黒煙と炎に包まれた爆撃機は、地表に到達するよりも早く空中で火の玉と化し、バラバラに四散してバルトライヒの山へと降り注いでいく。これで敵爆撃機全滅!幸いにも、連中が搭載していたという核爆弾は起爆せず、全てを葬ることに成功する。
「イーグルアイより全機、全爆撃機の撃墜を確認!!よくやってくれた、これでウスティオの明日は守られたぞ!!」
「イヤッホー!!見たか、ベルカの連中。この俺の、PJの飛び方、良く覚えておけ!」
「へへ、ざまぁみやがれ、ベルカの野郎!!これに懲りて二度と悪さはするんじゃねぇぞ!!」
傭兵たちの喜びが爆発する。全く、この期に及んで核を投下するなど、正気の沙汰ではない。落とされた連中も命令に従っただけだろうが、たとえ同じ民族の血が流れる同胞であったとしても、そんな蛮行を認める必要は無かった。敵の姿が消えたバルトライヒの山々は、もとの静けさを取り戻しつつある。これで俺たちがここから立ち去れば、この空には元通りの美しい自然が残る。俺はシートに背中を預け、軽くため息を吐き出した。一仕事終えた安堵感が、心の中に広がっていく。普段なら、後はイーグルアイの戦闘終了の宣言と帰投命令を待っていれば良かっただろう。だが、イーグルアイ――マッケンジー少佐の声の変わりに聞こえてきたのは、耳障りな激しいノイズ。そして、俺の機体のレーダーが突然真っ白になって機能を失う。
「何だこ…ゃ!?…が……どうな…た!?」
「ECM!敵……手でも……ていたのか!?駄目……レー……が利……い!!」
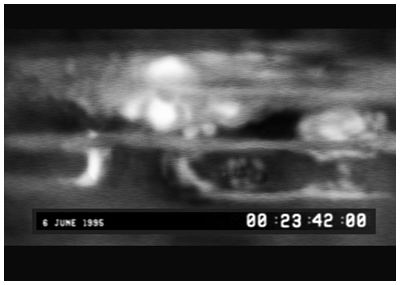 勝利の余韻は未知の恐怖へと姿を変える。敵の姿は確認できない。ゆっくりと旋回をしながら、俺は高度を上げていくルートを取った。その間、首を巡らせて辺りをうかがう。周辺、仲間たちの機影以外は確認できず。やはり敵影無し。ふと俺は、いつもならあるはずの左翼に、相棒の姿が無いことに気が付く。今日の奴は、明らかにおかしい。戻ったら、酒を傾けつつ話し合ってみよう、そんなことを考えていた瞬間だった。太陽が昇り、朝の光を弾けさせた――最初、俺はそう思ったのだ。だがその方角は太陽の方向ではないし、もっと禍々しい色に染められていた。そして、相当な遠方であるはずなのに、衝撃と轟音が俺たちの機体を容赦なく揺さぶる。レーダー画像が機能を回復するが、ノイズまみれの画像ははっきりとは見えず、電気系統にも障害が発生したようで、普段は点灯しているのを見たことも無いコーションランプが点滅している。ずっと遠くで、膨れ上がった光が、ゆっくりと薄れていく。機体の外的損傷は見られないが、電気系統、一部がアウト。幸い、操縦系統には問題なし。だが、ヴァレー組の何人かの機体は、物理的に破壊されたわけではないのに、戦闘機動はもはや不可能、という状況に追い込まれる。
勝利の余韻は未知の恐怖へと姿を変える。敵の姿は確認できない。ゆっくりと旋回をしながら、俺は高度を上げていくルートを取った。その間、首を巡らせて辺りをうかがう。周辺、仲間たちの機影以外は確認できず。やはり敵影無し。ふと俺は、いつもならあるはずの左翼に、相棒の姿が無いことに気が付く。今日の奴は、明らかにおかしい。戻ったら、酒を傾けつつ話し合ってみよう、そんなことを考えていた瞬間だった。太陽が昇り、朝の光を弾けさせた――最初、俺はそう思ったのだ。だがその方角は太陽の方向ではないし、もっと禍々しい色に染められていた。そして、相当な遠方であるはずなのに、衝撃と轟音が俺たちの機体を容赦なく揺さぶる。レーダー画像が機能を回復するが、ノイズまみれの画像ははっきりとは見えず、電気系統にも障害が発生したようで、普段は点灯しているのを見たことも無いコーションランプが点滅している。ずっと遠くで、膨れ上がった光が、ゆっくりと薄れていく。機体の外的損傷は見られないが、電気系統、一部がアウト。幸い、操縦系統には問題なし。だが、ヴァレー組の何人かの機体は、物理的に破壊されたわけではないのに、戦闘機動はもはや不可能、という状況に追い込まれる。「ヒル……ブルク基地、応……よ、……デス……ク基地!くそっ、誰も………のか!?」
「ワーグリン!……そ……余裕は無い!……ろ!!後……敵機!!」
かろうじて回復した通信に飛び込んできたのは、どこかの戦闘を告げる交信。必死に基地を呼ぶ若者の声は、沈痛そのものだ。しかし一体今のは何だ!?閃光、衝撃、そして電子機器の故障――知識の一つでしかなかった事象に、俺の記憶が辿りつく。しかし、それは……!
「もう、この戦争に大義などない。相棒、悲しいけれど、もう潮時だ」
それは、背中を安心して任せられるはずの相棒のものなのに、その声に俺は戦慄を覚えた。背中を任せられるのではなく、背中を脅かされる――そんな雰囲気に、コクピットの中の気温が一気に低下したかのような錯覚を覚える。だが、ラリーに「何が潮時なのか」、そう尋ねるよりも早く、ノイズ交じりのイーグルアイの叫びが飛び込んでくる方が先だった。
「警告!南西方向より、敵戦闘機部隊の接近を確認!数は8!現在、細かい戦況分析は全く出来なくなっている。全機、気を抜くなよ。作戦行動継続可能機は、敵部隊を迎撃せよ!先程の閃光と、何か関係があるかもしれない!!」
くそ、質疑応答は後回しってか!機首を引き上げ、高度を稼ぎながらインメルマルターン。今度は相棒も指定位置に付いて同様に反転。今はさっき感じた悪寒を確かめている余裕は無い!俺たちに続いて、ガイア、PJ、そしてシャーウッドが反転し、俺たちの正面から突っ込んでくるらしい敵部隊へと相対する。何が起こったのか、今の俺たちに知る術は無いが、今は何より生き残ることが先決――残存弾数と残燃料を素早く確認して、俺は愛機を加速させた。何にしても、難しいことは基地に戻ってからだ!!ぼんやりとしか映らないレーダーに、確かに敵戦闘機部隊の姿が映し出される。少々パニックに陥りかけた心を静めて、気合を入れ直す。自分に言い聞かせるように、俺は交戦を宣言した。
「ガルム1、エンゲージ!!」