遥か高空へと上昇していく「V2」の姿はもう雲の向こう側へと消え、コクピットの中から確認することは出来ない。だが、見えないだけで今こうしている間にも破滅のときが迫っている。もう残された時間は少ない。――ラフィーナ!俺はディレクタスの街で、俺の帰りをきっと待ち侘びているに違いない彼女と娘たちの顔を思い浮かべていた。決して失うわけにはいかない、かけがえのない宝物。お前に奪われてたまるか、ラリー!!
「イーグルアイよりガルム1、「V2」の発射制御を片羽の妖精が握っている。奴を止められるのは君しかいない。円卓の鬼神、健闘を祈る――!!」
ああ、勿論だ。――やってやる。照準レティクルの中に奴の機体を捉えた俺は、唯一の弱点であるエアインテーク目掛けて機関砲弾を撃ち込んだ。ADFXからも応射。互いの放つ攻撃が交錯し、虚空を貫く。命中弾なし。高速ですれ違った奴の姿を追って、強引にインメルマルターン、急反転。圧し掛かるGが容赦なく身体中を軋ませ、苦痛と激痛とが全身を刺激する。だが痛みを感じている間は意識を失うことは無い。歯を噛み締め、HUDを睨み付けて、スロットルを離さない。愛機はこれでも限界までまだまだ余裕がある。俺さえ耐えられれば、もっと飛べる。もっと早く、もっと鋭く。スペックでは現行の戦闘機たちを凌ぐに違いない奴の機体に追い付くには、それしか無い。そうでなくてもタイムリミットが存在する戦いだ。無理を承知で俺は奴に襲い掛かった。俺の姿が射線上に捉えられる前に奴の正面を取った俺は、再びその鼻先目掛けて機関砲弾を叩き込む。曳光弾の筋が明後日の方向に弾き飛ばされていく。祖国ベルカの科学力には驚きよりも呆れてしまう。何発か、障壁を貫いたものもあったようだが、有効打にはならない。むしろADFXから至近距離で放たれたミサイルが機体を掠め、さらにすれ違いざまに浴びせられたガンアタックがコクピットのすぐ側を通過して、どっと吹き出した冷や汗が俺の背中とコクピットの中を冷たく濡らした。
「なあ相棒、国境が俺たちに何をくれた?この星の大地のどこに国境線なんてものが見える?そんなものは、まやかしだ。人間が勝手に作り出した線だ。そんなものに意味は無い。かつて祖国を追い出されたお前なら、よく分かるだろう。違うか?」
「確かにお前の言う通りかもしれない。国境、民族、宗教、エトセトラ。そんなものを口実にして戦争をやりたがる連中が一度だって前線に立ったことは無い。代わりに俺たち兵隊が命を削りあう。今の俺たちのように――」
「だから、そんな世界をリセットしてやろうというのだ。そのための、「V2」だ」
「言ってることは立派だがな、その目的のために何の関係もない人たちを焼き殺すことのどこに大義がある?それは単なる虐殺だ。お前の――いや、国境無き世界のやろうとしていることは、世界規模の虐殺を単に正当化しているだけだ。お前だってもう分かっているんだろう!?」
「――俺はブリストーたちとは違う。世界のためなら、俺は全てを憎むことが出来る」
「この世界の人間の運命を全部背負ったつもりか、相棒!いつから神に成り上がった!!」
ADFXの後方に回り込んで、その後姿を捕捉する。ミサイルシーカーが奴の姿をはっきりと捉える。右へ急旋回し、こちらの追撃をかわそうとする奴の姿をさらに追う。垂直に切り立った天地が右から左へと流れていく。旋回方向を変えようとする刹那、奴の動きが一瞬止まる。その機会を狙って、残り少なくなってきたミサイルを放つ。その瞬間を待っていたかのように、ラリー機が急機首上げ、前進翼の特徴ある姿が目の前に迫り、そして後ろへと流れていく。速度を落とし、俺をまんまとやり過ごしたラリー機は、後方でくるりと機体をロールさせて、俺の後背にへばり付く。形勢逆転。俺には奴のような反則技のような防御機構は無い。つまり、逃げるしかない。脱兎の如く!圧倒的な推力を発して、ラリー機が俺を追撃している。シートの角度だけでなく、コクピットにも色々と工夫が加えられているのだろう。そうでなければ、あれだけ大柄の機体をあんな無茶な機動で振り回すことは出来ない。右へ、左へ、俺は愛機を振り回して奴の追撃から逃れるべく操縦を続ける。焦りは禁物。奴と俺の技量が拮抗している以上、ほんの少しのミスが致命的な失敗に繋がりかねない。背後から威嚇射撃のようにミサイルが、機関砲弾が浴びせられる。相手のペースに乗せられたら負けだ。自分に言い聞かせながら、回避機動を続ける。奴が完全に俺を捕捉することが出来ない、ということは、俺の機動は今のところ間違っていないのだから。
「――仕切り直しだ、相棒。まさか追いついていけないとは、予想外だ。こっちの身体がもたん」
「これだけ追い回しておいて、良く言うぜ。こっちのスタミナ切れを待っているんじゃないのか?」
「だがタイムリミットを忘れるなよ、相棒。俺を止めなければ、お前に勝ちは無い」
俺の背後から離れた奴の機体が、あっという間に見えなくなる。俺も反対方向へと逃れ、虎口から逃れることに成功する。ハーネスに散々絞られ、痛みを発する身体を軽く擦る。これをずっとは続けていられない。その前に、俺の身体がぶっ壊れちまう。内臓がいくか、骨がやられるか。運が悪ければ即死ということも有り得る。――やれやれ、似合わないほどの重荷を背負っているのは俺じゃないか。圧倒的に高性能な機体を操り、今や世界の生殺与奪を手に入れた相棒。それに立ち向かうのは、機関砲弾もミサイルもいよいよ残り少なくなったフラフラのこの俺。仲間の死をこれ以上見たくないという俺のエゴが招いた結果だから仕方ないが、重荷に押し潰されそうだ。弱気は気持ちだけでなく、体の力すら萎えさせる。病は気から。良く言ったものだ。プレッシャーを認識してしまった俺の心と身体が、萎んでいくような錯覚を感じる。これが絶望という奴なのか。俺はここまでの男だったのか。多くの仲間たちを犠牲にして、俺たちの背中を追い続けて飛んできた仲間を失ってまでして辿り着いたのは、勝ち目の無い戦いで空しく敗れていくことなのか――。憎しみを糧とした奴が最も強いというのなら、この世界のどこに救いがある。
「サイファー、しっかりして下さい!!大丈夫、まだ時間はあります。諦めないで!!」
「こちらポップス。聞こえるかな、円卓の鬼神?ベルカのエースたちとの連戦を生き延びた君が、こんなところで終われるはずは無いだろう!?目を開け。前を見ろ。まだ君の翼は折れていない。守るべきものがあるのなら、立ち上がれ!!」
目を閉じかけた俺の心を、仲間たちの声が叱咤する。シャーウッドが、ウスティオの仲間たちが、そして今日ここに集ったエースたちが。――思い出せ。俺は何のために飛んでいる?何のために戦っている?何のために今ここでこうして、相棒と戦っている?何のために、相棒を倒そうとしている?――そうか。俺には戦わなくてはならない理由が、確固たる理由があるじゃないか。かつて、一人の未来をこの手で奪ったときから、俺の両手は血塗られている。だが、そんな俺であっても、戦闘機を操り、戦い続けることで守れるものがある。それは、奪われる必要の無い、無数の人々の未来。無数の人々の明日。結局人間は争いを止めることは出来ないのかもしれない。これからもこの世界のどこかで戦争は起きる。だが信じあうことが出来るのも人間だ。国境、民族、宗教、確かにそれらは人と人とを区別して戦いを生む温床となるのかもしれない。だがその垣根を越えていけるのも人間だ。そこに核の恐怖による統治など必要ない。互いが互いを信じること。このアヴァロンの空に集ったパイロットたちが、同じ目的のために轡を並べて戦ったように、それは簡単に出来ることなのだ。きっとこれからも、それは出来る。憎しみをぶつけ合い、傷つけあうために、人間は生きているんじゃないのだから。俺たちは、語り継いでいかねばならない。争いを生むのが人の心なら、戦いを止めることが出来るのも人の心なのだ、と。戦争が全てを解決することも無ければ、破壊と殺戮と恐怖が世界を平和にすることなど決して有り得ないのだ、と――。
「こちら海兵隊第115連隊、ハーリングだ。もう見てられねぇ。全員、要塞に突入開始!!俺たちのために戦っているアイツにだけ、厄介事を押し付けていられるか!!命令が何だ、糞喰らえだ!!」
「オーシア第101空挺師団より、上空の航空部隊へ。我々の待機地点から、地上の要塞施設は目前だ。これより基地内に突入、「V2」の制御施設を制圧に向かう。止めても無駄だぞ。全部終わったら、このダムの上で祝杯をあげよう。……よし、行け行け行け行けーっ!!」
「ヴァレンタイン1より、各機、地上部隊の援護に回るぞ」
「こちらルーク1、気が合うな。片羽の妖精の相手は俺らじゃ不足だが、要塞相手なら話は別だ。彼らの突入を支援する――!!」
「レックレス了解!オーシアの連中たちにだけ任せていられねぇからな。ウスティオの傭兵の意地を見せるぞ!!」
まだ火災の続くアヴァロンを制圧するべく、地上部隊の猛者たちが歓迎の火線をものともせず飛び込んでいく。低空を飛翔する連合軍戦闘機の支援を受けながら、フル武装の兵士たちが次々とハッチの中へと飛び込んでいく。また少し離れた発電設備にも、空挺師団の一部隊が突入を開始していた。既に水の無いアヴァロン要塞が稼動するためには、膨大な電力を必要とする。発電に要した熱を排熱する都合がある以上、地下深くに発電施設を設けることが出来ないアヴァロンは、周辺に大規模な電力施設を別途持っていた。だが、その施設が制圧されることは、要塞の機能自体の大幅低下に繋がる。残されたわずかな時間の中でどれだけの効果が得られるのかは分からない。だが、誰もがもう黙って見ていることが出来なくなっていたのだ。片羽の妖精の繰り出す猛攻をしのぎながら戦い続ける「鬼神」の後姿に。絶望するのではなく、最後まで希望を持ち続けること。自分たちに出来ることを果たすこと。上で戦い続ける男のためにも、指を銜えて待っているようなことだけはしたくない。
「――あと3分だって?上等だ、まだ3分もある。飯の1食ぐらい、それだけあれば作れるぞ。エレメントより上空待機の各機へ。湯でも沸かして待っていてくれよ?」
「空中給油機に熱湯でも積み込ませておくか?ワイバーンよりエレメント、携帯食料積み込んでいるのか?お湯だけあっても仕方ないぞ」
仲間たちが冗談半分に口走った一言。だがそれは戦士たちを奮い立たせるのには最高の一言だった。「まだ」時間がある。「まだまだ」出来ることがある。後悔は全て終わってからすればいい。だが、「まだ」何も終わっていないのだから。
一度は止んでいた砲火が地上――アヴァロンのあちらこちらで赤い光を瞬かせる。残されたタイムリミットは3分を切った。そろそろ大気圏外を飛ぶ「V2」の弾頭が、ゆっくりと弧を描いてウスティオの上空を捉え始めた頃だろう。だが、「まだ」3分ある。全く、弱気な自分が嫌になる。こんな俺を見たら、きっとラフィーナにはどつかれるに違いない。私はそんな情けない男を亭主にした覚えは無い、と。無意味にADFXとのすれ違いを繰り返し続けた俺は、再び目を見開いて奴の――ラリーの姿をはっきりと捉える。仲間たちが諦めていないのに、どうして俺だけ負けた気でいられる?ここで奮い立たないような軟弱な男に、俺はなりたくない。ADFX、ループから水平に戻し、俺を狙って突撃体勢。こちらも同様に奴の姿を捉える。弱点は、奴のエアインテーク付近のみ。少しでも命中すればいい。照準レティクルの中に捕捉した相棒目掛けて、ミサイル発射。続けてガンアタック。残弾ゲージかコマ送りで減少していく。向こうからもミサイルと機関砲弾の雨が降り注ぐ。曳光弾の筋を機体をロールさせて回避し、襲い掛かるミサイルの白煙をかいくぐり、再び至近距離からすれ違いざまの攻撃を仕掛けて離脱。効果があったかどうかは分からない。諦めるな。飛べ、そして戦え。自分の心を叱咤して、操縦桿を手繰り、スロットルを押し込む。強引に機体を振り回して再び奴の正面を捉えるべく旋回。身体の疲労はとっくにピークに達している。だが、得体の知れない熱と力が、俺を突き動かす。
「そうです、サイファー。それでこそウスティオの鬼神です!攻撃は効いています。さあ、我々の意地を、あなたの意地をラリー君に見せてやるのです。ヴァレーのエースたちを舐めるな、とね!!」
「イマハマの旦那、アンタそんな熱い男だったとは知らなかったぜ」
「私も知りませんでしたよ、ついこの間まではね。でも今は、あなたをぶん殴ってやりたくて仕方ないんですよ、片羽の妖精」
再び真正面からの集中攻撃を浴びせあう俺たち。奴の障壁を突き抜けた数発が、ついに奴の機体に穴を穿つ。同時に鈍い振動が機体を揺らし、右のカナードが真ん中からへし折れ、機体を掠めた数発が愛機に傷を刻む。相撃ちか。衝突を避けるべくバレルロール。ラリーも同様に反対方向へと逃れていく。だがそこに、弾け飛んだカナードがあった。高速ですれ違うラリー機と接触したカナードは、跡形も無く粉々に砕け散る。それは予想外の「攻撃」だった。ADFXの機体の上をバウンドした翼は、奴の障壁に粉砕される前に、機体上部を引き裂くことに成功していたのだ。バランスを崩したADFXが薄煙を引きながら高度を下げていく。致命傷にはもちろんなっていないに違いない。なら、致命傷を与えてやればいい。攻撃は命中している。奴の機体が俺の愛機を上回る性能を持つというのなら、その上を行くべく飛べばいい。一足先に旋回を完了したラリー機から、ミサイルが連続して放たれる。その機動、ミサイルとの距離、抜けられる空間。目が捉えた情報に身体が反応し、そして機体へと伝わる。白い排気煙を潜り抜けた俺と愛機は、至近距離からのミサイル攻撃――最後に残っていたミサイルを奴の鼻先へとぶち込んだ。そのまま低空へとパワーダイブ。ミサイルの爆発に巻き込まれないように少しでも距離を稼ぐ。火球がすぐ後ろで膨れ上がる。吹き飛ばされた破片が尾翼と機体を叩くが、悪運だけは良いらしく損害を受けずに低空へと一気に舞い降りる。
 一方、相棒の方はそうはいかなかった。奴の機体の放つ障壁は確かにミサイルの針路を捻じ曲げる事には成功していた。しかし、弾頭の炸裂による衝撃波と爆風と、そして撒き散らされる破片の全てを防げるほどの代物ではなかった。衝撃波によって上へと跳ね上げられるADFX。その右エアインテークに、殺到した執念の攻撃が、障壁を貫き、そして内部へと飛び込んでいった。エアインテーク入り口が引き裂かれ、中に飛び込んだ破片のいくつかは内側から機体を貫通した。そしてタービンブレードを粉砕し、エンジンの中枢へとめり込んだ破片は、砕け散ったブレードの破片と共にエンジンの中をかき回し、引き千切ったのである。今度こそ、がくん、と大きくバランスを崩したADFXの右エンジンから黒煙が吹き出す姿を、後ろに俺は確認した。こちらも無傷ではないが、俺はまだやれる。苦しい戦いを共に潜り抜けてきた愛機のことを、俺は一番良く知っている。中に乗っている人間同様、往生際の悪いこの機体だ。そう、この機体には俺だけでなく、俺たちをヴァレー空軍基地で見送った、これまた往生際の悪い整備兵たちや基地の仲間たちの想いが込められている。こんな損害は、かすり傷にもならない。若干機動性能は落ちているのかもしれないが、それは片肺飛行になったラリーとて同様だ。さあ、そろそろ決着を付けよう。俺の残された武器は機関砲のみ。なぁに、やってみせるさ。
一方、相棒の方はそうはいかなかった。奴の機体の放つ障壁は確かにミサイルの針路を捻じ曲げる事には成功していた。しかし、弾頭の炸裂による衝撃波と爆風と、そして撒き散らされる破片の全てを防げるほどの代物ではなかった。衝撃波によって上へと跳ね上げられるADFX。その右エアインテークに、殺到した執念の攻撃が、障壁を貫き、そして内部へと飛び込んでいった。エアインテーク入り口が引き裂かれ、中に飛び込んだ破片のいくつかは内側から機体を貫通した。そしてタービンブレードを粉砕し、エンジンの中枢へとめり込んだ破片は、砕け散ったブレードの破片と共にエンジンの中をかき回し、引き千切ったのである。今度こそ、がくん、と大きくバランスを崩したADFXの右エンジンから黒煙が吹き出す姿を、後ろに俺は確認した。こちらも無傷ではないが、俺はまだやれる。苦しい戦いを共に潜り抜けてきた愛機のことを、俺は一番良く知っている。中に乗っている人間同様、往生際の悪いこの機体だ。そう、この機体には俺だけでなく、俺たちをヴァレー空軍基地で見送った、これまた往生際の悪い整備兵たちや基地の仲間たちの想いが込められている。こんな損害は、かすり傷にもならない。若干機動性能は落ちているのかもしれないが、それは片肺飛行になったラリーとて同様だ。さあ、そろそろ決着を付けよう。俺の残された武器は機関砲のみ。なぁに、やってみせるさ。「まだだ、まだ終わりじゃないぞ、相棒!!」
黒煙を引きながら、ADFXがゆっくりと旋回している。恐らく次の一撃が決着を付けることになるだろう。狙うは一点。奴の傷付いた右エンジンを吹き飛ばす。
「そろそろ決着といこう、ラリー」
「同感だ。それにしても、ここまでやられるとは思いもしなかったぜ。さすがは相棒だ」
「――俺はこんな風に戦いたくなかったよ」
「本当に、火付きの悪い奴め。――さあ、いくぞ相棒!」
右旋回から機体を水平に戻したラリーのADFX、俺の真正面から加速を開始。さすがに一方のエンジンを潰された影響で、さっきまでの鋭さは見えない。こちらも奴の姿を正面に捉えて、スロットルを押し込んでいく。残された機関砲の残弾は、あと僅か。俺に残されたチャンスは、この1回きり。これが最後だ。この機会を逃せば、俺に勝機は無い。だが、残された時間、仲間たちがラリーを追い詰めるだろう。それだけは避けたかった。互いに加速しながら大空を疾走する。彼我距離はあっという間に近づき、互いの姿が肉眼で確認できる距離まで接近する。黒煙を吐き出しながら突進する相棒の姿が、照準レティクルに捉えられる。俺の姿も、きっと捕捉されているだろう。
「撃て、臆病者!!俺を止めるんだろう?撃て!!」
ギリギリまで引き付けて……実際にはほんの僅かな時間が、限りなく長く感じられた。点にすぎなかったADFXの姿が膨れ上がり、目の前へと迫ってくる。狙うは奴の傷付いた右エンジン。
「撃て!!」
ラリーの絶叫。その声が聞こえるのと同時に俺は反射的にトリガーを引いた。残されていた機関砲弾が一斉に飛び出して、ADFXへと襲い掛かる。残弾ゲージはあっという間に一桁になり、そしてカウントは「0」を示した。当たっていてくれよ――!!目の前にラリーの姿が肉薄する。ほとんど激突寸前の至近距離で、俺たちは互いに90°ロール。互いの腹が触れるほどの僅かな距離で、俺たちはすれ違った。――相棒、何故打たなかった!?お前の機体にはまだ充分に弾丸が残されていただろうに。だがラリーは何も語らなかった。黒煙を吐き出しながら後方へと抜けたADFXの右エンジンが爆発を起こし、内側から機体を引き裂いた。真っ赤な炎が機体の右半分を覆い、傾きながらその姿が見えなくなっていく。そして虚空に火球を出現させたADFXは、全身に炎をまとって大空から叩き落されていった。
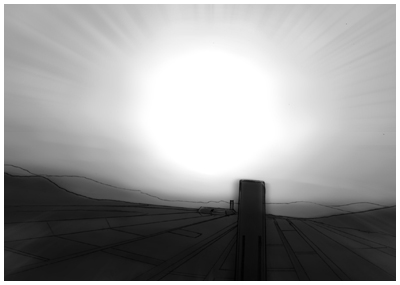 その直後、大空が真っ白な光に包まれた。まるで太陽が唐突に出現したかのような、圧倒的な光が、暗い雲に包まれていた大空を漂白する。そうだ、残り時間は――!?タイムリミットに俺は間に合ったのか?ディレクタスは――?しばらくの間空を漂白し続けていた光が、やがてゆっくりと薄れていく。その光景を、アヴァロンに集った者たちが見上げていた。ある者はコクピットの中から。ある者は、撃墜されて負傷した敵パイロットの肩を支えながら。ある者は自動小銃を肩に担ぎながら。
その直後、大空が真っ白な光に包まれた。まるで太陽が唐突に出現したかのような、圧倒的な光が、暗い雲に包まれていた大空を漂白する。そうだ、残り時間は――!?タイムリミットに俺は間に合ったのか?ディレクタスは――?しばらくの間空を漂白し続けていた光が、やがてゆっくりと薄れていく。その光景を、アヴァロンに集った者たちが見上げていた。ある者はコクピットの中から。ある者は、撃墜されて負傷した敵パイロットの肩を支えながら。ある者は自動小銃を肩に担ぎながら。「――イーグルアイより、ガルム1へ。「V2」は……「V2」は大気圏再突入前に自爆!!やったぞサイファー、ディレクタスは……世界は新年を迎えられる!!我々の勝利だ!!」
「こちらシャワークラウド。敵要塞アヴァロンから、無条件降伏宣言を受信した。繰り返す、国境無き世界は、無条件降伏を宣言した!!」
歓声が、最後の決戦場に木霊する。どうやら相棒が、最後の後始末を済ませてくれたらしい。戦いは終わった――そう悟った体と心に、疲労がどっと押し寄せる。出来るものならこのまま眠りたいところだが、居眠り操縦はご法度ものだ。地上にこの足で降り立つまで、俺のミッションはまだ終わっていないのだから。傷付いた俺の機体の周りに、ウスティオの仲間たちが集まってくる。下を見下ろせば、戦いを終えた兵士たちが両手を振って俺たちの姿を見上げている。落ちた奴の捜索、救助、国境無き世界の生き残りの捕縛――まだまだやらねばならないことは残っている。だが、ひとまずは終わった。少なくとも、俺に課せられたミッションは。
「――イーグルアイより、ガルム1へ。さあ、我々の家へ帰ろう。お前の帰りを待っている奴らがいる」
そうだ。俺には帰る家がある。仲間たちの待つ、ヴァレー空軍基地。そして、俺の帰りを首を長くして待っているであろうラフィーナたち、そしてスウィート・ホーム。ゆっくりと機体を傾けて、俺は針路をヴァレーへと向けた。
「ガルム1より、イーグルアイ、各機。ミッション・コンプリート。RTB」
戦いの終わった空を、戦闘機たちの群れが1機、また1機と通り過ぎていく。アヴァロンの空に静けさが戻るまでにまだ時間はかかるだろう。だが、この場にいる者は皆確信していた。哀しい戦いが、今こうして終わったのだ、と――。
 涙が止まらなかった。望みとおり、相棒たるレオンハルト・ラル・ノヴォトニーの手によって撃墜されていったラリー・フォルクの姿に。背中を信頼して預けていた相棒に、トドメを刺さなければならなかった円卓の鬼神の姿に。そして、国籍も民族も階級も関係なく、その垣根を越えて協力し合う連合軍の兵士たちの姿に。長い復讐の時を越えた先に見た、一つの可能性。それを現実のものにした円卓の鬼神の姿に――。既に敵の姿も見えなくなり始めたアヴァロンの空で、ロッテンバークは独り泣いていた。まだまだ、世界は捨てたもんじゃない。戦いを起こすのが人間ならば、平和を実現するのも人間。人間の心。世界は決して止まっているわけではないのだ。むしろ、絶えずゆっくりと進み続けている。時に誤った道へと転ぶこともあるだろう。だがそこから戻ることが出来る限り、人がその努力を怠らない限り、世界は何度だってやり直せるに違いない。円卓の鬼神が、片羽の妖精が、今それを証明してみせた。国境無き世界の指導者たちの言う浄化によってではなくして、だ。憎しみに染められた数年間、そして仇を追い求めたこの数ヶ月間、何かが吹っ切れた。その時間は、決して無駄ではなかったのだ。祖国の崩壊、円卓の鬼神との絶望的なまでの差、そこから立ち上がってきた今の自分は、多分明日も立ち上がれるだろう。ロッテンバークは、決心を固めた。全てを今こそ、やり直すために、祖国ベルカへ戻ろう、と。そして罪を償った暁には、今日のことを伝えられる職業に就こう、と。
涙が止まらなかった。望みとおり、相棒たるレオンハルト・ラル・ノヴォトニーの手によって撃墜されていったラリー・フォルクの姿に。背中を信頼して預けていた相棒に、トドメを刺さなければならなかった円卓の鬼神の姿に。そして、国籍も民族も階級も関係なく、その垣根を越えて協力し合う連合軍の兵士たちの姿に。長い復讐の時を越えた先に見た、一つの可能性。それを現実のものにした円卓の鬼神の姿に――。既に敵の姿も見えなくなり始めたアヴァロンの空で、ロッテンバークは独り泣いていた。まだまだ、世界は捨てたもんじゃない。戦いを起こすのが人間ならば、平和を実現するのも人間。人間の心。世界は決して止まっているわけではないのだ。むしろ、絶えずゆっくりと進み続けている。時に誤った道へと転ぶこともあるだろう。だがそこから戻ることが出来る限り、人がその努力を怠らない限り、世界は何度だってやり直せるに違いない。円卓の鬼神が、片羽の妖精が、今それを証明してみせた。国境無き世界の指導者たちの言う浄化によってではなくして、だ。憎しみに染められた数年間、そして仇を追い求めたこの数ヶ月間、何かが吹っ切れた。その時間は、決して無駄ではなかったのだ。祖国の崩壊、円卓の鬼神との絶望的なまでの差、そこから立ち上がってきた今の自分は、多分明日も立ち上がれるだろう。ロッテンバークは、決心を固めた。全てを今こそ、やり直すために、祖国ベルカへ戻ろう、と。そして罪を償った暁には、今日のことを伝えられる職業に就こう、と。どうやら、この空を飛び続ける理由が無くなったらしいことにロッテンバークは気が付いた。いや、最初から彼は戦う必要が無かったのだ。亡くなった父親が、復讐を望んでいただろうか。少なくとも、当時の自分はそう考えた。だが、父親の夢は何だったか。自分を復讐鬼にすること――?違う。そんなことを父が望むはずも無かった。円卓の鬼神は、今でもあの日のことを夢に見て、苦しみ続けているという。それだけで、充分だった。父の記憶が失われることが何より怖かった。だが円卓の鬼神は、未だに忘れていない。父親にとっても、そして円卓の鬼神にとっても不幸な結果。それを招いたのは、残念ながら強国たるプライドを維持しようとしていた祖国でもある。ならば、社会を変えるしかない。不幸な結果を招いた原因を取り除かねばならない。手に入れた未来、明日をそうやって過ごしていくことが出来れば――。ロッテンバークはバイザーを上げ、グローブで滲んだ目を擦った。クリアになった目で、空を、そして地上を見る。戦いを終えた要塞の上に、粉雪が舞い降りていく。再び、「北の谷」に本格的な冬がやってくるのだ。だが、雪が解け、春はいずれやってくる。季節も巡る。人もまた然り、だ。戦争という冬の時代を抜けた世界は、また新しい季節を迎えるために進んでいく。その流れを止めることなど、誰にも出来はしないのだ。
「ユーミル2、ロッテンバーク、ミッション・コンプリート。RTB」
それは誰も聞くことの無い帰還報告。たった1機のS-32が、引き上げていく連合軍部隊とは反対方向へと針路を取り、そして灰色の空へと消えていく。その後姿に、復讐鬼の面影は無い。――復讐は、果たされたのだ。
薄暗い部屋に設置されたディスプレイが、戦闘終了と国境無き世界の降伏を告げている。今ごろ兵士たちは喜びの歓声を挙げているに違いない。だが、部屋に集った男たちの表情は様々だった。勝利を素直に喜んでいる者。苦虫を噛み潰したような表情を浮かべている者。むしろ怒りの感情を爆発させている者。軍服姿の男たちはそれぞれの表情で、刻々と伝えられる情報を眺めている。
「――ブリストーの馬鹿者めが。これでは投資の全てが台無しではないか」
「彼は早まったのだ。ウスティオの青二才如きに打ち負かされるとは。――所詮、その程度の器だったということかもしれないが――」
「では、我々はどうすべきか。この戦いは「あってはならない」ものなのだ。各国政府をそれで納得させるためには、それ相応の材料と実弾が必要だ。――それに、知りすぎた者たちを放っておくことも出来まい」
議長席に座る男の発言に、他の男たちが同意の頷きを返す。そう、知りすぎた者――「円卓の鬼神」をウスティオに預けたままにすることは出来ない。幸い、良い"ケース"がある。ベルカのエースたちをアグレッサーとして配属した実績を、彼らは持っていた。同じ要領だ。今日の戦いを闇に葬るに足る餌をばら撒く。その代償として、「円卓の鬼神」の身柄を確保すれば良いだけのこと。これほど安い取引は無い、と思わせるに充分な投資は必要になるが――。
「なかなか貪欲ですな。このまま行くと、我らの空軍はエースの見本市になりますな」
「まぁ、そう言うな。諸君ら8492の実力は充分に分かっている。そこにもう一人エースが加わるだけだ。同じ血を持つ者同士、うまくやってもらいたいものだ」
そうと決まれば、動くべきときだ。先手を打たなければならない。この戦いを終わらせたのは、祖国で無ければならないのだ。ウスティオのエース如きに戦争を終わらされるなど、超大国のプライドが許さないのだから。
「――では、ウスティオ方面への工作は、アップルルース君、君に一任しよう」
方針は決定された。立ち上がった男が了解の意を伝え、早速部屋から出て行く。そう、世界を導くのは人ではない。超大国の力こそが導くのだ。"オーシア"こそが、世界を導く。そのために、円卓の鬼神の存在を彼らは否定しなければならない。本来なら、最大の恩人であるはずの、連合軍のトップエースの存在を――。