ハイライン・ロッテンバーク
彼の経歴は極めて複雑である。ベルカ空軍 第2航空師団第52戦闘飛行隊に当初所属も部隊が壊滅し、その後第13夜間戦闘航空団第6戦闘飛行隊へと配属。さらに、「国境無き世界」の航空隊に属するという経歴を持つのだ。
彼は、「鬼神」への復讐を果たすために戦闘機乗りの道を選んだ男。そして、最後の戦いを「国境無き世界」の立場から見届けた男。彼をエースと呼ぶことが出来るのかどうか、そこは人により評価が分かれるに違いない。エスケープキラー時代の罪状を問われ、戦犯として一時収監。現在は、ハイスクールの教師として、忙しい日々を送っている。
「――私が空を目指したのは、父親の仇を討つためだった。私の父親は、私が子供だった頃に殺された――「鬼神」にね。だから正直なところ、あまり良く若い頃のことを覚えていない。私にとって、学生生活も軍人としての日々も、全ては復讐を果たすための通過点でしかなかったんだ。父親を殺してのうのうと生き延びているだけでなく、気ままな傭兵生活を送っている「鬼神」を許せなかったんだ、当時の私は。だが、正規軍の兵士に出来ることは実は少なかった。世界中の戦場を渡り歩く傭兵を追うことなど出来はしないのだからね。だから――祖国が世界に対して戦端を開いてくれたことが嬉しかったよ。必ず仇はこの戦場のどこかに現れる。この私の手で血祭りにして、父親の仇を討つんだ――そんなことばかり考えていた」
――しかし、現れた「鬼神」は想像以上の強さだった?
「その通り。フレイジャー隊長の下で、私もエースの一人としての自負を持っていたつもりだった。だが、彼の技量も強さも、私の想像を遥かに上回るものだったんだ。まさに、無数の戦場と修羅場を潜り抜けてきた男ならではの戦術眼、戦況を瞬時に見極める判断力、機体性能を存分に発揮出来る操縦技術――私は全ての面で劣っていた。だから、今死ぬわけにはいかない。例え隊長たちを見殺しにしてでも。……戦場から逃走したのは賭けだった。敵前逃亡は重罪だ。一つ間違えれば銃殺刑ものだ。私は、彼に勝つためにはもっと非情になることが必要だと考えたんだ。賭けには勝ったよ。ベルカ空軍の中でも、最も悪名高く、最も非情な部隊へ私は転属することが出来たんだからね。ズボフ隊長の下で私がやっていたこと――それは味方殺しと虐殺だった。軍は戦意高揚のためなら役に立たない後方基地を「始末」することに何のためらいもなかったんだ。そして私の属する部隊はその尖兵としてこき使われた。私はそんな戦いの中で、決して動じない冷酷さと非情さを見に着けたつもりだった。祖国が自らの大地と同胞を焼き払ったあの日、ようやく再会した彼に私は決して負けるはずは無いと確信していたよ。でも、結果は完敗だった。完膚なきまでに、私は打ち負かされたんだ」
――その後のあなたの消息は半年以上途絶えています。その間に、何があったんですか?
「不時着した私は、本当に偶然、「片羽の妖精」たちに拾われたんだ。そう、私は「国境なき世界」の男たちによってこの命を救われたんだよ。当時、実際問題として組織のパイロットは不足していた。でも私は空っぽになっていた。空を飛ぶべき理由を見失ってしまったんだ。どう足掻いても、私は彼には勝てない。このままでは決して勝てない。それが分かってしまったんだ。――そんな私を、「片羽の妖精」が鍛え直してくれた。そして、私は初めて知ったんだ。「鬼神」が、今でも私の父親を殺した日のことを思い出して苦しみ続けているということを。彼もまた、人間としての苦悩を抱えた一人の人間であったことを、知ったんだ。そして同時に、不思議に思ったんだ。彼はどうしてあそこまで強く空を駆けることが出来るのだろう、と。そうしたら、色々と興味が湧いてきてね。復讐の決着がどうというより、純粋に彼のことを知りたくなったんだよ。そうして、私は「片羽の妖精」の2番機として再び空に上がったんだ」
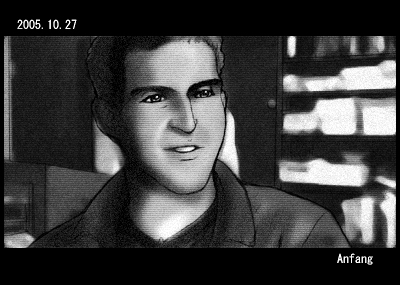 ――1995年12月30日、「国境なき世界」の最終拠点アヴァロンの空で起こった戦いを教えてもらえますか?
――1995年12月30日、「国境なき世界」の最終拠点アヴァロンの空で起こった戦いを教えてもらえますか?「あの戦いを私は一生忘れないだろう。彼とラリー隊長、互いに信頼して背中を預け、戦場を共に生き抜いた相棒同士が空で激突したんだ。隊長の乗る機体は、ベルカの科学技術を結集して作られた最新鋭機。彼の乗る機体は、ベルカの兵士たちを、そして「国境無き世界」の兵士たちを恐れさせた、F-15S/MTD。お互いが、お互いの信じる道とプライドを賭けてあの空で戦ったんだ。私たちはその戦いを呆然と見守るしかないくらい、激しい戦いだった。二人とも、実際には心を傷つけ合いながら飛んでいたのだと思う。そして、ラリー隊長は自ら退路を断った。世界を焼き尽くすための最終兵器「V2」を発射させたんだ。決着の制限時間は、弾頭が大気圏に再突入するまでの僅かな時間。――だがそこで、信じられないことが始まったんだ。連合軍の兵士たちが、逃げるどころか進撃を再開したんだよ。皆、彼の翼を見て奮い立ったんだ。まだ俺たちには出来ることがある、最後まで決して諦めるな――。「国境なき世界」は、最早人間を対立させるだけでしかない線、国境を消し去ることで人の心を解放しようとした。だが、連合軍の兵士たちは、階級も民族も思想も所属も乗り越えていたんだ。お互いが、お互いの心を信じて――皮肉な話だけど、我々が目指しそして為しえなかったことを、彼は実現して見せたんだよ。ついに、激しい戦いは彼の勝利に終わった。私は泣きながらその光景を目に焼き付けていたよ。世界は、人間は、まだまだ捨てたもんじゃない、と確信した瞬間であり、私の戦いが全て終わった瞬間でもあったんだ」
――「円卓の鬼神」に再会したら、どうしますか?
「とりあえず、一発殴らせてもらう。その後は、じっくりと話し合ってみたい。私が教師の道を選んだのは、極右政権の精神に惑わされて若者の心を傷つけてしまった父親や、必要の無い差別を公然と認めるような社会で傷ついて祖国を負われる羽目になった彼のような、被害者を生み出さない社会を作りたいからだ。そのためには、若者たちに伝えるしかない。あの戦争の愚かさを。そして人の心を信じることの強さを。……私は、大切なことを「片羽の妖精」と「円卓の鬼神」に教えてもらった幸せ者なんだろうね、きっと」
校舎の窓の外に広がる夕暮れ時の赤い空を見上げて、ハイライン・ロッテンバークは楽しそうに笑った。この男が「復讐鬼」と呼ばれていたこと自体が信じられない。実際、私の持っている当時の彼の写真と、今目の前にいる男の顔は、全くの別人であるかのようだった。彼もまた、過酷な人生を歩んできた男の一人。過酷な時代を乗り越えてきた男の顔には、今すっきりとした笑みが浮かんでいる。
「実はね、戦犯として服役した後、フレイジャー隊長に謝りに行ったんだよ。思い切りぶん殴られて、叱られてしまった。当然だよ。私は隊長たちを見捨ててしまったんだからね。だけど、私に教師の道を勧めてくれたのも隊長だったんだ。おかげで、私はこうして穏やかな日々を送っている。妻と子供と一緒に、ね」
「私もフレイジャーさんをはじめとしたエースの皆さんにお世話になりっぱなしです。でもそのかいあって、こうして歴史の闇にもメスを入れることが出来ました。そして、貴重な証言をあなたから聞くことが出来ました。……ロッテンバークさん、一つ教えてください。私の取材が番組として放映されるにしても、決して報道しないことを誓います。彼の――「円卓の鬼神」の名を教えてくれませんか?」
顎に手を当て、目を閉じたロッテンバークがしばらく沈黙する。それほど長い時間ではなかったが、ゆっくりと頷いた彼が、私に視線を向ける。
「――レオンハルト・ラル・ノヴォトニー。それが彼の名前だ。そして、彼の父親はタイアライト・ラル・ノヴォトニー。かつて、銀色のイヌワシたちと共に飛んだトップエースの一人が、「鬼神」の父親だ。ケラーマン隊長は何も教えてくれなかったみたいだね。……それとも、自分で調べてみろ、ということだったのかな?」
私はケラーマンの老獪な笑い顔を思い浮かべてしまった。彼はある程度舞台裏を知ったうえで惚けていたのだ。全く、人の悪い好々爺だ。即ち、彼は「円卓の鬼神」の正体を知っていたということになるのだから。
「まあいいじゃないか。結果として、君は真実をまた一つ知ることが出来た。私のインタビューも、君が知りたいと欲する「鬼神」の姿を形作る良い材料になるだろうしね。……残るは、組織の首謀者たちかな?」
「それと、「円卓の鬼神」と共に飛んだ男たちです。ウスティオ空軍ヴァレー空軍基地に未だに在籍しているエースの話も、聞かなければなりません」
「"ウスティオの若き狂犬"だね。ふふ、彼の話を持ち出したら、ジョシュア・ブリストーはきっと嫌な顔をするだろう。自信満々の演説をぶち壊しにしたのが、"若き狂犬"なのだからね。私とあまり年齢は変わらないはずだけど、そんな若者に論破される程度の陳腐な大義しか、実はあの組織は持っていなかったというのが真実なのかもしれない」
恐らく、ロッテンバークの言うとおりだろう。調べれば調べるほど、「国境なき世界」の掲げた理想には疑問が湧いてくる。自分たちの理想に従わない者たちを焼き尽くしても構わない、という考え方の底辺にあるのは憎しみだ。だが、一方的に従わされる者たちもまた、憎しみを抱くだろう。結果、新たな争いが起こるに違いない。強大な軍事力と絶対的な力を手にしたものが世界を手中に収めることほど、人間にとっての悲劇は無い。結局、「国境なき世界」のやろうとしたことは、実は世界に戦争を仕掛けたベルカとほとんど同義なのだ。力を正当に扱う術を知った者こそ、世界を統治するに相応しいと考えていることがその何よりの証拠。まやかしの正義に意味が無いことを、ロッテンバークも、そして恐らくは「片羽の妖精」も悟っていたに違いない。だが、「片羽の妖精」は自分の選んだ道を貫き、そしてかつての相棒と相対した。……そんな悲しい話、あってはならない。
「……時に、"灰色の男たち"というのを聞いたことがあるかい?」
「灰色の男たち……ですか?いえ、初耳です」
「私も詳しいことは知らない。だが、祖国にはより統治者たちに近い勢力として存在はしていたんだ。私の属した組織も、彼らの支援や協力があったと聞いている。あの戦争後姿を消して、今尚「死んだ」とされていない政治家や軍人、貴族たち……その辺りを調べてみるといい。何か、掴めることもあると思うよ」
"灰色の男たち"――?私は愛用のメモ帳に素早くその言葉を書き込んだ。少なくとも、私がかき集め続けた資料の中に、その言葉が出てきたことは無い。そんな私の様子を、ロッテンバークは感心したように頷いている。ふと、廊下から声がかけられる。ロッテンバークの担当している部活動の教え子らしく、彼は話を中断して廊下の外へ歩いていった。それにしても、「鬼神」を追い続けることが、まさかこれほどスケールの大きな話になってくるとは思いもしなかった。彼も詳しくは知らないようだが、「国境無き世界」が莫大な資金や物資をベルカ本体、そして信じがたい話ではあるがオーシアなどから調達していたことは間違いなさそうだ。"灰色の男たち"の正体は不明だが、アントン・カプチェンコらが地下に潜伏して交渉をしていた相手に、その存在があった可能性は否定できない。
結局、この日の取材はこれで終わりとなった。彼の担当する部で怪我人が出てしまったため、付き添いで病院に行くことになってしまったためだ。その代わり、私は彼の自宅への招待をもらった。彼の知る「国境無き世界」の姿、そして「鬼神」の姿をもっと知るためにも、彼の好意に私は感謝した。事実、彼からもたらされた情報は後に番組を編成する過程において極めて重要な役割を果たすし、さらに5年後、私は改めて"灰色の男たち"の実態に出くわすことになったのだから――。
ハイライン・ロッテンバーク。
「円卓の鬼神」と「片羽の妖精」の後姿に、生きる道を見出した男。そして、歴史の闇に葬られた真実の語り部として、生き残ることを選んだ男。彼が空に上がることは二度とないかもしれない。だが、彼だからこそ、若者たちに伝えられる真実がある。彼の教え子たちが社会に巣立っていくとき、きっとベルカという国は新しい一歩を踏み出すことが出来るのではないか――そう、私は信じたい。