激闘、赤い戦闘機隊
グレースメリアの誇る大鉄橋の名は伊達ではなく、本来の目的地たる旧王城へと到達するまでに結構な時間が過ぎ去っていた。橋の上を逃げ惑う小さな人間の姿など、どうやら戦闘機を操る敵のパイロットたちの眼中には無かったことはラッキーだった。だけど、先頭を切って、きっと1,500メートル走のタイムを計ったら間違いなく最高記録と言えるようなペースで走り続けられたのは、マティルダを含めた数人だけだった。上級生の数人は、年少の、それも女に仕切られるのを潔しとしなかったのか、「子供を戦場で狙う兵士はいない。何をそんなに急ぐ必要がある?」と言って、途中からペースを落としてしまった。そうなってしまっては、マティルダに出来ることは無い。彼女と行動を共にしてくれる友人たちを励ましながら、ようやく橋の終結点、王城前の広場へと到達した頃、一際大きな轟音が、王様橋のしかもすぐ傍で響き渡った。膨れ上がる火の玉、海面から吹き上げられた水飛沫。そして、橋の欄干の外側へと舞い上がる人間の姿を、マティルダの瞳は捉えていた。どうやら父親譲りらしい、視力の良い眼が、こういう時は恨めしくなる。王様橋と海面の間には、数十メートルの高さがある。そこから転落した人間の生存可能性が限りなくゼロに近いことくらい、マティルダは理解していた。横転したバスの中から、この短時間の間に一体どれだけの人の死に様を目にしたことだろう?それでも、自分たちはまだ生きている。判断を誤ってしまった上級生たちを哀れだとは思うけれども、今は自分が生き残ることだけを考えるしかない。王城の下には、大昔の隕石墜落に備えて作られたシェルターが今でも残っていると聞いたことがある。そこなら、子供の身である自分たちでも何とか生き延びられるかもしれない――それだけが、マティルダにとっての心の拠り所だった。
まるで雷のように轟く戦闘機のジェット・ノイズを潜り抜けて、子供たちは王城入口の扉に辿り着いた。普段なら解放されているはずの扉は、硬く閉ざされていた。ノブを力いっぱい引っ張ってみても開くものでは無い。下級生たちの顔に落胆の表情が浮かぶ。それを見てマティルダは、内心は不安一杯に、でも外面は自信満々の笑みを浮かべて、どうやら「敵」の攻撃で捲れあがったアスファルトの破片の中から、手頃な大きさの塊を拾い上げた。歴史的建造物にはありがちの、無駄に大きなガラス面の一つの前に立ったマティルダは、大きく振りかぶってその塊を叩き付けた。バシャン、という派手な音を立てて砕け散るガラス。多分、それすらも歴史的価値とやらがあったのかもしれないが、それは子供の知ったところではない。「丁度手頃な」入口を確保したマティルダは、真っ先に「金色の王様」の待つ玉座の間へと足を踏み入れた。少し遅れて、何だか申し訳なさそうな表情を浮かべて友人たちもやって来る。そんな子供たちの仕種を、不思議そうな表情で見守る大人の姿に、「侵入犯」の首謀者たるマティルダは気が付かなかった。当の本人から、声をかけられるまで。
「王城のガラスを割って入ってきちゃ駄目じゃないか、お嬢さんたち」
「うわわわっと!?」
ぎょっとして振り返ると、重そうなガラスのショーケースを抱えた「大人」の姿が、思ったよりも彼女の傍にあった。背も父親やおっちゃんに比べればずっと小さくてしかも細いし、「精悍」という言葉とは無縁そうな、のんびりした口調と表情に、大きな眼鏡。ワイシャツのポケットに入れている懐中時計が、マティルダの興味を引いた。緊急事態の状況に姿を現した闖入者をしげしげと眺めていた男は、ショーケースを一旦カートの上に乗せてから、ぽん、と手の平の上に一方の拳を軽く当てた。
「ひょっとして、今日見学に来る予定だったクラスの子たちかい?ああ、残念だけど、今日は説明をしている暇が無いんだよ。何しろ、こんな状況下だからね。早く、安全なところに逃げた方がいい」
「帰れるなら帰ってます!王様橋は壊れちゃったし、乗ってたバスだって滅茶苦茶で……クラスメートたちだって、大変なことに……!」
そこまで言って、マティルダはバスの中で絶命していた友人たちの無残な姿を思い出した。じわりと滲んできた涙を強引に袖で拭い去り、改めて「大人」を見上げる。先程と変わらない表情ではあったけれど、いつの間にかマティルダの傍に立った彼は、しゃがみこむと同時に、一方の手を彼女の頭の上に置いた。
「どうやら僕が軽率だったみたいだ。済まなかった。ええと……ミス?」
「子供相手に何言ってんの。マティルダ・ハーマンよ。マティルダでいいわ」
「オーケー、マティルダ。僕はジャン・ロック・バレンティン。ここで歴史研究をしていた学芸員のなり損ないさ」
照れくさそうに笑いながら立ち上がったバレンティンは、手近にあるショーケースに手をかけると、どうやら出来る限りの力を込めてそれを持ち上げた。だが、その重みを支えられず、見事に足元がふらつく。かろうじてカートの上に置いた時には、肩で息を付いている有様だった。自宅にいても毎朝10km近くをランニングしてきて、ほとんど息を切らすことも無く、牛乳瓶を傾けていた父親の姿とは雲泥の差。あーあ、普通の大人ってのはこんなものなのかしら、とマティルダは首を振った。
「その学芸員さんが、どうしてここに残っているの?どこかの軍隊が攻めてきたんでしょ?逃げないの?」
「逃げたいのは山々だけど、ここの貴重な宝物をそのままにしておくのはもっと危険なんだ。だから、こうやって運ぼうとしているんじゃないか」
「その調子じゃ、運び終わる前に捕まっちゃうんじゃない?」
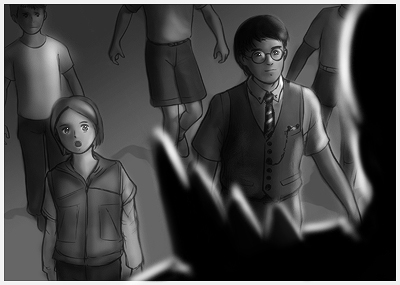 うっ、と詰まってしまったバレンティンの姿に、マティルダは手を顔に当てて首を振った。緊急事態ならそれなりのやり方ってものがあるはずじゃないか。見たところ、全然焦っているように見えないバレンティンは、どうやらご丁寧にケースを一つ一つ運び込もうとしているらしい。「普段は絶対にやっちゃ駄目だぞ」とおっちゃんが教えてくれた方法を思い出したマティルダは、自分の肩掛け鞄の中身を漁った。丸い形の目標物を探り当てた彼女は、素早くテープを「×」印にしてガラスケースに貼り付けると、次いで金属製の水筒を少し強めに叩き付けた。
うっ、と詰まってしまったバレンティンの姿に、マティルダは手を顔に当てて首を振った。緊急事態ならそれなりのやり方ってものがあるはずじゃないか。見たところ、全然焦っているように見えないバレンティンは、どうやらご丁寧にケースを一つ一つ運び込もうとしているらしい。「普段は絶対にやっちゃ駄目だぞ」とおっちゃんが教えてくれた方法を思い出したマティルダは、自分の肩掛け鞄の中身を漁った。丸い形の目標物を探り当てた彼女は、素早くテープを「×」印にしてガラスケースに貼り付けると、次いで金属製の水筒を少し強めに叩き付けた。
「うわああああっ!!なんてことするんだい、君は!」
「大丈夫大丈夫。ほら!」
そう言いながら、マティルダはテープをゆっくりと剥ぎ取った。テープの粘着力に引っ張られて、大きなガラスの破片がそのまますっぽりと抜ける。綺麗に開いた穴から、マティルダはまんまと「重要な宝物」の一つであるネックレスを取り出して、ウインクした。バレンティンは開いた口がふさがらないといった様子で首を振った。
「ほら、時間が無い!みんなも手伝って!バレンティンさんは宝物をしまう箱をカートに乗せて。学芸員なら、後でどれがどれだかの整理は出来るんでしょ?」
「ああもう……。ま、いいさ。こんな状況下に君たちを放り出すわけにもいかないからね。皆、済まないけれども手伝ってくれ。今マティルダ嬢がやったように、ケースは片っ端から割ってしまって構わない。こっちの整理が済んだら、本丸を片付けるよ!」
「本丸?」
「あれさ」
そう言いながらバレンティンが指差した先には、玉座に悠然と腰掛けた「金色の王様」の姿があった。あんな大きな物を、子供大多数と大人一人でどうやって?先程のバレンティンと同じように呆れた表情を浮かべたマティルダに、バレンティンは似合わないウィンクをしながら応えた。
「我に秘策アリさ。それも、とっておきの隠し場所付きでね」
時間と空間が凍り付いた。AWACSゴースト・アイから伝えられた指令は、グレースメリアの上空で奮戦を続けるパイロットたちを一瞬無言にさせることに成功していた。誰しもが、耳を疑ったに違いない。撤退命令は覚悟はしていたかもしれないが、「グレースメリアを放棄する」だって!?防空司令部からそのような命令が出てきたということは、恐らく全軍に対して同様の命令が下されたと見て間違いなかった。もっとも、これだけ彼我戦力に差が出てくると、ダッシュで逃げられる戦闘機と異なり陸軍と海軍の部隊は撤退自体が極めて困難な状況とも言えるに違いない。理性で考えれば妥当な判断かもしれないが、感情的にその命令を受け入れるのは難しかった。首都防衛の任を果たせず、首都を放棄して逃げる――それを詰られたとしても受け入れろ、とAWACSは同時に俺たちに求めているのだから。そして、当然のように反発が起きる。
『何を寝ぼけたことを言っているんだ。こちらウインドホバー、そのような命令は承服出来ない』
『こちらアバランチ。我々もこの街に残る。グレースメリアを見捨てることは出来ない』
その反発は至極当然のものだった。生き残りの他の部隊からも同様の声があがる。まして、俺たちは編隊飛行をしながらその命令を聞いているわけではない。数の攻勢を仕掛けてきているエストバキア空軍部隊との戦いを続けている最中なのだ。逃げるにしても、彼らの包囲網を突破しない限りは、撤退命令すら全う出来ないのが今の俺たちの立場なのだ。だが、そんなことは承知の上、と言った風でゴースト・アイの檄が飛ぶ。
『聞け!我々はグレースメリアから一時撤退する。その後――残存戦力を再編成して反攻作戦に転じる。そのためには、貴君らの戦力を今ここで失うわけにはいかないんだ。貴君らの気持ちは私とて充分に分かる。だが、ここは堪えて、命令に従ってくれ!!』
命令を下している方も辛い――ゴースト・アイが並みの指揮官だったら、淡々と撤退命令を繰り返しただけだろう。だが、本来格下が相手であるにもかかわらず、パイロットたちの心情を無下に否定しない当たり、ひょっとしたら昔は戦闘機乗りだったのかもしれない。その言葉が口先だけのものではないことを悟ったパイロットたちから、止むを得ない、という様子で、少しずつ「了解」の返答が返り始める。最終的な判断はタリズマンに委ねるとして、俺はレーダーに視線を映して状況を確認する。新市街上空に展開しているエメリア軍を包囲するようにエストバキア軍は展開中ではあったが、西方向の包囲網は手薄で第一陣さえ突破出来れば逃げ切れる可能性があった。
『こちらシャムロック。僕もこの命令は妥当だと思う。――行こう、タリズマン』
『こちらドランケンじゃ。ワシも同意見じゃよ。ちと骨の折れる奴を相手にしとるから、その後じゃがの」
「おいおい、いい歳して無理すんなよ、とっつぁん。シャムロック!援護に回れるか?」
『了解した。だが、いい腕だ。フランカーが形無しって様子だぞ』
シャムロックのF-16Cが右旋回。例の赤い戦闘機隊の1機と激闘を繰り広げるドランケンのF-16Cの援護ポジションに向かう。フランカーの高い機動性能に付き合うのではなく、小回りの効くF-16Cをコンパクトに振り回しながら、敵エースと互角に渡り合っているのであった。
『――気の毒だが、逃がしてやる義理は無い。各機、エメリア軍機の撤退を阻止せよ』
「やらせねぇ、って言ってるんだよ!エッグヘッド!MAAM、攻撃スタンバイ!!」
敵前で踵を返して脱出を図る友軍機たち。その後姿を狙おうとする敵部隊の真正面に、俺たちは飛び出した。どうやら足の長いミサイルを積み込んできているらしい敵編隊の一つを、ターゲットとして捕捉する。これを撃ち出せば、残ると短射程のAAMと機関砲弾のみ。
「タリズマン、正面右方向、ラファールの編隊を狙って下さい!」
「了解だ。……よし、捉えた。タリズマン、FOX3!!」
『ガルーダ隊、撤退命令に従い、西方面へ脱出しろ!敵戦力は尚も増大している』
「分かってる。だが殿(しんがり)も必要だろ。足の速い俺たちが、その役目としては適任だ。あの赤い連中の足止めもしなくちゃならんしな!!」
白い新たな排気煙を空に刻んで、ミサイルが加速していく。肉眼では追い切れないが、レーダー上、目標機目掛けてこちらから発射された光点が接近していく。空に3つ、火の玉が膨れ上がり、2つの赤い光点が消滅する。残り2つは健在も、そのうち1つは黒煙を翼から吹き出しながら離脱するべく反転していく。お返しとばかり放たれる攻撃を回避し、高度を稼ぐべくズーム上昇。ある程度上昇したところで水平に戻しつつ反転。撤退する友軍機を狙う別の一隊へと高速で接近。逆にその後姿に、ロックオンをお見舞いする。溜まらず編隊を解いた敵部隊。そのうち、こちらの目の前に背中を晒してしまった1機の左主翼を狙い、機関砲弾の雨を降らす。大穴をいくつも穿たれたうえ、どうやらぶら下げてきたミサイルが誘爆を起こしたらしい。黒煙と炎で半身を覆った敵機は、こちらがその真下を通過するや否や火の玉と化した。爆発の閃光と炎とが一瞬こちらの機体を包み込む。その隙に、友軍のF/A-18Cの一隊が攻撃圏内からの離脱に成功する。包囲網に加わっていたのが、敵第一陣の旧型機を中心とした部隊であったことも幸いしたらしい。残る攻撃手段の全てを注ぎ込んで網を噛み破った友軍機たちが、西方向へと加速していく。シャムロックとドランケンは?レーダーを見れば、こちらと同様に敵の正面に立ちはだかってその針路を妨害しているところだった。
「エッグ……エッグヘッドよりドランケン、敵エース隊機は?」
『ドランケンより、若いの。仕留めてやったワイ。存外、大した事無いのぅ』
余裕風を吹かせた台詞ではあったが、かなり息が切れている。タリズマンよりも歳が上、しかも「まだ飛んでいるのか」と言われる御仁が、40歳前とは考え辛い。年齢的には相当無茶であるし、相当負担もかかっているに違いない。だが、少し前に叩き落したF-22同様に、エース隊機の損耗は敵将兵に動揺を与えるには良い手段であった。
『シュトリゴンが2機も落とされただと……!?』
『何機か、やたらと動きのいいのがいる。気をつけろ!!』
 『――エメリアの航空部隊は張子の虎ではないという事だ。シュトリゴン・リーダーより、各機。私があのF-15Eをやる。誰も手出しはするなよ』
『――エメリアの航空部隊は張子の虎ではないという事だ。シュトリゴン・リーダーより、各機。私があのF-15Eをやる。誰も手出しはするなよ』
「フン、真打登場ってところか」
「ミサイル、機関砲弾、共に弾切れ間近です。無茶は出来ませんよ」
「じゃ、サックリ仕留めて俺たちも撤退だ。シャムロック、ドランケン、お前たちは先に行け!!」
『しかし……!』
「F-16Cの速度じゃ、連中に追い付かれる。何、後からちゃんと行く。行け!!」
『その余裕がアダにならなければ良いがな』
敵航空部隊の中から、例の赤黒いカラーリングのSu-33が1機、突出して俺たちの真正面に姿を現した。こちらの姿を確認すると、ヘッド・トゥ・ヘッドで急速接近。速度を減じることなく、その機体が見る見る間に膨れ上がる。パイロットの姿が一瞬確認出来た次の瞬間、敵機はこちらの腹の下、至近距離で後方へと抜けていく。初回のタイミングで攻撃を仕掛けなかったのは、一対一の戦いを始めるうえでの敵パイロットの感傷なのだろうか?それとも、自らが葬り去る相手への憐みなのか――。こちらは機体を逆さまにして降下反転へ。一足早く下方に抜けた敵の姿を探すと、こちらからそう遠くない地点で、敵機は既に上空へと舞い上がっていた。タイミングを図ってスナップアップ、一気に上昇へと転じたのか?ちっ、と舌打ちしたタリズマンは機体を強引に捻らせて水平に戻し、そして機首を跳ね上げた。ミシッ、と肋骨が鳴ったような気がするほどのGが全身へと圧し掛かる。スプリットSでの反転を行っていたなら、頭と後方とを取られていたかもしれない。それを嫌っての強引な姿勢変更と急上昇。垂直に空を駆け上がっていく愛機。コクピットにレーダー照射を告げる警告音が鳴り響く。一足遅れて上昇する俺たちよりも早く攻撃ポジションを確保した敵機は、姿勢を水平に戻してこちらに狙いを定めていた。だがこの上昇スピードならレーダーロックを確定させるのは難しい。構わず高度を上げていくこちらに対し、敵機はクロスアタックを仕掛けてきた。機関砲弾の雨と曳光弾の輝きが頭上から降り注いでくる。ここに至って、タリズマンが動いた。機体をロールさせて軌道をずらし、横方向へと倒れこむ。至近距離を敵の攻撃が通り過ぎたが、シュガッ、という鋭い音と軽い振動がコクピットの中に響いた。コクピット脇を通り過ぎた一弾が、機体を掠めた音だった。
何とか振り返って後方を確認。胴体部に命中弾無し。こちらの後方に抜けた赤い機影を捕捉する。この程度で諦めるような相手ではない。早くも機体をバンクさせて、右方向に旋回している。すると、敵の位置がぐいと変わった。敵機を狙って、こちらは左方向へと急旋回。自分よりも大柄なタリズマンの場合、こういった激しい機動時に受ける負荷も相当なものになるはずであるが、そんなことお構いなしと機体を振り回す。互いに反対方向から旋回。敵からも、旋回するこちらの姿が見えているだろう。真正面からの撃ち合いか、それとも後背の奪い合いか。速度と旋回角を微妙に調整しあいながら接近する2機。今度はタリズマンから仕掛ける。ぐっ、と機首を素早く引き上げて、旋回状態の敵の姿を捕捉、加速開始。流線型の機影を捉えたのも束の間、その機首が勢い良く跳ね上がってこちらを向く。互いにガンアタック。命中せず。互いの軌道が交錯する。ぐるり、と視界が回転して反対方向へと急旋回。敵機も同様に急旋回。旋回性能で分が悪いこちらが前方に押し出される。スロットルを調整しながら、速度を落とさずにさらに旋回を続ける。一つ間違えればスピン状態に入ってもおかしくないギリギリのライン上。右、左、右、と旋回の都度体内の血液が振り回される。首を動かすことすら出来ず、俺はレーダーモニターを必死になって睨み付けていた。敵は相変わらずこちらの後背に。だが、向こうもこちらを捕捉しているわけではないようだ。こちらに合わせて向こうもダンスを踊っているかのよう。右方向へやや高度を下げながらの旋回から、身を翻して左方向へ。そのまま行くと思いきや、ガクン、と姿勢が入れ替わる。右方向へと再び急旋回。さすがに読み切れず、敵機が前へと押し出される。だが敵も並ではない。鋭く機体を旋回させると、機首を勢い良く下へと向けてダイブ。低空へと逃れていく。
「レーダーでしっかりと追尾しとけ、エッグヘッド!」
「了解!」
アフターバーナーに点火。甲高い咆哮と、ドン、と弾き飛ばされるような加速。新市街の上空を離れ、崩落した王様橋方面へと移動する。これで見逃してくれれば良いのだが、敵さん全くそんなつもりはないらしい。仕切り直し、とばかりに悠然と反転すると、海上へ一旦抜けてこちらの正面へと回り込んでくる。
『……これほどのパイロットがエメリアにいたとはな……』
『シュトリゴン・リーダーの動き……一切無駄が無い。だけど、あのF-15E、どうして隊長に付いていけるんだ……!?』
実際に後席に座っている身としても、あの「トンデモ」機動のフランカー相手に良く渡り合っていると思う。だが、何となくその理由が分からなくも無い。タリズマンは、Su-33が得意とする近接格闘戦では必ずしも勝負をしていない。鋭い切り返しに加えて、クルビットやプガチョフ・コブラといったあの機体で無いと困難な機動を持つ相手に、狭い戦闘空域内でぐるぐる旋回しているだけでは勝ち目が無い。さっきのシザース合戦にしても、極力速度を殺さずに旋回を繰り返していたのは、低速度域での戦闘になったら全く勝ち目が無いからだ。逆に高速域では、こちらにアドバンテージがある。ほぼ間違いなく、最高速度だけならF-15Eの方が上だ。敵が逃げの一手を打ったとしても、こちらはそのケツに喰らい付くことが出来るに違いない。それが分かっているからこそ、敵の隊長機はこちらに後背を取らせまいとしている。巧みな機動でこちらを翻弄してオーバーシュートさせて、無防備な背中にミサイルか機関砲弾を撃ち込む算段をしているに違いない。こうなってくると、如何に早く、自分のフィールドに相手を引きずりこむかが肝心だ。恐らく、敵隊長機はヘッド・トゥ・ヘッドでの戦闘に自信があるのだろう。或いは、そこから近接格闘戦へと持ち込むつもりなのか?答えの代わりとでも言うように、コクピットにミサイルアラートが鳴り響く。
「真正面、敵ミサイル!!」
「良く見えてるぜ。こっちもお返しだ!」
タリズマン、ミサイル発射。ただしこちらの攻撃はロックオンはしていない。接近する敵機の真正面を狙って放っただけ。前世紀のロケット弾攻撃と何も変わらない。だが命中すれば威力はその当時の比ではない。翼をキン、と立てたSu-33は、そのままローリング状態へ。こちらはこちらで、白煙を吹き出しながら迫り来るミサイルから逃れるべく、旋回……しない。斜め上方向へと機首を上げて、そのままバレルロール態勢。姿勢を変えたこちらに合わせるように、ミサイルの軌道が曲がってくる。その狙いはかなり正確だ。機動性向上型のミサイルを向こうは積んで来ているらしい。
「駄目ですタリズマン!ミサイル、こちらに合わせて近付いて来ます!」
「そこで旋回してみろ。あの赤い奴の機関砲弾のシャワー浴びてお陀仏だ。赤外線誘導型じゃないよな!?」
「確率の問題ですが、多分違います!」
「お前の勘に賭けてやる。行くぞ!」
緊急回避時に使用するチャフ散布。続けて、バレルロールで反動の付いている機体をさらに大きく振ってもう一回転。目前に発生したアルミ片の雲によって目標選定に混乱したミサイルの動きが鈍る。それだけの時間が稼げれば十分だった。チャフ片に突っ込んだミサイルが炸裂した時には、ギリギリ安全圏内へと退避。膨れ上がる火球をそれぞれ逆方向に抜けて、F-15EとSu-33は次なる衝突に備えて同一方向へと旋回を開始する。だが、その周りは、いよいよ敵の機影ばかりとなりつつあったが、友軍機の撤退はどうやら順調に進んでいる。命令には渋々従ったものの、こちら同様に撤退する友軍機を支援するために「アバランチ」と「ウィンドホバー」の二隊が敵部隊の進撃を阻んでいたのだ。さらに言うなれば、彼らの奮闘によって、未だ西方向への脱出口はかろうじて開かれたままであった。今なら、あのフランカーを振り切って撤退することは困難であっても不可能ではないだろう。後は、機長であるタリズマンがそれを潔しとするかどうかだ。ここで彼が敵エースとの戦いにばかり眼が行ってしまっているのなら、その襟首を引っ掴んでも本来の命令に回帰させなければならないのが、後席――兵装システム士官席に座る自分の役割である。それに、弾薬はいよいよ弾切れ寸前。これ以上、戦いを長引かせることも、これ以上他の敵を相手にするのも得策ではなかった。
「――タリズマン。友軍部隊が脱出口を確保してくれています。脱出の好機です!」
「やっぱりそう思うか?潮時、という奴か」
タリズマンが極めて冷静な状態にあることに、俺は安堵した。もっとも、次の台詞が聞こえてくるまでの、ほんの僅かな時間だけだったが。どうやらこの上官、俺が考えていた以上に、桁外れだったらしい。この状況下で、きっとマスクの下では笑みを浮かべているに違いないのだから。
「じゃ、敵の隊長機、そろそろ噛み砕くとするか――!」
「天使舞う空、駆け抜ける鉄騎」ノベルトップページへ戻る
トップページへ戻る
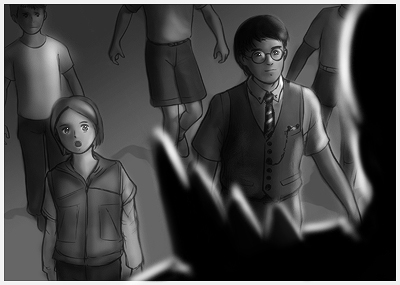 うっ、と詰まってしまったバレンティンの姿に、マティルダは手を顔に当てて首を振った。緊急事態ならそれなりのやり方ってものがあるはずじゃないか。見たところ、全然焦っているように見えないバレンティンは、どうやらご丁寧にケースを一つ一つ運び込もうとしているらしい。「普段は絶対にやっちゃ駄目だぞ」とおっちゃんが教えてくれた方法を思い出したマティルダは、自分の肩掛け鞄の中身を漁った。丸い形の目標物を探り当てた彼女は、素早くテープを「×」印にしてガラスケースに貼り付けると、次いで金属製の水筒を少し強めに叩き付けた。
うっ、と詰まってしまったバレンティンの姿に、マティルダは手を顔に当てて首を振った。緊急事態ならそれなりのやり方ってものがあるはずじゃないか。見たところ、全然焦っているように見えないバレンティンは、どうやらご丁寧にケースを一つ一つ運び込もうとしているらしい。「普段は絶対にやっちゃ駄目だぞ」とおっちゃんが教えてくれた方法を思い出したマティルダは、自分の肩掛け鞄の中身を漁った。丸い形の目標物を探り当てた彼女は、素早くテープを「×」印にしてガラスケースに貼り付けると、次いで金属製の水筒を少し強めに叩き付けた。 『――エメリアの航空部隊は張子の虎ではないという事だ。シュトリゴン・リーダーより、各機。私があのF-15Eをやる。誰も手出しはするなよ』
『――エメリアの航空部隊は張子の虎ではないという事だ。シュトリゴン・リーダーより、各機。私があのF-15Eをやる。誰も手出しはするなよ』