リ・スタート!②
普通に歩くことが出来る、という状態がどれほど恵まれたものであったのか、今なら嫌というほどヴォイチェクは理解出来る気分であった。厳しい訓練に耐え続けてきた身体であればこそ、この程度の期間で回復出来たことは事実なのだが、その代償として彼は「回復出来ない」傷を負った。不時着時のショックで派手な傷を負った足は、軍医たちの腕を以ってしても完治不能と判断されたのである。それは即ち、戦闘機パイロットとして復帰する道が完全に閉ざされることと同義であった。戦闘機乗りとして生きることを心に決めてただひたすら走ってきた身にとって、二度と飛べないという事実は衝撃以外の何物でもなかったが、かといって自暴自棄になるほどヴォイチェクも若くはなかった。ドブロニク上級大将の推薦もあり、退院後のポストも用意された。「空軍諜報部付特命調査官」という新たな肩書にヴォイチェクは首を傾げざるを得なかったが、自ら見舞いに訪れたドブロニクは「早い話がリハビリだ。当面の間、無理はさせたくない。ただ、貴官の人を見る目を充分に役立てて欲しい」と言い、当面の任務はエメリア軍捕虜の尋問官になるだろう、と告げた。長い付き合いの上官の配慮はヴォイチェクとしてもありがたいものであったが、彼の新たな任務は決して心の翼を駆り立てるようなものではなく、傷が治れば治るほど、気分を重くする重石だった。そんなヴォイチェクではあったけれど、彼をこんな立場に陥れた張本人たるエメリアのエースパイロットへの恨みは微塵もなかった。それどころか、グレースメリア上空での激しい戦いを思い出すたび、しょげていた心の翼がしゃんと羽を伸ばすような気分になるのだ。かなうものなら、もう一度奴と合間見えたいものだ、と。
リハビリを一通り完了し、杖を突きながらではあるものの歩くことが出来るようになったヴォイチェクは数日間の休暇を取った。最前線で戦い続けて彼にとって、オフ以外で休暇を取得したのは軍人となって以来初めてのことだったろう。「最前線から外れた過去のエース」の申請は、すんなりと認可された。最前線に立てない以上は、特に拒む理由もない、ということなのだろうと納得する。彼は、小旅行に出ることを決めていた。新たな任地に出発する前に、気分転換をしておきたかったのも理由の一つ。この機会に、訪れておきたい場所があったことが一つであった。戦時下、優先的に運行されている軍用列車に乗り込んだヴォイチェクは、エメリアとの国境近くに位置する片田舎への旅路に出た。列車の旅は新鮮だった。飛行機ならものの一時間もあれば到着出来る距離を、座席から外の景色を眺めながら何時間もかけて移動するのだから。買ったまま読むことが無かった過去のエースパイロットたちの伝記に時折目を通しながら、祖国の風景を眺める。ユリシーズ落着時に破壊され、そのまま放置された町並みがいくつも視界を通り過ぎて行く。今となっては利用客が一人もいなくなり、通過されるだけの駅もあった。だが、そんな風景もエメリア国境へと近付くにつれて変わっていく。奇跡的に被害を受けることの無かったエメリア本土同様に、エストバキアの西方はユリシーズによる損害もほとんどなく、今でも昔からの風景を保っているのだ。もっとも、かつてリエース派によって統治されていた一帯は、その後の内戦による傷跡が穿たれてはいたが。それでも、ユリシーズの直撃を受けた地域よりは遥かにマシだ。まだ当分の間は生活することも出来ないほどに汚染された区画。跡形も無く、街の存在自体が消滅した区画。空から見た凄惨な光景は、ヴォイチェクの両眼に焼き付いたまま、決して拭うことが出来なかった。
片田舎に相応しいこじんまりとした駅で列車を降りた彼は、もしかしたら内戦以前から変わらないのかもしれない、のんびりとした空間へと足を踏み入れた。長い間、大空を音速で駆け抜けていた身には、何もかもが新鮮であった。古びたセダンのタクシーの後席へと乗り込んで行き先の住所を告げると、老齢の運転手は分厚い眼鏡をかけてロードマップを開いた。年季の入った地図には無数の付箋が貼り付けられていて、手書きで新たな道が書き足された形跡もある。とはいえ、ルートの確認はそう長いものではなかった。動き出した車が目的地に至るまでの2時間ほどの道のりは、ヴォイチェクにとって不快ではなかった。暖かな日差しに誘われて、何年ぶりかの居眠りをしたことに驚く。体力が落ちたことも理由の一つかもしれない。ニコニコと笑顔を絶やさない運転手に料金を多めに払い、帰りも使いたいので待っていてほしい、と告げると、運転手はすぐ側のドライブ・インで待っていると快諾した。走り去るタクシーを見送ってから、ヴォイチェクは片足を引きずりながら歩き出した。辺りは本当にのどかな田園風景。柵の中には放し飼いにされた羊たちが午睡を貪っている。場違いな訪問者の姿に気が付いた何匹かが訝しげに首を持ち上げるが、やがて興味を失ったか、そっぽを向いてしまう。爽快な空気を楽しみながら進む先に、丸太造りのログハウスがあった。部屋の一つから張り出したログハウスには、車椅子に乗った男の姿が一人。この田園風景を楽しみながらパイプをふかす様が堂に入っている。少しして、男の視線がこちらへと向けられる。いぶかしげな表情が、やがて苦笑へと変わっていくのを、ヴォイチェクの両眼は捉えていた。飛べない身体になったからといって、目まで衰えたわけではない。
「――久しいな。どうした?飛べなくなった戦闘機乗りの生き方でも教わりに来たのか?」
「元気そうだな、プリスタフキン。……ま、そんなところだ。ご覧の通り、飛べないパイロットの仲間入りだ」
「エメリアにも大したパイロットがいる。俺でも出来なかった、シュトリゴンの長の撃墜を達成したんだからな」
「「青」の長を撃墜した時点で、私の幸運は使い果たしたらしい。見事だったよ。言い訳のしようもないとはこの事さ」
「そんなところに立ってないで入ってこいよ。贅沢なものは無いが、茶と酒なら豊富にある」
バルコニーにおかれた木製のテーブルの上には、煙草の一式と、マグカップ、ティーポットが並べられていた。香りは紅茶の類のものではない。もう遠い昔、基地の食堂の一角に陣取って、食後の一杯に使う茶葉を楽しそうに選んでいた男の姿をヴォイチェクは思い出した。どうやらその趣味は今でも変わっていないらしい。かつて翼を並べて空を舞っていた相棒の翼を奪ったのは、ヴォイチェク自身だった。あの戦いも熾烈なものだった。思い出すだけで、身体に刻まれた戦いの記憶が蘇ってくる。空で幾度も交錯する二機の航跡。一体何度すれ違ったのかすら覚えていない戦いの最後、ヴォイチェクが引き絞ったトリガーは、機関砲弾の矢となってプリスタフキンの青い機体を撃ち抜いていった。黒煙を吹き出して高度を下げていく相棒の愛機。だが、そのコクピットからプリスタフキンの姿が射出される事は無かった。後から知ったことだが、リエース派の指導者たちは優秀なパイロットたちが敵方に引き抜かれることを何よりも恐れ、射出座席をわざと故障させていたのだ。それを知ってか知らずか、プリスタフキンは不時着には成功していた。だが、その時の衝撃によって、彼は下半身に重傷を負ってしまった。そして、車椅子の上の生活が始まったのだった。
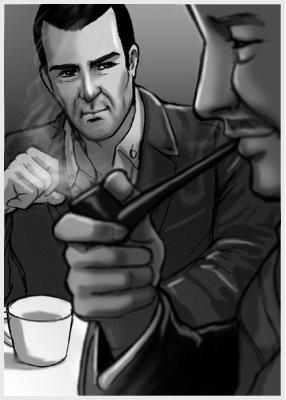 「随分苦戦しているそうじゃないか。もう政治がらみのゴタゴタは一切ご免だが、ラジオをかけていると嫌でも聞こえてくるもんでな。戦い方ならエメリア如きに劣るはずもない……っていう広報官のハッタリは見事的外れなわけだ」
「随分苦戦しているそうじゃないか。もう政治がらみのゴタゴタは一切ご免だが、ラジオをかけていると嫌でも聞こえてくるもんでな。戦い方ならエメリア如きに劣るはずもない……っていう広報官のハッタリは見事的外れなわけだ」
「前線を知らない奴らはいつでもそうさ。死に物狂いになった敵がどれ程手強いか知らないから、物事を簡単に口にする。ニンバスとアイガイオンが無かったなら、今頃苦杯を舐めているのは我々の方さ」
「――で、そんな状況の中、操縦桿を握る以外には能が無いお前は、何を為すつもりだ?」
マグカップを持ち上げたヴォイチェクの手が止まる。やれやれ、といった風に、プリスタフキンの口元に苦笑が浮かんだ。お見通しだったか、とヴォイチェクの顔にも苦笑が浮かぶ。
「後方の実務もろくに知らんパイロット崩れに出来る即席の仕事といったら、せいぜい捕虜の尋問官くらいだろ。鋼鉄の翼を持っていた人間にとっては、たとえ強固な忠誠心と意志を持っていたとしても、落差に苦しむだろうさ。俺みたいに面倒事を捨てちまえば楽だったんだが……頑固だからな、お前は」
「……エストバキア軍人としての誓いを立てた時から、私の忠誠と命はエストバキアという国家に差し出したと今でも私は信じている。飛べなくなったのは、自らの過ち。そして実力不足に油断だ。そんな私でも為すべきことが残っているなら、祖国のために出来ることがあるなら――空を飛べなくとも私の戦いは続くのだと思う」
「ふう、本当に変わって無いな、お前は。――なら聞くが、俺たちが誓いを立てた祖国は今どこにある?お前の「為すべきこと」とは一体何だ?」
「それは……」
「即答できないだろ。それが、答えだ。……だが、その身体になったからこそ、敵国へと行く意味があると俺は思っている」
「どういうことだ?」
「そう結論を急ぐなよ。こういう時は……カモミールだな。ちょっと待っていろ」
当惑するヴォイチェクを余所に、プリスタフキンは新たなティーポットを手繰り寄せ、茶葉の詰まったポットにスプーンを差し入れる。ヴォイチェクがここを訪れた時点で、プリスタフキンはある程度理由を察知していたのかもしれない。旧友から突き付けられた問いは、まさに今のヴォイチェク自身が結論を出せずにいる難問だった。祖国のため――それはヴォイチェクが内戦を生き抜くうえで硬く心に刻み付けた誓いであった。だがそれは、ひょっとしたら思考を停止させる「逃げ」だったのではなかろうか?戦闘機を操れなくなった今、何を為すというのか。捕虜の尋問が祖国再興に何の意味を為すのか。――これまでの長い戦いの意義は。親友までも撃ち落としてまで成し遂げた祖国の再統一の意義は――。沈黙したヴォイチェクの前に新たなマグカップが差し出されるまで、ヴォイチェクは彼自身の思考の中に意識を没頭させていた。その姿を眺めながら、先に口を開いたのはプリスタフキンの方だった。
「俺たちは常に空から世界と戦いを見てきた。陸軍の連中みたいに、泥と煤にまみれて、中身をぶちまけた敵や味方の死骸を踏み越えてなんてことなしに、な。まして、占領地の人間との付き合いなんざ、基地の近くの飲み屋程度。だから、陸軍や海軍の兵士からはお気楽なトンボ稼業なんて言われるわけだ」
「だが、我々の役目はそうならざるを得ないものだろう?」
「その通り。だから、その身体になって初めて得るものが多いのさ。大体お前、占領地の民草がどんなことを考えて日々を送っているか、考えたこともないだろう?まさかとは思うが、エメリアの市民がエストバキアによる統治を歓迎しているなんて信じているんじゃあるまいな?……返す言葉も無い、って感じだな。そんなお前だから、自分の足で歩いて、自分の目と耳で感じた方がいいのさ。どうせ尋問官の仕事なんざ、数時間で終わっちまう。残りの十何時間か、違う国、違う土地、そいつを楽しんで来い。そうすりゃ、これからの生き方が見えてくる。おや……湯が切れたか。どうだ、久しぶりに「アルコール消毒」でもするか?待ってろよ」
「おい、私は今酒は……」
「いいからいいから。本当に相変わらず頭硬いよなぁ、お前」
そこで座っていろよ、と言い残して、プリスタフキンの姿が家の中へと消える。頭が硬いとは心外だ、と呟きながら、ヴォイチェクは頬杖をついた。とはいえ、プリスタフキンの指摘したことは、認めたくはないが図星だった。それだけでも、ここに来た意義があった。この穏やかな風景と、地上の生き方の先任たる旧友との再会。視線を空に向けると、何の鳥かは分からないけれど、綺麗なトライアングルを組んだ群れが頭上をフライパスしていく。ほんの少し前まで、あの空を同じように舞っていたヴォイチェクにとって、それは何よりも羨ましい姿だった。
「それでは、よろしくお願い致します。すみませんなぁ、ホントに」
ドアがゆっくりと閉ざされるまでの間、深く折った腰を戻すことも無く、カークランドは頭を下げ続けた。やがて家人が家の奥へと去ったことを確認してから、ようやく彼は姿勢を戻した。一方の手で腰を叩きながら、もう一方の手で古びた手帳を取り出して開く。ケセドの寒空の下、車の前で待つ秘書ですらコートを羽織っているというのに、カークランド自身はダークグレーのスーツのみの姿でひょこひょこ歩いてくる。車のドアを開けた秘書に手をあげて礼を言いながら、彼は後席へと腰を下ろした。その車も、グレースメリアで乗っていたVIP御用達の大型車ではなく、普通の国産のセダン車。予備知識が無ければ、まさか一国の首相が乗っているとは誰も気が付かないことだろう。この車で唯一改造されているところがあるとすれば、それは缶コーヒー好きの首相のために冷蔵庫ならぬ温蔵庫が後席に搭載されていることだった。自ら扉を開け、二つ缶を取りだしたカークランドは、カップホルダーに秘書の分も置き、ブルタップの口を開けた。
「ふはぁ……やっぱり寒い時には温かいのに限るな」
「首相、コートくらい羽織ってください。身体を壊します」
「いやいや、寒いのはみんなお互い様。まして私たちは無理なお願いをするために回っているんだから。居候の身が厚着なんかしちゃダメでしょう」
「とはいっても一国の首相なんですから、何もここまでされなくとも……」
カークランドと同じように缶コーヒーを傾けた秘書は、わずかに眉をひそめる。彼はどちらかと言えばブラック派であって、上司が愛飲しているような甘過ぎるものは嫌いな部類なのだ。ところが、カークランドは「この緊急時に我々が高いものを頂くのは筋違いというもの。私はこちらで充分なんですよ」と言って、ケセドに本拠を置く中規模メーカーの缶コーヒーを軍需用として大量に発注してしまったのである。もっとも、当初の想定コストの1/3で済んでしまったと説明されれば、部下たちには抗議する術もない。そんなわけで、ケセドに脱出してきたエメリア軍部隊は、缶コーヒーだけは満足に飲めるような状況にあった。ちなみに、カークランドが次に好むのはサイダーである。説明するまでも無く、同じメーカーからに大量の発注をしたことにより、エメリア全軍はサイダーにも苦労しない生活を送れるようになっている。
「君も良く知ってるでしょ。私は、オザーバ幹事長の準備が整うまでの「つなぎ」の政治家でしかなかったんです。つまり、私には他の皆さんにあるような基盤というものがほとんど無い。何しろ政策の決定も含めて私がやってきたわけではないですからねぇ。おまけに地元支部が「中央の決定がないと動けない」と言うんだから、自分で何とかするしかないじゃないですか。これが、私の「権限」というものですよ」
「その幹事長たちですが、エストバキアの統治を万全に進めるために、将軍たちに接近しているというじゃないですか。そんな人たちの決定を待つだなんて……地元支部をもう少し動かしてもいいのではないですか?」
「無理強いしたところで、後々離反する人が出てしまっては遅いんです。私がしなくてはならないことは、私の出した無茶な命令に従って、この地までやって来てくれた軍の精鋭たちが、100%の力を発揮出来る環境を整えること。そして、地道に協力を得ることなんです。エストバキアとの長い戦いを生き延びるために、ね」
白いものがめっきりと増えた頭を撫でながら、カークランドは缶をぐいとあおった。そして、扉を開けてもう一つ缶コーヒーを取りだす。よくあんな甘いものをこれだけ続けて飲めるものだ、と秘書は上司の味覚を疑いたくなった。古びた手帳を開いたカークランドは、これまた古びたペンを取り出して、住所録にメモを書き入れていく。几帳面に書き込まれたリストの人物と住所は、今や唯一のエメリア領土となったケセドの有力者や企業経営者たちのものだった。カークランドは政務の合間を縫って、こういった人物たちのもとへと直接赴くことを日課にしていた。主流の政治家ではなく、何事も無い時代なら彼は傍流の役目を果たして政治家生命を終えていたことだろう。それだけに、彼はこうして地元の人々や支持者たちと接点を持つ機会がこれまでも多かったし、魑魅魍魎の住まう議会の中よりは、人々と接する場面の方が好きだった。
「市長、市議会、及び地元の商工会の支持はほぼ取り付けた……か。財界というよりは地元の名士たちですが、よくぞこの国を見捨てずにいてくれました。おかげで、オザーバ幹事長たちに対抗するためのささやかな基盤が私にも出来ました。とはいえ、このまま待っているだけではジリ貧ですねぇ……。軍の集結状況はどうなってましたか?」
「集結可能だった空軍に関してはほぼ全軍。それから……傭兵部隊もケセドに着任しています。海軍はもともと残存戦力が少ないため、全艦が集結済みですが、戦力的には1個艦隊と呼べるかどうか……。陸軍は再編成にまだまだ時間を要します。シルワートタウン方面に機甲師団が残ってしまった点も想定外でして、こちらの予想の七割もいれば良い、というところです」
「それだけ集まってくれただけでも予想外ですよ。そんな彼らの士気を下げないためにも、そろそろ始めなければなりませんねぇ。祖国を取り戻すための反攻作戦を」
いつもと変わらぬ口調で語られた重大発言を、秘書は聞き逃すところだった。改めてその意味を反芻して、その顔にギョッとした表情が浮かぶ。運転席でハンドルを握る運転手ですら、バックミラーをちらりと見たくらいである。そんなことはお構いも無く、カークランドは缶コーヒーをのんびりと傾ける。そして今度はカレンダーを広げて、何やら考え込み始める。11月のカレンダーをしばらく睨み付けていた彼は、しばらくしてある一週を大きく丸で囲んでみせた。
 「では、この辺でいきますか。ウスティオからの支援組のお手並み拝見というところですか。それに、うちのエースたちの実力が噂の猛者たちに劣らないことの証にもなるでしょうしね」
「では、この辺でいきますか。ウスティオからの支援組のお手並み拝見というところですか。それに、うちのエースたちの実力が噂の猛者たちに劣らないことの証にもなるでしょうしね」
「か、カークランド首相、そんな戦闘開始日を決めてどうするんです!?まだこちらは部隊編成も完全ではないんですよ!?」
「今回、エストバキアは我々を侮ってかかってくるでしょう。その程度の相手ですら退けられないのであれば、その後に待っているエストバキア本隊との厳しい戦いに勝利出来るなどとは思えないんですよ。それに、部隊編成を待っていてくれるほど、エストバキアだって甘い相手じゃない。なら、エストバキアが侮ってくれている今この時が、我々にとっては数少ないチャンス――私はそう思ってます。エメリアに必要なのは、戦略的にはあまり重要でなくてもいい、とにかく目に見える形での「勝利」なんですから」
「では……例の件を動かしますか」
「うむ、そうなるね。フフフフフ……オザーバ幹事長やハバトーヤ議長の横っ面を張って、正気に戻して差し上げるとしましょう。まあ、もし本当にグレースメリアに戻ることが出来たなら、現実に平手打ちの一撃でもプレゼントして差し上げますがね。やれやれ、戦後のエメリア議会の再編は厄介なことになりそうですなぁ……時に、殿下の消息はどうなっているのかね?」
「それが……グレースメリア陥落後、お姿を見た者が誰もおらず、未だ以って消息不明です。調べようにも、グレースメリアがあの状況では……」
「とはいえ、エストバキアのお世話になっているという話も聞こえてこない。なら、まだ切り札はあるということですね」
グレースメリア陥落時、エメリア軍が救出できなかったVIPの最重要人物こそ、アウレリウス二世の末裔でもあるエメリア王族最年少のエスト・ファン・エメリア皇太子だった。陸軍特殊部隊による市内潜入作戦も、既に皇太子の姿はどこにもなく、空しく撤退せざるを得ず今日に至る。外遊中だったために難を逃れていた現国王夫妻にとって、たった一人の実子の消息が分からないという痛みは、カークランドにも痛いほど理解出来た。なぜなら、彼自身も、次男坊をエストバキアとの戦いで既に失っていたからだった。愛息戦死の報を聞いた時、カークランドは「そうか、御苦労」の一言だけで悲報を終わらせてしまった。泣くのは、全て終わってからで構わない。それまでは、この胸に痛みはしまっておかないとね――夜遅く、秘書とウィスキーを傾けていた時に、彼はぽろりと漏らしたものである。
「カークランド首相。一つだけ確認をさせてください。首相は……自らの道を進まれる決断をされた――「つなぎ」の役目を捨てて、本気でエメリアを取り戻すための戦いを始められた。そう私は理解していれば良いのですね」
「どうしましたか、急に改まって。決断も何も、私は初めからそのつもりですよ。幸か不幸か、それが出来る「首相」という立場にいるんですから。いやいや、こうなって来ると「つなぎ」のために首相に任命してくれたオザーバ幹事長やバックフィールド大臣たちに感謝しなければなりませんねぇ。ハハハハハハ」
なかなかどうして、エメリアにも人物はいたものだ――愉快そうに笑っているカークランドの姿を眺めながら、秘書は少し冷めてきた缶コーヒーを傾ける。もしかしたら、この時にこの首相を迎えたことは、エメリアにとって最良の選択となるかもしれない、と秘書は確信し始めていたのである。もっとも、「タヌキ親父」という評価こそが、今のところ彼の最も納得している確信ではあったが。
「天使舞う空、駆け抜ける鉄騎」ノベルトップページへ戻る
トップページへ戻る
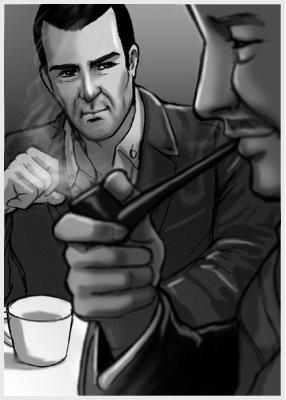 「随分苦戦しているそうじゃないか。もう政治がらみのゴタゴタは一切ご免だが、ラジオをかけていると嫌でも聞こえてくるもんでな。戦い方ならエメリア如きに劣るはずもない……っていう広報官のハッタリは見事的外れなわけだ」
「随分苦戦しているそうじゃないか。もう政治がらみのゴタゴタは一切ご免だが、ラジオをかけていると嫌でも聞こえてくるもんでな。戦い方ならエメリア如きに劣るはずもない……っていう広報官のハッタリは見事的外れなわけだ」 「では、この辺でいきますか。ウスティオからの支援組のお手並み拝見というところですか。それに、うちのエースたちの実力が噂の猛者たちに劣らないことの証にもなるでしょうしね」
「では、この辺でいきますか。ウスティオからの支援組のお手並み拝見というところですか。それに、うちのエースたちの実力が噂の猛者たちに劣らないことの証にもなるでしょうしね」