篭城部隊救出・前編
パターソン解放の一報の効果は非常に大きかった。レサス軍の電撃的侵攻によって分断され、絶望的な状況で抵抗を続けていたオーレリア軍部隊が合流したり、或いは連絡を寄越したりするようになったのだ。おかげで通信部は大忙しとなって、その応対に追われている。オーブリー基地の面子だけでは当然足らず、通信関連の技術を持っている人間は総動員となっていた。僕ら残党軍の構成も少しずつではあるけれども強化されつつあり、同時に作戦行動を決定する大人たちの数も増え、僕らが作戦会議に顔を出す機会も大幅に減少した。搭乗員が空での戦いに専念するようになるのは本当は当然の話だけれども、寄り合い所帯の井戸端会議のような雰囲気が味わえないのはちょっと寂しいような気もする。ひたすらトレーニングというわけにもいかないので、パターソンの航空基地に設置されていたレサス軍版の空戦シミュレーターにおける訓練を行うか、或いは機体の点検を行うか――という三択が僕らの主要な任務と変わりつつあった。しかし「点検」については難題が僕の場合はある。「マッドエンジニア」の2人組――フォルド二曹とデル・モナコ女史による点検と改造――絶対に違法改造に違いない――が始まってしまうと、在来機の知識しかない僕はお払い箱となってしまうのだ。パターソンの戦闘を経験したことによって、愛機XR-45Sは貴重な戦闘データを得たそうで、それに基づいて機体のチューンナップを図るのだという。これでも読んでなさいと渡された仕様書は最初の数ページしか読んでないが、驚いたことにこの機体、主要部分も含めてユニット単位での交換すら可能なのだ。……ということは、次に乗るときには全く別の機体になっているなんてことも有り得るのだろう。やはり僕はデル・モナコ女史にとっては最高のモルモットなのかもしれない。では訓練が出来るかと言えば、相棒のスコットは自分の機体の点検で手が離せず、ないない尽くしの僕に出来ることと言えば、夏の陽射しを浴びるパターソンの港の散歩ということになる。いやもちろんトレーニングしててもいいのだが。
夏が確実に近づいていることは明らかで、足元のコンクリートがじりじりと熱を反射している。それでも、海から吹いてくる風は心地よい。埠頭に沿ってしばらく歩いていた僕は、見慣れた同僚が座り込んでいる姿を発見した。この暑さ、僕以上に彼には堪えるのだろう。首からタオルをぶら下げて、さらにもう一枚のタオルを頭に巻きながら、ユジーンがチョコレートを頬張っている。こちらの足音に気が付いて振り返ると、彼は嬉しそうに手を振って笑った。
「――こんなところで油売ってて大丈夫?」
「さっき交代してもらったとこさ。いやー、戦闘中よりもしゃべったような気がするよ」
「……それってマズくない?」
「……やっぱりそうだよなぁ。でもほら、無駄口叩くと今度は拳骨が飛んでくるし、難しいよ」
今の僕はユジーンたちの仕事を全く軽く見ていない。むしろその重要さを、実戦を経験することで理解することが出来たように思う。モニターの上にしか表示されない戦闘状況を見極めて適確な指示を飛ばさなければならない彼らの仕事は地味で困難なものだ。僕らが存分に戦うことが出来るのは、彼らのバックアップがあるからこそだ。頼りない人間の代名詞のように言われていたユジーンだが、少なくとも戦闘中の彼は違っていた。ちょっと予想外だったけど。
「やっぱりジャスティンたちはたいしたもんだねぇ。モニターからしか分からないけど、レサス軍を翻弄して飛んでいるもんね。さすがはオーレリアの南十字星」
「勘弁してよ。毎回生き残ることを考えるだけで精一杯なんだから。レサス軍のパイロットだって、こんな若造が飛ばしているなんて知ったら呆れるんじゃないか」
「それは違うよ、ジャスティン。僕ら通信士はね、指示を飛ばすと同時に、味方の士気を鼓舞しなければならないときもあるんだ。こんなことを言ったら失礼かもしれないけれど、南十字星が健在であることをわざと知らせるのも、僕らの仕事だし戦いなんだ。だからジャスティンたちが戦っているときは、僕も一緒に戦っているつもりで指示を出しているんだよ」
ユジーンの穏やかな目がいつもよりもちょっとだけ細められて僕を射る。さすがにちょっと照れくさくなって水平線の向こうへと視線を僕はずらした。何事も無かったようにユジーンは再び次のチョコバーの袋を開けて噛り付く。あれで何袋目だろう?海の向こうを穏やかな目で眺めているユジーンの姿は何というか、周りの人間の気分をのんびりさせる魔力に満ちているようだ。妖怪怠け者魔人?全然戦には役に立たなそうだ。同じ話題を続けているとどんどん持ち上げられて居心地が悪くなりそうなので、僕は話題を少し転じてみた。
「……ところで、今日とか何でこんなに忙しくなってるんだろ?」
「あー、ジャスティンたちにはまだ伝わってないんだ。実はスタンド・キャニオンに追い詰められている陸上部隊から救援要請があってね。結構規模も大きいから無論僕らの戦力拡大のためには彼らを救出しなければならないと思うんだけど……」
「何か問題でも?」
しまった、という顔でユジーンが顔を掻く。どうやらまだ僕らには話せない「機密事項」であったらしい。
「――多分飛ぶのは君たちだろうから言ってしまうか。彼らは渓谷の中に逃げ込んでいるんだ。そして、その上空はグレイプニルの射程内なんだよ。つまり、SWBMによる衝撃波を回避出来る高度でしか飛べないんだ。データによれば、2400フィート以下。そこを戦闘機で飛ぶのは無謀だから、バーグマン隊中心の陸上部隊で行くかどうかを、マクレーン中尉たちが話し合っている」
「2400フィート……って、じゃあ谷の真っ只中を飛べということ?」
ユジーンは無言でうなずく。おいおい、正気の沙汰じゃないぞ、それ。ホバリングによる方向転換が出来る戦闘ヘリやVTOL機ならともかく今の僕らにそんな機体は無いから、必然的に僕はXR-45Sで飛ぶことになる。まいったな、相当操縦が大変になるじゃないか……。とはいえ、パターソンをがら空きにすることも出来ないし、十分な戦力は無い、かといって友軍を見殺しにも出来ない。なるほど、大人たちが難問を突きつけられているのは明らかだった。せめてもう一部隊くらいいれば違うのだが……僕は不意に、太平洋方面に現れた友軍艦隊の話を思い出した。ちょうど昨日の話だけれども、どうやら別任務か何かで公海上にいて難を逃れた小規模の機動艦隊が、レサス軍の攻撃部隊を殲滅したというニュースが飛び込んできたのだ。もし彼らとコンタクトが取れれば、留守のパターソンを任せられるのではないか?だが、ユジーンは残念そうに首を振った。
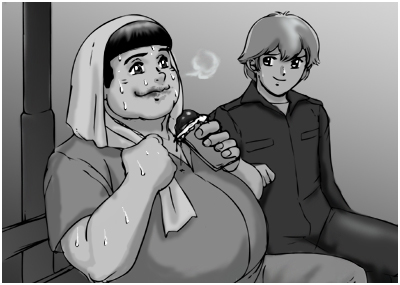 「実際のところ、通信をやり取りすることでその所在をレサス軍にキャッチされてしまうリスクが高いみたいで、こちらからはなかなか連絡を取りにくいみたいだよ。ジャスティンの言うとおり、彼らと連携出来れば心強いんだけどねぇ」
「実際のところ、通信をやり取りすることでその所在をレサス軍にキャッチされてしまうリスクが高いみたいで、こちらからはなかなか連絡を取りにくいみたいだよ。ジャスティンの言うとおり、彼らと連携出来れば心強いんだけどねぇ」
「そんな機動艦隊が残っていただけでも驚きだけど……どこの艦隊所属か分かったの?」
「それが分からないんだよねぇ。混乱の渦中だから詳しいデータが無いんだけど、敵の無線を聞いた限りじゃステルスとかが混じっていたとか……。少なくともうちの海軍にステルス機はいないからね。そもそもレサスの謀略じゃないかという話もあるくらいさ」
結局、広域レーダーも持たない弱小部隊の僕らではどうにもならない問題のようだった。かといって僕らに何かを決定する権限も無く、結局大人たちの決定事項に従うしか無い。大人たちが勝手に始めた戦争ではあるけれども、もうそれに加担しないわけにはいかない。僕自身、既に敵兵の命をこの手で葬り去った人間の一人になってしまったのだ。戦争を早く終わらせるため、XR-45Sに乗って、戦う。戦闘機をこの手で飛ばせるという喜びはあるけれども、その代償は敵兵の命を奪い取り、一つ間違えれば自分自身が空の塵と化す戦場への直行切符だ。悩んでも仕方ないとはいえ、心の整理が付いているわけではない。夢で見るんだ。敵兵の返り血を浴びて真っ赤になったパイロットスーツを着た自分の姿を――。
「お〜い、ジャスぅ!お呼びかかってるでぇぇっ!!」
現実から逃避しかけた意識が、スコットの大声で引き戻される。振り返ってみると、ファクト少尉と並んで――鼻の下を伸ばした――スコットが嬉しそうに両手を振っている。小走りにやってきたスコットはそのまま僕をやり過ごし、ユジーンの腕ポケットに入っていたチョコバーを強奪した。
「へへ、一コもらうで」
「仕方ないなぁ。貸し一つ追加だよ。まとめて払ってもらうからね」
穏やかに言うユジーンの目が少し怖い。遅れてやってきたファクト少尉の口元に苦笑が浮かんでいる。……やっぱり、オーブリー組の中では一番の美人だと僕も思う。どうしてそんな彼女が、よりにもよって昼行灯……マクレーン中尉と仲が良いのか分からない。やっぱり、恋愛とか愛情とか、そういうのはまだ僕には良く理解出来ない。スコットのように、最後はハートと甲斐性だ、と開き直れれば少しは人生明るくもなるんだろうけど。良くは分からないけれども、ファクト少尉にとってマクレーン中尉は気にかかる存在であるわけだ。そう考えたら何だか腹が立ってきた。スコットの言い分が少し分かるような気もする。
「出撃になりそうよ。……ちょっと今回も厄介な作戦みたいだけど」
「渓谷の中に突入とか?」
「あら、もう知ってたの?今度こそ、スコットは遺書を書いておいた方が良さそうね」
「え、何やそれ?渓谷の中?ヴァネッサさん、俺、聞いてへんで」
「言ってないもの。先に言ったら逃げ出すでしょう、スコットは」
……何てこったい。愕然として口を開いたまま突っ立っているスコットの手から、ユジーンがチョコバーを取り返している。僕は思わず天を仰いだ。これじゃ戦争やってる大人のいい玩具じゃないか。それもグレイプニルの射程内を、しかも渓谷の中を飛べだって!?僕は別の意味でレサス軍のことを恨めしく思った。全く、戦争のおかげでろくでもない経験だけは積めるみたいだ。作戦の困難さを思い浮かべて、改めて僕は慨嘆したのだった。
「3時方向、敵戦車部隊、間もなく顔出します」
「よく狙っとけよ。残りの弾も限りがあるんだ。引き付けて一網打尽にするんだ!」
「分かってますよ。よし……来た……!」
ズシン、と腹の底に響くような轟音が連続して響き、戦車砲の砲口が火を吹く。渓谷の合間を抜けて突撃してきたレサス軍戦車部隊の鼻先に砲弾が集中し、先頭部隊の何台かが瞬く間に爆炎に包まれる。直撃を被った車輌が真っ黒な炎を吹き出しながら燃え上がり、道を塞ぐ。こうなればこちらのもの。足止めされた敵の後続部隊に対して撃ち込まれた集中砲火が身動きの取れない敵戦闘車両に襲い掛かった。炸裂する爆炎が岩壁を駆け上り、炎に追われた兵員たちが必死に逃げ惑う。もうこんな光景をどれだけ見てきたのか、兵士たちは数えるのも面倒になっていた。襲撃してくるから迎撃する。自分たちが生き残るために。だがそれは、抵抗するための武器弾薬食料が充分にある場合の話だ。簡単なことだ。使えば無くなる。レサス軍が放っていった弾薬や食料を分捕ってはいたが、それで十分足りるはずも無く、サンタエルバ撤退時にしこたま抱え込んだ物資を少しずつ消費して今日まで戦ってきたのだ。部隊を率いるバグナード・ディビスは、戦闘指揮車の中から外の光景を眺めつつ、額の汗を拭った。この季節に戦闘車両の中にすし詰めというのは体力的にも精神的にも堪えるものだ。この数日間でショックだったのは、これまで1本も無かったはずの白髪が頭全体に広がってしまったことだ。たちまち10歳は老け込んだような自分の姿を見て、ディビスはレサスへの徹底抗戦を固く誓ったものである。これだけ不利な戦況に置かれながら、部下たちの士気が高いことが救いだった。もっともそれは、頭を真っ白にしながらも味方の損害を最低限にしようと指揮を続けるディビスの姿に、兵士たちの心が動かされた結果でもあったが。絶望的な戦況であったが、友軍の部隊が奮戦しているという噂が聞こえてきたのが数日前。そして連中がパターソンの奪還を成し遂げたニュースはどれだけディビスたちを勇気付けただろう。戦っているのは俺たちだけじゃない、と知るだけでも、兵士たちの士気は高まるものだからだ。
だからこそ、潜伏場所がばれるのを覚悟の上でディビスはパターソンへの救援要請を行ったのだ。サンタエルバに展開していた彼らの部隊は、数少ない機甲師団である。充分に戦争の準備を進めてきたレサス軍に比べ、オーレリアは元々火砲の数が足らないと言われてきていた。事実、足らないのだろう。だが、今のオーレリアには頼りになるエースたちがいるらしい。彼らと連携出来れば、きっと自分たちはもっと祖国解放のために活躍できるに違いない。そのためには、この深い谷から何としても脱出しなければならないのだ。
「やっぱり敵さん、本腰入れてきましたねぇ」
「少し手痛く叩きすぎたか」
「なあに、そんなことしてたらストレスでこっちがおかしくなっちまいますよ。とはいえ……対戦車ヘリに来られるとちょっと厄介ですね。相手が陸上部隊だけなら手の打ちようもありますが、空の相手じゃちと分が悪い」
ディビスは部下の言葉に頷き、現状の戦力を頭の中に思い浮かべる。サンタエルバは、突如として空に出現したグレイプニルによって呆気なく陥落してしまった。グリスウォールから来るであろう敵地上部隊に備えていた彼らは、帰るべき場所を唐突に奪われたも同然だった。グレイプニルと共に襲ってきた戦闘機部隊の追撃を何とか退けたものの、その戦闘で対空戦闘車両の多くを撃破されてしまったのである。だから、ここで戦闘ヘリに出てこられることは、ディビス隊にとって致命的なダメージになり得る。物資を捨ててパターソンへ急行するか、それともヘリの飛びにくいエリアへと移動して抗戦を続けるか――いずれにしても神経を磨り減らすような戦いを当面は強いられることになりそうで、ディビスは胃の辺りを押さえた。その姿を見て、部下たちが苦笑を浮かべる。これだけ追い詰められても自棄を起こさず、玉砕をとなえることもない指揮官だからこそ、彼らはここまで付いて来たのだ。事実それで全滅した部隊があるにもかかわらず、ディビス隊は奇跡的と言って良いほど戦力を温存しているのである。それは他でもない、指揮官殿の判断が決して間違ったものではないことを語っていた。
「……待ってくださいよ。畜生、敵の方が早いか。敵の本部方向から、戦闘車両多数接近中!第2分隊が敵戦闘ヘリ部隊の姿を確認しているそうです!!」
恐れていたことがついに現実となった。こちらの所在をはっきりと確認したレサス軍は、トドメを刺すために主力部隊を展開してきたのだ。今度は戦闘ヘリも繰り出してくるに違いない。――ここまでか。無言のまま俯きかけたディビスの背中を、部下の一人が思い切り引っ叩いた。
「なにぼさっとしてるんですか!俺たちゃ、アンタに命預けているんだ。ここまで来たんでしょう!?やるだけのこと、やってみましょうや」
「分散している隊を集めて、この際パターソン方面に強行突破を図りましょう。地の利はこちらにあります」
そう言いながら部下たちはさっさと他部隊への指示を飛ばしていく。彼らに降伏の二文字は見えないようだった。……指揮官失格だな、これじゃ。部下たちに激励されて指揮を執っているんじゃな……ディビスは照れ隠しに頬を掻きつつ、マイクを口元へと持っていった。パターソン方面の一隊に集中攻撃を浴びせて突破する指示を出そうとしていたちょうどその時、まるで傍受されるのも構わないかのように全車両に向けてその通信が聞こえてきた。
「ディビス隊、聞こえますか?こちら、オーレリア空軍のクラックスです。今、航空部隊がそちらに向かっています。彼らの到着まで、どうか持ちこたえてください!!」
スタンドキャニオンは、かつてこの地を流れていた川が大地を掘り下げて生み出した天然の要害だ。現在は流れる川自体が消滅してしまい、ここに残されたのは鋭く切り立った岸壁と水の気まぐれで残された高台だけになっている。オーレリアの風景100選にも選ばれる名所だけに、僕も写真でならこの地を良く見たことがあったけれど、実際に間近に見る日が来るとは考えもしなかった。それも、観光バスではなく、戦闘機に乗ってその渓谷を飛ぶなんて機会はそうは無い……というより有り得ない話だ。だが有り得ないことが現実となり、僕らグリフィス隊の向かう先は、その渓谷の中。レサス軍によって包囲されつつある友軍の脱出支援を僕らはしなければならないのだった。足元の風景が赤茶けた岩肌の大地へと姿を変えていき、そして進行方向の前方に、スタンドキャニオンの岸壁が姿を現すと、ノイズが混じるほどの音を立てながらスコットが盛大にため息を吐き出した。マスクの下で僕は苦笑を浮かべる。"他に作戦機いないのだから仕方ないだろう"の一言で作戦に組み込まれてしまったのだから、アイツが愚痴りたくなるのも分からないではない。でも、僕らが行かなければ友軍を見殺しにすることとなるのだ。結局、選択肢がないのはいつもの事だ。
「間もなくグレイプニルの射程内に入るぞ。各機、高度2400フィート以下まで下がるぞ」
先頭を行くマクレーン中尉のF-16Cが機首を下げる。僕らもそれに続いて少しだけ速度を落としつつ、高度を下げていった。地表が迫ると、自分たちの飛ぶ速度を改めて痛感させられて、何となく背筋の辺りに寒気が走る。
「クラックスより、ディビス隊、状況を知らせてください」
「こちらディビス隊。レサス軍の連中、本腰を入れて来ている。我々を包囲するように陸上部隊が接近中。こいつらの相手は何とかなるが、戦闘ヘリの相手は難しい。何とかやってみるが、支援を急いでくれ」
そう応える地上部隊の後ろからは、激しい砲撃の音、そして連続した機銃の音が轟いている。それを示すように、渓谷から黒煙が吹き上がり、時折火線が空へと伸びて光っている。既に戦闘は始まっているのだ。
「――グリフィス1、了解した。スコット、お前はファクト少尉に続け。ジャスティン、お前は先行しろ。俺がバックアップに付く」
「了解や。ヴァネッサさん、よろしゅう頼んます」
僕が前だって?僕は耳を疑ったが、きっと昼行灯――マクレーン中尉にも何か考えがあるのだろう。指示に従って少しだけスロットルを押し込み、マクレーン中尉の前に出る。渓谷は近い。ただ、先行した分僕は自由に動くことが出来る。実戦経験という点では僕らを凌駕する隊長なら、確実に付いて来てくれるだろう。過度に信頼しないほうが良さそうではあるが……。
「クラックスよりグリフィス隊へ。グレイプニルが臨戦態勢に入った模様です。――どうかくれぐれもSWBMに気を付けて下さい。渓谷の中なら回避できるはずです。――ご武運を」
「分かってる。ありがとう、クラックス。戻ったらチョコバーよろしく」
「ダースで用意しとくよ。スコットは駄目だけど」
「いらへんわ!虫歯になりとうないさかい」
編成を入れ替えて、僕が先頭に立って渓谷へと突入を開始する。開けていた台地はいよいよ狭まり、岩壁が僕らの両側から迫ってくる。だが怖がっている暇は無い。レーダーに敵影。渓谷内を移動中の友軍部隊が、砲撃を敵部隊に浴びせている、その横っ腹を狙って戦闘ヘリの群れが列を為している。まだ敵はこちらの接近に気が付いていない!素早く全兵装のセーフティを解除し、前方の敵を狙う。ホバリング状態のヘリを捕捉するのは簡単だ。ミサイルシーカーがその姿を確実に捉え、そして明滅する。ロックオン!電子音が鳴り響くのももどかしく、僕はトリガーを引いた。白煙を吹き出しながらミサイルが翼から放たれ、疾走していく。異常事態に気が付いたヘリが戦闘態勢を解いて散開しようとするが、もう遅い。戦闘機に比べればさらに貧弱な装甲を突き破り、炸裂したミサイルがヘリの胴体を容赦なく引き裂いた。地上部隊の歓声があがり、レサス軍が同様の叫びをあげる。
「な、何だ、冗談だろ!?戦闘機が渓谷の中に飛んできやがった!」
「見ろあのエンブレム!南十字星だ、オーレリアの南十字星がきやがった。くそ、撃墜しろ!!」
「――南十字星だけちゃうんやけど、やったるわ!!」
頭上はグレイプニルに押さえられ、地上からは対空攻撃が襲い掛かる。僕はHUDとレーダーとを睨み付けつつ、岩壁にキスしないで済むルートを確認しながら操縦桿を操った。前に比べて扱いやすく感じるのは、僕が慣れたのか、整備の賜物か――やがて切り立った岩壁が僕らの視界を覆う。向かう先、そして守るべき味方はこの奥にいる。目前に岩壁が迫る。90°ロール、捻りこむように愛機を旋回させて、僕は渓谷最深部へのルートへ足を踏み入れた。愛機XR-45Sが、翼の両端から白い雲を引く。素早く機体を水平に戻し、渓谷内のルートを確認しながら、熾烈な戦場の中へと、僕らは飛び込んでいった。
南十字星の記憶&偽りの空トップページへ戻る
トップページへ戻る
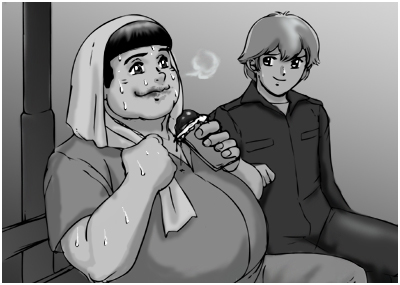 「実際のところ、通信をやり取りすることでその所在をレサス軍にキャッチされてしまうリスクが高いみたいで、こちらからはなかなか連絡を取りにくいみたいだよ。ジャスティンの言うとおり、彼らと連携出来れば心強いんだけどねぇ」
「実際のところ、通信をやり取りすることでその所在をレサス軍にキャッチされてしまうリスクが高いみたいで、こちらからはなかなか連絡を取りにくいみたいだよ。ジャスティンの言うとおり、彼らと連携出来れば心強いんだけどねぇ」