戦い終えて
案の定、というべきか、それとも止むを得ない、というべきか。首都解放を成し遂げた私たちは、残念ながら街へと繰り出した市民たちと共に喜びを分かち合う暇を与えられなかった。レサス軍部隊の全面撤退は現実のものとなり、反攻の気配すら見せずに国境線方面へとレサス軍残存部隊が去っていったことは明らかではあったが、サンサルバドル隊のように再び奇襲を仕掛けてくる敵勢力が無いとは言えない状況下、飛行可能な作戦機には漏れなくグリスウォール周辺領域の哨戒任務が割り当てられたのである。その背景には、ガイアスタワーを脱出後一向に行方の知れないディエゴ・ギャスパー・ナバロの追跡という目的もあった。戦闘中この空域を通過したヘリコプターが確認できない以上、彼は陸路を使って逃れたと見るべきだった。だが彼はオーレリアの首脳たちが用意していた脱出路を利用してまんまと逃亡に成功していたのである。既にこの街の中にはいるはずもないに違いない。そんなわけで、わずかな休息の後、私はジャスティンたちと共に再びグリスウォールの空へと上がった。対空砲火で狙われる心配も無く、ゆっくりと見下ろすグリスウォール市街の夜景はとても美しかったけれど、そのきらめきを素直に楽しむ気分にはなれなかった。勝利の喜びと、その先に確定している別れとが、私の心を複雑なものにしていたからだ。かといって、スコットもいる状況でジャスティンと会話をかわすわけにもいかず、ようやく任務を終えた頃には、もう夜が明けていた。襲ってきた眠気を振り払うことも出来ず、目をこすっている間にようやく少しだけジャスティンと言葉を交わしただけで、私は割り当てられた部屋へと入るとシャワーも浴びずに布団にくるまったのだった。
私たちに割り当てられたのはグリスウォール国際空港に隣接するシティホテルの部屋であり、戦時中という状況下ではある意味破格の待遇とも言えるべきものだった。なにしろ、陸軍部隊の大半がまだ野戦キャンプ暮らしを強いられている中で、個室、それも冷暖房が完備され、食事の面でも保証されているのだから。近日中にグリスウォール郊外にある空軍基地への移動は決まっていたから、それまでの間のご褒美、ということなのかもしれない。部屋の空調はホテル側で管理されていたけれども、昨晩の戦闘の残滓を引きずったままの身体がシャワーを欲して、私は眠りの園から離れて目を覚ました。何ともまあ、我ながら呆れる状態で寝ていたものである。何しろパイロットスーツやシャツがは床の上に放り投げられたまま。髪もボサボサになっている。おまけに、やっぱり汗臭い。よくよく考えてみると、部屋に戻ってきてからどうやって寝たのかはっきりと覚えてもいなかった。そんな状況でカーテンだけはちゃんと閉めていたのはせめてもの救いだったろう。何度か首を振って立ち上がった私は、クローゼットの中に収められていたタオルを取り出して身体を軽く拭い、それからシャワールームへと入った。暖かい湯を頭から浴びていると、ぼーっとしていた意識が次第にはっきりとしてきて、体が活性化してくるのが良く分かる。そして、今日のシフトが非番であることを思い出す。さてどうしよう……?グリスウォールの街は初めてではなかったけれども、別に観光気分で市街を回る気にもなれなかった。本当にやりたいことは勿論あるのだけれども、その一歩を踏み出せずに私の頭の中がぐるぐると回りだす。きっと断られるようなことはないんだろうけれど――そんなことを考えながらバスタオルで身体を拭っていると、シャワールームにも設置されている電話機のベルが鳴り、慌ててタオルを身体に巻きつけて受話器を取り上げた。
「はい、ノヴォトニー少尉です」
「――休んでいたところ、済まないんだが……」
「ミッドガルツ?どうしたの、珍しいわね」
期待をしていた相手の声ではなかったことに少し落胆しつつ、少しほっとする。
「土産を買いに行くのに付き合ってもらいたい。ついでだが、隊長からも伝言だ。"放っておくと部屋から一歩も出ずに過ごしそうだから外気に触れさせてやれ"――以上」
「……隊長って、意外と世話焼きよね」
「俺もそう思う。遅い昼食を取ったら連絡して欲しい」
遅い昼食?部屋に置かれたアナログ時計の針が既に午後3時近くになっていたことに私はようやく気が付いた。ここまで深い眠りに落ちたのも久しぶりであろう。それだけ身体も疲れていたということなのだが。しかし、ここは隊長の言うとおりかもしれない。この部屋の中でこもっていたとしても、何も結論は出ないし気だけが急いてくるだけのことだ。それよりは、ミッドガルツの許婚に送る土産物選びに付き合って気分転換をした方が余程ましというもの。ミッドガルツもその辺りに気を使って、私を誘ってくれたのだろう。彼の善意を無駄にするべきではなかった。
「分かった。じゃ、1時間後に連絡入れる」
「了解」
気分転換をしてから、もう一度良く考えよう。結論の先送りでしかないかもしれなかったけれど、それも必要だと私は判断したつもりだった。もっとも、私の勘働きは多分かなり鈍っていたのだろう。隊長をはじめとしたカイト隊の面々が、単純に善意の人たちではないことを見落としていたのだから。
ホテルのロビー傍にあるカフェで遅めのランチを食べ、ついでに頼んだパフェが意外に美味しくコーヒーを追加したのが悪かった。時計を見れば20分オーバー。慌ててロビーに駆けていくとジャケットを小脇に抱えたミッドガルツが苦笑しながら腕時計を突いて見せた。
「ごめん!空腹のままいるのは良くないと痛感したわ」
「先に出かけたのかと思っていた。ちょうどバスの時間だ、問題ない」
ホテルのロータリーに市街地行きのバスがちょうど待機しているところだった。駆け出して飛び乗り、座席の一つを確保するとエアロックタイプのドアがゆっくりと閉まり、ロータリーの石畳でゴツゴツと音を立てながら車が動き出す。まだ戦いの傷の癒えないグリスウォール市街には、戦闘中に墜落したヘリや戦闘機、破壊された戦闘車輌がそのまま放置されている。被害を被った建造物も少なくなかったが、早速再建に取り掛かっている人々の表情は明るい。それほど長期間ではなかったにせよ、軍政により様々な圧力を被っていた人々にとっては、ナバロという重石が取り除かれたことが何よりの喜びであるに違いない。だけど、そのナバロは単にグリスウォールから姿を消しただけに過ぎない。私たちがこの街の上空で戦闘を繰り広げていたちょうどその頃、戦闘に紛れてまんまと彼は脱出に成功していたのだ。陸上部隊を中心にした追撃隊が捜索を継続しているけれども、依然としてその消息は不明。それは即ち、この日が来ることを――レサスの敗北という事態を想定してあらかじめ彼が準備を整えていたことを証明している。内戦を生き抜いた男の真骨頂とでも言うべきだろうか?窓の外を流れていく景色を眺めながら、私はそんなことを考えていた。隣に座るミッドガルツはいつものように微笑を浮かべながら、どうやらホテルで集めてきたらしい市内の観光ガイドを開いてメモ帳に書き込んでいる。この戦いが終わったら、ミッドガルツも休暇を取って故郷の北の谷へと戻るのだろうか?通常とは異なる時間帯に睡眠を取ったのがまずかったのか、明らかに思考回路が失調気味だった。今日は難しいことは考えない方が良いわね――そう結論付けた私は窓にもたれかかりながら、ぼーっとすることに決めた。
バスに乗っていた時間はそれほど長いものではなかった。繁華街近くのバス停に停車した車から降りたミッドガルツに続いて、私も歩道へと降りる。街はいよいよ夕焼けに照らされる時間となり、赤い夏の太陽に街の景色が映える。夜景は夜景で綺麗だったけれども、この時間の街並みも美しい。グリスウォールは区画整理の観点でも成功した都市の一つであり、繁華街へと続く幹線道路の土手側を大規模なパーキングエリアとすることで街の中の混雑を緩和する工夫が取られていた。というよりも、繁華街中心部の道路は細く、しかも許可車輌しか進入出来ないようになっているのだ。だから、車で繁華街へと来た人間は否応無くここに駐車せざるを得ない。行政サービスの賜物と言っても良かったが、安価な値段でセキュリティもそれなりにしっかりとしていることも、利用率が高い理由の一つなのだろう。
「少し喉が渇いた。小休止していくか?」
「ええ、そうしましょ」
パーキングエリアに併設されている少し大きめのドリンクコーナーの一角に、私とミッドガルツは陣取った。「おごりだ」と手渡されたのは、何故かクリームソーダ風のメロンソーダ。もちろん無果汁。当の本人がストロベリーミルクで舌鼓を打っているのだから、おごられた私としては何も言えない。何とも懐かしい甘い味は、確かにクリームソーダだが、どうせならちゃんと上にアイスが乗っているクリームソーダを食べたいものだ。二人でコップをすする音だけが嫌に室内に響く。無口なミッドガルツだから、このまま何も話さなくても何とも思わないだろうけれど、私は少し時間を持て余し気味だった。――そういえば、ミッドガルツは超長距離恋愛中だったはず。近い将来、自分もそうなるかもしれない、というかなったらいいな、と思いついた私は、先達にコツを聞いてみたくなった。
「――ねぇミッドガルツ。ズバリ聞くけど、許婚との仲を保たせる工夫って、何だと思う?」
ミッドガルツはコップを傾けながら、視線だけをこちらに向けた。
「円卓の鬼神が選んだ許婚がいたとは初耳だ」
「いやそうじゃなくて、例えの話よ、例えの」
「手紙を書くことだ。まめに、きちんと」
「いやまぁ、それはそうなんだろうけど」
「後は土産だ……!別に高いものである必要は無い。その地方独特のものを選ぶことが大切だ」
「……ミッドガルツ、それあなたの場合だと思うな」
「悪いが、人の参考になるほど恋愛はしていない。フィーナよりはまし、みたいだがな」
ミッドガルツは基本的に無口なだけであって、人と話すのは決して嫌いではないし、冗談も飛ばす。そして、皮肉も勿論言う。彼にしてみれば、私の魂胆など見え見えなのかもしれない。その証拠に、彼の口元は愉快そうに笑っていた。口にはしていないが、ジャスティンとのこれからが心配なのだろう?――と、その顔は語っている。
「ま、本人と良く話をしてみることだ。折角お膳立てはしたわけだしな」
「へっ?」
人の悪い笑みを浮かべたミッドガルツが指差す方向を振り返ると、見覚えのある悪ガキ二人組――スコットとジャスティンが何事か喋りながらドリンクコーナーへと入ってくるところだった。
「おいおい、スコットと別行動なのか、僕は?」
「あんなぁ、俺はアイリーンとささやかーな戦勝記念パーティするんや。そっちはそっちでやってもらわんと」
「一人だったらホテルでも飯は食えるよ。帰る」
「ところがそうはいかんのや。ほら、ええから見てみい?」
私は思わず立ち上がってしまった。Tシャツにジーパン、キャップで長めの髪を隠しているジャスティンは、あの姿だと妙に少年らしく見えてくる。ラフな格好だけれど、良く似合っている。こんな姿もいいわね――と場違いなことを考えてしまい、私は首を振った。そうじゃなくて!どうしてここにスコットとジャスティンがやって来るの!?私を誘い出した張本人は、ジャケットを片手に、もう一方の手を軽く振ると、スコットに近寄っていく。どうやら向こうは向こうでスコットが暗躍していたらしい。ジャスティンはきっと私と同じような気分なのだろう。半ば呆然とした顔で、悪友とミッドガルツの二人を眺めている。
「ちゃんと連れて来たようだな。上出来だ、スコット」
「ほな、俺ら邪魔者は退散しますか?」
「ちょ、ちょっとミッドガルツ、どういうこと?」
「――俺は土産を買わなきゃならん。ここからなら、タクシーでもすぐに着く」
そう言ってニヤリと笑ったミッドガルツは、ジャスティンの肩を何度か叩いて小声で何事かをささやいている。謀ったわね、ミッドガルツ!!直接の企画はこの場にいない人々だろうけれど、私はまんまとシナリオ通りに動かされてしまったようだ。ミッドガルツは宣言通り許婚に送る土産物を探しに、スコットはどうやらアイリーンと約束があるらしく、当惑している私たちを置いてさっさと夜の街に消えてしまう。後に残されたのは、私とジャスティンのみ。いつまでもここにいるわけにはいかないし……。私は記憶に仕舞い込んだページから、以前この街に潜入した際にフェラーリン&ズボフの二大不良から教えられた「デートにオススメの店」の名前を必死になって引き出していた。特にズボフさんは父への嫌がらせもあるのか、必要以上に熱心に色々なジャンルの店を紹介してくれていた。私はその中から近場にある店の一つを抽出し、電話番号やアドレスが手帳に書き込まれていることを確認した。ジャスティンはと言えば、困った表情を浮かべながら頬をかいている。あの仕種が、私はたまらなく気に入っている。
「……何だか、私たちの周りって本当にお節介な人たちばかりね」
「やっぱりそう思います?しかしスコットとミッドガルツ少尉の組み合わせは予想出来なかったなぁ」
「ここにいつまでもいるわけにもいかないし、折角だから……皆の"悪意"は活用しよっか?」
私はいつもよりちょっと勇気を出して、ジャスティンの手を握って引く。少しして、私の手をジャスティンが握り返してくる。その手が思ったよりも大きくて、私は少し驚いた。
「んー、前にグリスウォールに潜り込んだ時に聞いた店があるのよ。そこでゆっくり食事でもどう?」
「お任せします」
楽しまなきゃ、絶対損よね。どうやらカイト隊&グリフィス隊プロデュースらしいデートではあるけれども、私とジャスティンは夕暮れに染まり始めた空の下、並んでゆっくりと歩き始めた。
私が向かったのは、バス停からそれほど離れていないブロックに店を構える、「ROCK'N CAFE OWL'S EYE NO.4」というカフェだった。どうやら経営者は騒動好き老人の知り合いらしく、「ここのソーセージは絶品だぜい」と力説していたことを思い出したのだ。ノルト・ベルカ生まれの父もスタウトの時はソーセージと決めてかかっているようで、マスタードをたっぷりと塗り回したソーセージにフォークを突き立てては「行儀が悪い」と母に叱られていたものである。古い木造のドアを開くと、ガランという鐘の音と共に、店内に流れる音楽が聞こえてきた。少し古めの、それもあまり激しくないロックが、バンガロー風の店内の雰囲気にぴたりとはまっていた。落ち着いて料理や飲み物を楽しめそうで、私は一人この店が気に入ってしまった。
「結構いいと思うんだけど……どうする?」
「こういう店来るの初めてなんでよく分からないんですけど……実は結構気に入りました」
「ちょっと背伸びして冒険……かな。じゃ、入りましょ」
ウェイターが飛んできて、私たちを店のやや隅の方にあるブースへと案内してくれた。既にアルコールが入って解放を喜び合っている一団とはわざわざ離れた所にしてくれたようで、なかなか気が利いている。メニューをざっと見て、ソーセージやハンバーガー、それに飲み物と追加を何点か注文する。
「実を言うと私もこういう店はあんまり入った事無いのよ。子供の頃はね、たまに父に連れられてウィスキー・バーなんかに行ったこともあるのだけど」
頬が少し赤いジャスティンを見ていると、何だか自分までが照れくさくなってきてしまう。ジャスティンの服装はラフだったけれども、案外良く考えているものなのね、と感心してしまった。それに引き換え、私は買い物に付き合わされるものだと思っていたから、飾り気無し。さらに言えば、化粧っ気もなし。
「……あーあ、ジャスティンがいると分かっていたら、私もう少しましな格好してきたのに。ごめんね、いつものラフな格好になっちゃって」
「そんなことないですよ。それは僕の台詞ですよ」
「そうかなぁ。多分ジャスティン気が付いていないと思うけど、この店に来る間すれ違った女の子たち、結構気にしていたわよ」
それは事実で、この店に入る前にすれ違ったティーンエイジゃーの一団などは、彼女たちから見れば「年増」に違いない私を睨み付けていた者までいたのだ。なーに、ひょっとして私が純真な若者を騙そうとしている悪女にでも見えるわけ?否応無く自分の年齢を思い知らさされたようで、私は思わず首を振った。そんな私の耳に、聞き慣れたギターサウンドが飛び込んできた。"FACE OF COIN"――時々部屋で聞いている曲の一つは、レイヴンに異動してきた直後、"ハートブレイク2"のコールサインで呼ばれる教官殿からデータをもらったものだ。どうやらジャスティンもこの曲を知っていたらしい。
「この曲、ジャスティンも知っているんだ」
「スコットから借りたCDに入っていたんですけどね。古いナンバーだけど不思議と馴染んじゃって」
「レイヴン配属時の教官殿がこの曲大のお気に入りだったのよ。昔の戦争で亡くなった戦友が大好きだった曲なんですって」
ちょうどそこに料理が運ばれてきて、私たちの会話は一時中断。中途半端な時間に起きて食事も軽いものしか基本的にはとっていなかったせいか、ハンバーガーとソーセージの香りが、空腹を訴える腹にトドメを与えたのだ。丁度良い味付けに舌鼓を打ちながら、私は目の前に座る少年の姿をじっと見つめた。その小さい身体に比べてはるかに大きく重いプレッシャーに耐え続けて、不正規軍を勝利に導いたトップエース「南十字星」が彼であるとは、この街の人々の知るところではない。でもこうしている姿は、多分年相応のものなのだろう。もし戦争が無ければ、彼は仲間たちとこんな時間を過ごしていずれ空を飛ぶようになる若者だったはずだ。戦争が、彼をこの国最高のエースパイロットに仕立て上げてしまったのだ。そして皮肉にも、その戦争のおかげで私は彼と出会ってしまったのだ。二人の向いている方向は同じだろうと確信はしている。ただ、同じ方向を向き続けられるのかどうか、私はそれが不安だった。何しろ、彼の意志はともかくとして、ジャスティンは間違いなく女性から好かれるタイプなのだ。オーレリアでの任務が終わった後も彼と今の関係を――いや、今以上の関係を築いていくには、越えなければならない障害が随分とあるような気がする。そんな肝心の話を切り出したかったのだけれども、何となく他愛の無い会話を交わしていくうちに時間が過ぎていく。そして、私はジャスティンがどこか生返事を返していることに気が付いた。ちょっと、どういうことよ?私は少し頬を膨らませて、ジャスティンをじっと見つめた。
「……ジャスティン、何だか上の空みたいね」
「え、あ、そんなことは……」
「そりゃね、私は同年代の子みたいに面白い話もあんまり出来ないし、口を開けば戦闘機の話がすぐに出てきちゃうけれど……やっぱりつまらないかな?」
そうなのだ!私ときたら、女性らしい会話のネタがほとんど無いのだ。別におしゃれに興味も無かったし、テレビドラマにも大して興味が持てなくてドキュメンタリー番組を好んでいたくらい。それに気が付いて私は一人落胆してしまった。だが、ジャスティンは別に退屈していたわけではなかったらしい。申し訳なさそうな表情で頬をかきながら、彼は私をじっと見つめた。うっ……ジャスティン、君ね、それは反則だよ。
「ごめんなさい。実はスコットに連れてこられる前も、ずっと悩んでいたんです。これから僕はどうしたらいいんだろう……って」
「これから――?」
「はい。否応無く戦場に放り込まれて、戦闘機を操り続けてきた僕は、戦争が終わった今どこへ歩いていけばいいのだろう……そんなことを考えていたんです。でも、何となく結論に辿り着いたような気がします。僕の進むべき道は、飛び続けることなんじゃないか……って。それが僕を支えてきてくれた人たちへの恩返しでもあるし、これから僕の後に空を目指すもっと下の世代たちに、この戦争の経験を伝えることにもなるんじゃないか、って。自分たちの手にしている平和の大切さを語り続ける人間がいなくちゃいけないんじゃないか……ちょっと、格好付けすぎかもしれませんけど」
難しいこと、考えてたんだね。でも、その台詞はジャスティンだからこそ言える言葉だよ。私は何度か首を振り、顔にかかった髪をそっとかき上げながら微笑んだ。
「いつの間にか、本当に強くなったんだね、ジャスティン。初めて知りあった頃とは別人みたい」
「僕は強くなんかないですよ。いつもいつも、ぐるぐると悩んでばかり」
「それは私も同じよ。私もね、ちょっと悩んでいたの。この国の戦争が終わって、レサス軍をとうとう撤退させたことは何より嬉しかったけれど、一つ重大な問題に気が付いたのよ」
私はジャスティンをじっと見つめた。何か手落ちでもあっただろうか、とジャスティンが訝しげに首を傾げている。――ちゃんと伝えなきゃね、自分の気持ち。逃げたがっている自分の心を軽く一押し。私は一歩を踏み出した。
「そんな顔しないで。別に戦闘のこととかじゃないわ。もっと、個人的な……そう、私にとっては重大な問題。この紛争が終われば、シルメリィ艦隊は再びオーシアへと戻ることになる。そう遠くないうちに……ね。そうしたら、会いたい人にもなかなか会えなくなっちゃうでしょ?それに気が付いたら、私もぐるぐる頭が回っちゃったの」
本当はね、私は一緒にいたいのよ、ジャスティンと。だって出会っちゃったんだから。ずっと一緒に飛び続けていきたい男性が、君だったんだから。本当は続けたい言葉はとてもそのまま言うことが出来ずに、私は別の言葉を紡ぎだす。
「だから、ミッドガルツに連れて来られた事、感謝しないとね。こうしてジャスティンと一緒に過ごしていたら、随分と気も楽になったわ。折角戦争が終わったのに、昨日も今日もゆっくり話をする時間無かったから。……本当はね、会って話をしたかったのよ」
「僕もです。僕も、誰かに僕の話を、僕の悩みを聞いて欲しかった。でも何だか……随分馬鹿みたいに悩んでいたんだな、という気分ですよ、今は」
私は腕時計をチラリと眺め、思った以上に時間が過ぎ去っていたことに気が付いた。今日は特に何事も無く過ぎそうだけれど、あんまり遅くなるとお節介な隊長殿たちがまた色々といらぬ勘繰りをしてくるかもしれない。
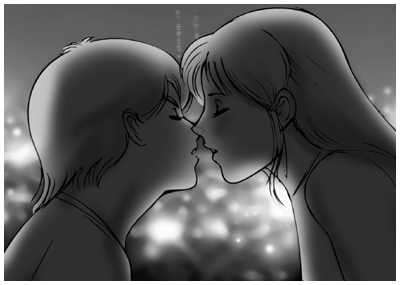 「……門限なし、ではあるけれど、さすがにあまり遅くなったら色々と言われそう」
「……門限なし、ではあるけれど、さすがにあまり遅くなったら色々と言われそう」
「スコット辺りが勝手に撒き散らしてくれそうな気がしますよ」
ちょっと名残惜しくなりながら、チェックを頼む。レシートを覗き込んだジャスティンと支払いをめぐってああでもないこうでもないと話をした結果、ジャスティンが1/3を持つことに決まる。苦笑いしている店員に紙幣を差し出して店の外へと出ると、外はすっかり夜の帳が下り、涼しい風が通り過ぎていく。あーあ、楽しい時間も終わりかぁ――大通りへと歩き出そうとした私は、自分の手をぐっと握ったジャスティンによって急停止を強いられる。
「ジャスティン?」
「もう少し、歩きませんか?もうちょっと、話もしたいし……」
私に断る理由などあるはずも無い。むしろ、ジャスティンが引き止めてくれたことに心から感謝したい気分だった。
ジャスティンに連れられていった市民公園の展望台は、その名ほどに大層なものではなかった。けれども、高台に張り出したバルコニー状の展望台から見下ろすグリスウォールの夜景はなかなかのもので、多分隠れたデートスポットの一つなのだろう。私は展望台の柵に肘を付きながら、傍らに立つジャスティンを見上げた。
「空の上からの眺めもいいけど、こういうところから見るのもなかなかいいわね」
ジャスティンは笑いながら、でも何かを決心したような真面目な顔になって私の方を向いた。
「フィーナさん、少しの間だけ、待っててくれませんか?」
「え……」
「今はまだ、無理かもしれないですけど、いつの日か僕は必ずレイヴンを目指します。今みたいに会えない間は辛いですけど……だから、それまで、待っててくれませんか?」
胸の奥で熱いものが広がっていくような気分になる。私の堂々巡りは、どうやら最高の結果で報われることになるらしい。ジャスティンの願いは、決して夢物語ではない。レイヴンの構成国の一つであるオーレリアからの派遣は、充分に現実的な話だ。いや、そんな難しいことはもうこの際どうでも良かった。私のために、彼はレイヴンを目指してくれる。これ以上の最高の言葉がどこにあるだろう?私は言葉で返事をせず、一歩隣へ寄って、そしてジャスティンの肩へと頭を乗せた。びくり、とジャスティンが直立不動の姿勢を取ろうとしたのが分かる。
「……適齢期逃したら、ジャスティンのせいだからね?」
返事を聞くよりも早く、私はジャスティンの唇を自分の唇で塞いだ。今は、少しでもこうしていたい――ジャスティンの温もりを傍に感じながら、私は幸せな気持ちを胸の中でそっと抱き締めたのだった。
南十字星の記憶&偽りの空トップページへ戻る
トップページへ戻る
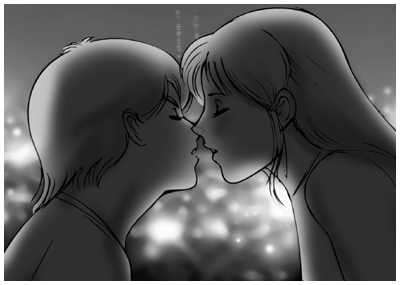 「……門限なし、ではあるけれど、さすがにあまり遅くなったら色々と言われそう」
「……門限なし、ではあるけれど、さすがにあまり遅くなったら色々と言われそう」