ブレーク・スルー
世界が回る。獲物の姿を追い、一体何度天と地をひっくり返して飛んだやろ?クールに決めんのが信条のはずが、ジャスのおかげですっかりガチンコ熱中路線。……ま、嫌いやないけど。そんなことを呟きながら、スコットはミニ・ロットバルトと呼ぶべき「脳味噌の詰まった」戦闘機部隊を相手に獅子奮迅の戦いを繰り広げている。敵の動きは物凄くコンパクト。何しろ生身が無い。縦だけじゃなく横方向にも平気で回転してくる物騒な代物。最初はその機動性に泡を食っていたのも事実だったが、まともに対抗すること自体が誤りだと気が付いた今は、「どんどんかかってこいや!」の気分になっていた。
「グリフィス3、1機行った!右下方から上がっていく、任せた!」
「こっちも捕捉した!ぶち抜いたるでぇ!!」
戦闘機というよりはロケットのような速さで上がってくる敵機と高度が並ぶタイミングを図る。XRX-45ほどではないにしても、XFA-24Sのコフィンシステムにもコンピュータによる戦闘支援機能はもちろん付いている。スコットが愛用しているのは、敵の航跡を履歴として表示する機能だった。機体を少しバンクさせて針路を修正し、俄か共闘することになってしまったアレクト3の追撃を振り切ろうと上昇する獲物に対して攻撃態勢。愛機を加速させて敵の針路上に割り込んでいく。攻撃タイミングはほんのコンマ数秒。予定通過ポイントの400メートル手前で、追加ガンポッド分も合わせて、スコットはトリガーを引き絞った。目で捉えるのも難しいくらいの速度で敵機が目の前を通過。交錯点はあっという間に後方へと去る。そのまま操縦桿をゆっくり目に引いてループ上昇。上方に視線を向けると、黒煙を吐き出した敵機がそれでも勢いを止めずに高空へと舞い上がっていく姿が目に入った。機関砲弾のシャワーは、機首から後ろまで、多数の命中痕を穿つことに成功していた。推力も失い、惰性で昇り続ける敵機のコクピットにも攻撃は直撃し、ルシエンテスたちの実験の犠牲となったパイロットの頭脳は消し炭と化して跡形も無い。ほどなく、エンジンから回った炎は機体全体へと燃え移り、犠牲者の小さな骸ごと、錐もみ状態になって墜ちていく。
「ナイスキルってところだな。少しは見直したぜ」
「ほとんど勘やけどな。でもま、そっちの追い込みのおかげやで、アレクト3」
「じゃ、二人の戦果っつーことにしとくか」
「図々しいやっちゃなー。ま、勝手にせい」
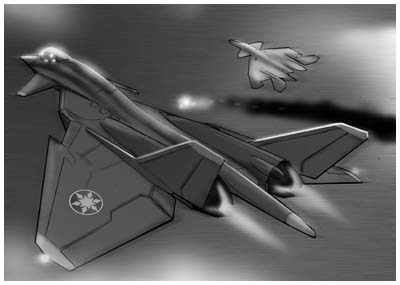 結構な数を落としたつもりだったが、それでもまだフリーの小物がブンブンと飛び回っている。アレクト隊に4機しか渡さなかった割には、随分と新型とやらは量産をされていたらしい。アレクトの面々も含め、機体格納庫の中では脳味噌だけの戦隊機が静かに眠っていることを知らなかった連中は多いのかもしれない。初めからその存在が分かっていれば戦闘の初っ端から使っていただろうし、アレクト隊もそれを前提とした戦術を組み立てて来たに違いない。全く、ナバロのおっさんは煮ても焼いても食えない、つまりはそういうことやろ?味方すら平気で騙して死地へ赴かせる――それは政治の仕事であることを、スコットは理解してもいる。そうやって踊らされる立場になるのは真っ平ご免だったが、現実問題としてオーレリアですらその構図は変わらない。戦場で命のやり取りを繰り広げるのは、どんな場合でも前線の兵士たちなのだから。スコットがナバロを許せないのは、奴がその構図を自らの利権と欲望のために最大限利用したからだった。レサスの兵士たちに個人的な恨みは全く無かったが、今スコットの前に立ちはだかっている敵は細かい理屈を置いておいて、「とにかく気に食わんから叩き潰す」対象でしかなかった。それも、既に死んでいる人間の残りカスともなれば、容赦の必然性すら感じない。どちらかと言えば、さっさと眠らせてやる、というところだろうか。どうやら人間を辞めて来たらしい化け物を相手にしている親友のためにも、余計なハエは出来る限り叩き落しておくしかない。それを自らの役目、とスコットは定めていたのだった。
結構な数を落としたつもりだったが、それでもまだフリーの小物がブンブンと飛び回っている。アレクト隊に4機しか渡さなかった割には、随分と新型とやらは量産をされていたらしい。アレクトの面々も含め、機体格納庫の中では脳味噌だけの戦隊機が静かに眠っていることを知らなかった連中は多いのかもしれない。初めからその存在が分かっていれば戦闘の初っ端から使っていただろうし、アレクト隊もそれを前提とした戦術を組み立てて来たに違いない。全く、ナバロのおっさんは煮ても焼いても食えない、つまりはそういうことやろ?味方すら平気で騙して死地へ赴かせる――それは政治の仕事であることを、スコットは理解してもいる。そうやって踊らされる立場になるのは真っ平ご免だったが、現実問題としてオーレリアですらその構図は変わらない。戦場で命のやり取りを繰り広げるのは、どんな場合でも前線の兵士たちなのだから。スコットがナバロを許せないのは、奴がその構図を自らの利権と欲望のために最大限利用したからだった。レサスの兵士たちに個人的な恨みは全く無かったが、今スコットの前に立ちはだかっている敵は細かい理屈を置いておいて、「とにかく気に食わんから叩き潰す」対象でしかなかった。それも、既に死んでいる人間の残りカスともなれば、容赦の必然性すら感じない。どちらかと言えば、さっさと眠らせてやる、というところだろうか。どうやら人間を辞めて来たらしい化け物を相手にしている親友のためにも、余計なハエは出来る限り叩き落しておくしかない。それを自らの役目、とスコットは定めていたのだった。
その親友の姿をレーダー上の位置を確認し、視線を動かしたスコットは、化け物の操る化け物機体から放たれる多数の射出物の吐き出す炎と雨のように降り注ぐ飛翔体から、これまた尋常ではない機動で辛くも直撃を免れているXRX-45の姿に気が付いた。既に無傷と呼べる状態ではなく、白い機体の一部の部品は脱落しているようにも見える。それでも、本来のずば抜けた機動性自体は損なわれること無く、「南十字星」のエンブレムが気安い笑いを振り撒いている。あれほどの苦境の中、ジャスの奴は勝負をあきらめていないのだ。……ま、最愛の女性を撃墜されれば、理屈抜きでブチ切れるのが道理ではあるが。なら、悪友としてやるべきことは決まっている。さっさと外野を黙らせて、あのイカレた野郎をぶちのめすパーティに参加するまでのこと。敵の小物が大きく回りこむようにして、XFA-24Sとフェンリアの方向に向かってくる。数は2。そう、向かってくるのが分かるから、怖くは無い。パイロットとしての経験がある人間の脳を活用している割に、攻撃パターンが豊富ではないことにスコットは気が付いていた。もちろん、近接格闘戦時の圧倒的な機動には何度も肝を冷やされてはいたが、人間が乗っている戦闘機のように、攻撃タイミングを伺って大きく旋回したり、僚機と遠距離で連携して相手を罠にはめたり……といった戦術を駆使することが無い。それが故に、必ず敵機は攻撃態勢を取って突っ込んでくるのである。光学兵器の威力は半端ではなかったが、人間ならではの戦い方に、あの機体は慣れていない。さらに言うなれば、どうやら「経験」と「機体性能」とが必ずしもバランスを取ってはいないらしい。時折だが、明らかにアンコントロールを起こして意味の無いスピン状態に陥るような光景が何度もあったのだ。要するに、あのイカレ野郎は欠陥を承知の上で営業デモをやってるっちゅーことや。悪徳商人の丁稚に相応しいやり口やな――マスクの下で、スコットの口元に微笑が浮かぶ。猛烈な加速を得て突っ込んでくる敵機に対し、愛機をバレルロールさせてその斜線上から逃れる。ミサイルのような速さで頭上を通過した敵機はあっという間に後方へと見えなくなる。だが、有人機にはおよそ実現不可能な機動で、再びあのハエはたかってくる。こちらは無理せず、ゆっくりと上昇しながらインメルマル・ターン。水平に戻したところで、フェンリアと翼を並べる。
「グリフィス3、仕掛けるぞ!」
「オーライ、アレクト3。おいジャス、聞こえとるか?あとちょっとで欠陥戦闘機を退治して、ブンブン煩いハエの王様退治に加勢したるさかい、もうちょい辛抱しとけよ。……っちゅーか、ワイかて一発ぶちかましたいから出番取っとけや、ええな!!」
一方的に言いたいことをしゃべり切ってから、スコットは意識を前方へと集中させた。ハエを叩き落すくらいの弾薬はまだ残っている。敵の最大の弱点。それは、あの高速の突っ込み。頭からカチ割ったる――レーダーロックを起動させ、ミサイルシーカー越しに敵の姿を睨み付ける。地上では女たらしの遊び人という評価の定着した男の、もう一つの素顔を知る者は少ないかもしれない。だが、この時の戦いぶりが、「南十字星」に告ぐオーレリアの若手トップエースとしての評価を確固たるものにするのであった。
最新鋭かつ最高の性能を持つ戦闘機が最強とは限らないのがこの空の世界。既に時代遅れの機体性能であるはずのF-4Eを自在に操り名を馳せた旧ベルカ空軍の「銀色のイヌワシ」のように、結局はその機体を操る人間が勝敗を左右にする。だからこそ、パイロットたちは最前線で命のやり取りをすることになる相手に対して、互いに畏敬の念を抱くのだ。だが、少なくとも今グランディスたちの周りを飛び交う敵機はその理屈から外れた存在でしかなかった。ただ、戦うためだけにその「性能」を追求されただけの奇形児。グランディスの目には、そうとしか映らなかったのである。かつての同志たちの言葉を歪んだ形で吐くサンサルバドルの隊長機を見たら、きっと祖国の恩人である"マカレナ"は悲しむに違いない。その薫陶を受けてパイロットとしての道を歩み続けたグランディスにしても、ゼネラル・リソースの尖兵と成り果てたルシエンテスたちの存在は認めるわけにはいかなかったのである。
「グリフィス5より4へ。小物の相手はもう大丈夫そうだが、ジャスティンの援護に回らなくても良いか?」
「グリフィス7から隊長機、複数機で一斉に攻撃を浴びせるというわけにはいきませんか?」
レーダーから姿を消していくのは、敵の機体ばかりとなっていた。スコットたちも見事に戦っている。所詮、修羅場をいくつも潜り抜けてきた生身の人間の技量に、脳味噌だけの出来損ないが及ばないことが証明されたというわけだ。だが、血迷ったとはいえ「ロットバルト」と奴が呼称する敵機だけは別格だ。
「――そうしてやりたいのはやまやまだが、あの反則技を何とかしない限りは単なる無駄弾になるだけだ。それに、乱戦状態になるのがジャスティンに幸いするとも限らない。あたいらが盾にされたとき、躊躇いも無く引き金を引けるような坊やじゃないからね。可哀想だが、逆にタイマンの方が今はまだいい」
「やはり隊長も同意見か。あの苦境を凌いでいる姿を黙ってみているしかないのは辛いが、我々の中で最も最新鋭かつ最高の機動性を誇るのがジャスティンのXRX-45だ。加勢して、逆にボカチン食らう確率は我々の方が高い」
「ロットバルト」の放つ小型タイプのミサイルは、レサス軍独自の技術ではないだろう。恐らくは、グレイプニル建造期に、空中要塞の概念と共に持ち込まれたのだ――エストバキアから。極少数が生産されたCFA-44という機体の兵装の中に、同種のマイクロミサイルが含まれていたことが判明している。アネア大陸での紛争から既に数年が経過しているということは、性能面では更なるバージョンアップが図られているといっても過言ではない。そんな物騒な攻撃を立て続けに浴びながら、辛くも凌いでいる「南十字星」の度胸と腕前は、「ロットバルト」以上に十分化け物ではあるのだが。だが、さらに恐ろしいのは、かつてルシエンテスとマクレーンが参加していた開発プロジェクトでは、試作機のパイロットが敵のミサイルの誘導すら乗っ取ったという点だ。ジャスティンには伝えていないが、XR-45Sの改良指針には、強力な電子戦機能を搭載するプランが含まれており、かつてのテストパイロットがやって見せたというミサイル乗っ取りまで盛り込まれていたのだ。そのプランを策定したのは、他ならぬゼネラル・リソース。「ロットバルト」もゼネラル謹製の最新鋭戦闘機、しかも乗っているのはあのルシエンテス。敵ミサイルまで自らの攻撃に利用出来る物騒な便利機能を積んでいたとしてもおかしくはない。何しろ、何でもアリの戦い方を現実に繰り広げているのだから。それに対応するには、強力な対電子戦防御が施されていることが前提となる。
「ファレーエフの言うとおり、さ。あたいのADF-01Sならともかく、アンタらの機体じゃ最悪の場合乗っ取られる危険すらある。燃料タンク付きの特大弾頭の出来上がり、というやつだ。……とはいえ、黙って指くわえているのはあたいの性分じゃないんだけどねぇ」
小型タイプが2機、自動目標探知でXRX-45の姿を捉えたのか、針路を変更して右旋回。脳味噌だけにしては綺麗な編隊を維持したまま、ミサイルから逃れるべく回避機動を続けるXRX-45に向かって加速を開始する。
「グリフィス6よりグリフィス4。小型タイプ2、こちらでは追いきれない。支援を要請!」
「あいよ、良く見えてる。ファレーエフ!あたいはちょいと一撫でしてくる。その間の指揮は任せるよ」
「おいおい隊長!」
 一方的に指揮権を押し付けて、グランディスはスロットルを押し込んだ。GBXX-435Paエンジンが怒りの咆哮をあげる。ADF-01Sの大柄な機体が轟然と加速し、程なく音速へ到達。一瞬水蒸気の白い煙が機体の外を覆ったのも束の間、更に加速する愛機は前方を行く敵小型タイプの後ろを追う。XRX-45のように華麗に舞うことは出来なくとも、パワーという点ではADF-01Sにアドバンテージがあるくらいなのだ。コフィン・ディスプレイ上には既にミサイルシーカーが表示され、獲物の姿を捕捉している。同時に、激しいポジションの奪い合いを繰り広げている2機の姿も。あそこに到達させるわけにはいかない。慣れた身体の感覚が自然とミサイルレリーズに指を乗せていく。ロックオン、ファイア。そこにほんの少しの力を入れるだけで、敵機と搭乗者を焼き尽くす道具を撃ち出す感覚。――ジャス坊、アンタを守ってやりたいのはあたいらだって同じなんだぜ。マスクの下で微笑を浮かべたグランディスは、選択兵装を素早く切り替えた。ある程度エネルギーさえ溜まっていれば何度も使用出来る戦術レーザーとは違い、腹の下に抱えてきたレールガンはしっかりと弾数制限がある。ハイレディン艦隊を守るべく敵艦隊に破壊の雨を降らした今、ある意味唯一強敵のコントロールを受けないはずの一撃は、最後の一発となっていた。本音を言えば、勿体無い。あのキチガイ本体にぶちこんで何もかも吹き飛ばしてやりたいのが真情。やや上方、上から下へと舞い降りながら尚もポジション獲りを続けるXRX-45。ジャスティンの腕前が尋常のものでないのは事実だ。だが、同時に複数方向から一斉に狙われたとしたら、あの坊やでもひとたまりも無いだろう。それに――あの二人の戦いは、喩えるなら宿命の対決というやつだ。ルシエンテスの方にその意識があるかどうかは知らないが、ジャスティンにとっては恋人の仇。さらに、未来へ進むためにはどうしても打ち倒さなければならない相手だ。悔しいが、あたいはお呼びでない。ならば、迷うことなど何も無い。障害は排除してやるだけのこと。モニターに表示された照準レティクルが変更される。残弾1、と表示されたモニターを確認し、グランディスは邪魔者たちの姿を睨み付ける。
一方的に指揮権を押し付けて、グランディスはスロットルを押し込んだ。GBXX-435Paエンジンが怒りの咆哮をあげる。ADF-01Sの大柄な機体が轟然と加速し、程なく音速へ到達。一瞬水蒸気の白い煙が機体の外を覆ったのも束の間、更に加速する愛機は前方を行く敵小型タイプの後ろを追う。XRX-45のように華麗に舞うことは出来なくとも、パワーという点ではADF-01Sにアドバンテージがあるくらいなのだ。コフィン・ディスプレイ上には既にミサイルシーカーが表示され、獲物の姿を捕捉している。同時に、激しいポジションの奪い合いを繰り広げている2機の姿も。あそこに到達させるわけにはいかない。慣れた身体の感覚が自然とミサイルレリーズに指を乗せていく。ロックオン、ファイア。そこにほんの少しの力を入れるだけで、敵機と搭乗者を焼き尽くす道具を撃ち出す感覚。――ジャス坊、アンタを守ってやりたいのはあたいらだって同じなんだぜ。マスクの下で微笑を浮かべたグランディスは、選択兵装を素早く切り替えた。ある程度エネルギーさえ溜まっていれば何度も使用出来る戦術レーザーとは違い、腹の下に抱えてきたレールガンはしっかりと弾数制限がある。ハイレディン艦隊を守るべく敵艦隊に破壊の雨を降らした今、ある意味唯一強敵のコントロールを受けないはずの一撃は、最後の一発となっていた。本音を言えば、勿体無い。あのキチガイ本体にぶちこんで何もかも吹き飛ばしてやりたいのが真情。やや上方、上から下へと舞い降りながら尚もポジション獲りを続けるXRX-45。ジャスティンの腕前が尋常のものでないのは事実だ。だが、同時に複数方向から一斉に狙われたとしたら、あの坊やでもひとたまりも無いだろう。それに――あの二人の戦いは、喩えるなら宿命の対決というやつだ。ルシエンテスの方にその意識があるかどうかは知らないが、ジャスティンにとっては恋人の仇。さらに、未来へ進むためにはどうしても打ち倒さなければならない相手だ。悔しいが、あたいはお呼びでない。ならば、迷うことなど何も無い。障害は排除してやるだけのこと。モニターに表示された照準レティクルが変更される。残弾1、と表示されたモニターを確認し、グランディスは邪魔者たちの姿を睨み付ける。
「脇役は脇役らしく、静かにネンネしてな、三下!」
躊躇いなど微塵も無く、グランディスはトリガーを引く。光の塊のような弾頭が瞬時に空を貫き、ほとんど同時に目標に到達した。回避不能の速度と衝撃。中に乗っかっていた脳味噌とコンピュータは、異常な速度で接近する飛翔体をデータとして捉えていただろうか?粉々に粉砕された敵の残骸が、衝撃波に引きずられて舞い散る。レーダー上からも敵の姿が消滅したことを確認し、愛機を傾けて旋回させる。
「さあ、ジャス坊。円卓の鬼神の娘に惚れた男の意地、あたいに見せてご覧」
ヴァレーから預かった大切な雛鳥は、既に大きな翼を広げて在るべき場所に飛び立った。今度は、ウスティオから世界へと羽ばたこうとする雛鳥が、自らの旅立ちを示す時だ。この大一番、多分一生思い出になるのだろうな――ほとんど敵の姿が見えなくなってきた空を見上げながら、グランディスは二人の戦いをしっかりと見届けることを決めたのだった。
飛び立ってきた敵は、全部が全部小物というわけではなかった。ルシエンテスの大馬鹿野郎の乗る「ロットバルト」とやらは別格として、小物よりは二周りは大きい有人タイプも混ざっている。普通じゃない機動性能を持っているということは、中に乗ってるのは改造人間か。全く、脳だの改造だの、ナバロの旦那は相当にエグイものがお好みらしい。
「ちっくしょ、動きだけは素早い、ってのわぁぁぁっ!!」
その有人タイプに張り付かれていたラターブルの悲鳴が聞こえてくる。同時に、奴の乗るX-02の右エンジンから黒煙が溢れ出す。翼端に太陽の光を反射させた敵機が、もう興味は無いとでも言いだけに戦闘続行不能になった獲物から離れていく。
「隊長ぉ、すんません!」
「相手が悪い。空母まで持ちそうか?」
「なぁに、最後は泳いでいきますよ」
「フ、そうだな。バトルアクス隊のお約束だ。……必ず帰還しろ。いいな。離脱は支援してやる」
残りの弾薬はだいぶ少なくなってきていたが、敵の数もそうは残っていない。X-02を仕留めたあの敵を、自分が何とかすれば良いだけの事。戦域から離脱コースを取り始めたラターブル。旋回してその後ろを取ろうとする敵機の前に、マクレーンは立ちはだかった。
「――この空は通行止めだ。悪いが、人間捨てた化け物を残しておくほど、俺は心が広くないんでな」
「初めからこちらの狙いはアンタだ、バトルアクス。お前の……お前たちのおかげて……俺たちはぁぁっ!!」
敵機の翼の下から、ミサイルが数本切り離される。この相対速度で当たるようなものではなかったが、機体をロールさせて射線上から逃れつつ敵とすれ違う。ミサイルの白い排気煙が、マクレーンの頭上を覆った。一度後方を振り返ると、どうやらルシエンテスが乗っているのと同様の有人タイプがスプリットS、というよりはほとんどその場回転で反転していた。やれやれ、XFMXにはそこまでの機動性はなかったんだがな……かつて操っていた試作機の感覚を思い出しながらマクレーンは苦笑する。大柄な機体故か、それとも機体設計の問題か、XFMXもラダーだけでの水平方向への動きはあまり良くなかった。どうやら、その後継機たるフェンリアやロットバルトにも、その特性は引き継がれているらしい。もっとも、あれだけくるくると縦方向に回れるんだったら、そのネガは完全に相殺されていると言っても良かったが。高度を下げた相手に対し、こちらはループ上昇。愛機YR-99が、軽やかに空を駆け上がっていく。ゼネラル・リソースの試作機の中で「Rナンバー」と呼ばれる新系統のコンセプト機の名に相応しく、最新技術の塊とも言って良い機体はこれまでのマクレーンの常識の外にある構造だった。だが正直、飛ばす方にとってはその辺りの差異はあまり重要ではない。要は、命を預けて飛ぶに足る機体かどうか、戦場で通用する性能を持っているか、ただそれだけだ。乗りこなせなければ死が待ち受けるという点で、戦闘機には共通する何かがあるに違いない。空に鮮やかな弧を描いてループの最頂点に達したところで、スロットルを切る。天地逆転の状態で推力を失った機体は、鎌首をもたげる様にがくんと真下を向く。下から上昇してくる敵機の姿をマクレーンの瞳が捉える。
「――悪いが、こっちは恨まれる筋合いが無いんだがな。向かってくるなら容赦はしないぜ」
「お前らが……解放軍が革命の道筋を全て台無しにしてくれたんだ。お前の首を獲って、祖国改革の礎にしてくれる。大人しく裁かれろ、ブルース・マクレーン!!」
「人の話は聞けってのに……全く!!」
敵機の攻撃の方が早い。翼の下から切り離された通常型のミサイルが加速を開始すべく炎を吐き出している。だが、このポジションではかわす事は容易い。双方の速度があまりにも速すぎるのだ。射線から機体をずらしてやるだけで、難なく回避が出来る。それはロットバルト相手であったとしても同じ。むしろ注意すべきはその後だ。あの反則技のようなその場回転から敵はこちらの後背にへばり付く戦法を取ってくるだろう。振り切るための算段はいくつも持ってはいたが、正直これ以上体力と気力をすり減らすのはご免被りたいというのがマクレーンの本音だった。さて、どうする?スロットルを押し込んでパワーダイブしようとした腕を止める。水平方向への移動後、バレルロールを組み合わせて相手の射線とミサイルの機動から逃れた今なら、それほど下降スピードも付いていない。後方へと抜けた敵機はまだ反転する素振りがない。仕掛けるなら、ここがチャンスだ。昔の自分ならここで躊躇していただろうが、今の自分は違う。それにだ。この俺の首を獲ろうとする相手なら、本気の本気を見せてやるのが礼儀というものだ。自分自身が勝ち残るためにも、だ。機体を90°ちょいロールさせ、目一杯操縦桿を引く。ロットバルトほどではないが、勢い良くスナップアップした機首が天頂を向く。目の前に広がるのは蒼天。スロットルをぐいと押し込んで少しばかり機体を加速させるが、これはフェイント。それでも、軽量級の機体はぐいと押し上げられる。だが上昇に十分な推力を得られずに、すぐにその速度は減じていく。一方で、敵機は思ったよりも近くで例の鮮やかな反転を決めていた。その姿を確認して、マクレーンは苦笑を浮かべた。
 「取ったぞ、バトルアク……!!いない、どこだ!?」
「取ったぞ、バトルアク……!!いない、どこだ!?」
「ルシエンテスの野郎に改造されたことは気の毒だと思うがな。今はお前なんぞに関っちゃいられないんでな。……あばよ」
推力を失って失速するYR-99は、右方向に倒れこみながら降下し始める。ちょうどその前方に、その場反転から降下しようとするロットバルトの横腹があった。マクレーンの右指がトリガーを引き、撃ち放たれた機関砲弾はロットバルトの機体にシャワーを浴びせていく。こうなれば、コフィンで覆われていることは余り意味が無い。言葉に表すのが難しいように悲鳴が聞こえ、その後敵の声は途絶した。上手い具合に速度が落ちていた状態であったことが、敵には災いした。全体を容赦なく撃ち抜かれた敵機から、左主翼が脱落。二つの大きな塊は、炎に包まれながら大地目指して落ちていく。哀れむわけではなかったが、マクレーンは旋回しながらその姿を見送った。
「全ての元凶は、あの日あの時、そしてよりにもよって戦友から始まったわけか……」
"ブルース、ブルース!その元凶に、南十字星が仕掛けるよ!"
「何だって!?」
"って、あの子何考えてんの!?真正面から突っ込むつもりだよ!!"
「あんの馬鹿!」
ここから間に合うかどうかは分からなかったが、マクレーンは今度こそ本気でスロットルを押し込んだ。色々と教えてきたつもりだが、自棄になるとか、特攻なんてものを教えたつもりは無かった。お前に死なれちゃ、俺の立つ瀬がないんだよ!!ジャスティンには何か策があるのかもしれないが、よりにもよって敵の真正面から突っ込んでいくなんて、リスクが大きすぎるというものだ。
「お前だけで、ケリ付けようと思うんじゃねぇぞ、坊主!!待ってろ、今行ってやる!!」
"ボクも行くよ。ここが決戦だもの。大丈夫、マクレーンなら間に合うよ"
妖精の予言はアテにならないのが相場ではあったけれど、今度ばかりは信じたいものだとマクレーンは笑った。そんなマクレーンの意志を受け取ったかのように、YR-99は轟然と加速する。その進む先、蒼空に白い飛行機雲を刻みつけながら、対峙する2機の姿があった。
南十字星の記憶&偽りの空トップページへ戻る
トップページへ戻る
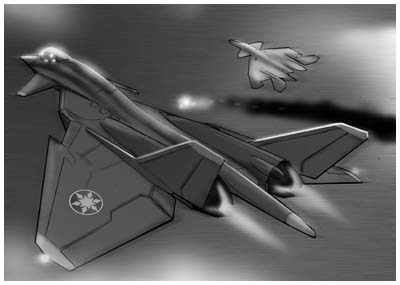 結構な数を落としたつもりだったが、それでもまだフリーの小物がブンブンと飛び回っている。アレクト隊に4機しか渡さなかった割には、随分と新型とやらは量産をされていたらしい。アレクトの面々も含め、機体格納庫の中では脳味噌だけの戦隊機が静かに眠っていることを知らなかった連中は多いのかもしれない。初めからその存在が分かっていれば戦闘の初っ端から使っていただろうし、アレクト隊もそれを前提とした戦術を組み立てて来たに違いない。全く、ナバロのおっさんは煮ても焼いても食えない、つまりはそういうことやろ?味方すら平気で騙して死地へ赴かせる――それは政治の仕事であることを、スコットは理解してもいる。そうやって踊らされる立場になるのは真っ平ご免だったが、現実問題としてオーレリアですらその構図は変わらない。戦場で命のやり取りを繰り広げるのは、どんな場合でも前線の兵士たちなのだから。スコットがナバロを許せないのは、奴がその構図を自らの利権と欲望のために最大限利用したからだった。レサスの兵士たちに個人的な恨みは全く無かったが、今スコットの前に立ちはだかっている敵は細かい理屈を置いておいて、「とにかく気に食わんから叩き潰す」対象でしかなかった。それも、既に死んでいる人間の残りカスともなれば、容赦の必然性すら感じない。どちらかと言えば、さっさと眠らせてやる、というところだろうか。どうやら人間を辞めて来たらしい化け物を相手にしている親友のためにも、余計なハエは出来る限り叩き落しておくしかない。それを自らの役目、とスコットは定めていたのだった。
結構な数を落としたつもりだったが、それでもまだフリーの小物がブンブンと飛び回っている。アレクト隊に4機しか渡さなかった割には、随分と新型とやらは量産をされていたらしい。アレクトの面々も含め、機体格納庫の中では脳味噌だけの戦隊機が静かに眠っていることを知らなかった連中は多いのかもしれない。初めからその存在が分かっていれば戦闘の初っ端から使っていただろうし、アレクト隊もそれを前提とした戦術を組み立てて来たに違いない。全く、ナバロのおっさんは煮ても焼いても食えない、つまりはそういうことやろ?味方すら平気で騙して死地へ赴かせる――それは政治の仕事であることを、スコットは理解してもいる。そうやって踊らされる立場になるのは真っ平ご免だったが、現実問題としてオーレリアですらその構図は変わらない。戦場で命のやり取りを繰り広げるのは、どんな場合でも前線の兵士たちなのだから。スコットがナバロを許せないのは、奴がその構図を自らの利権と欲望のために最大限利用したからだった。レサスの兵士たちに個人的な恨みは全く無かったが、今スコットの前に立ちはだかっている敵は細かい理屈を置いておいて、「とにかく気に食わんから叩き潰す」対象でしかなかった。それも、既に死んでいる人間の残りカスともなれば、容赦の必然性すら感じない。どちらかと言えば、さっさと眠らせてやる、というところだろうか。どうやら人間を辞めて来たらしい化け物を相手にしている親友のためにも、余計なハエは出来る限り叩き落しておくしかない。それを自らの役目、とスコットは定めていたのだった。 一方的に指揮権を押し付けて、グランディスはスロットルを押し込んだ。GBXX-435Paエンジンが怒りの咆哮をあげる。ADF-01Sの大柄な機体が轟然と加速し、程なく音速へ到達。一瞬水蒸気の白い煙が機体の外を覆ったのも束の間、更に加速する愛機は前方を行く敵小型タイプの後ろを追う。XRX-45のように華麗に舞うことは出来なくとも、パワーという点ではADF-01Sにアドバンテージがあるくらいなのだ。コフィン・ディスプレイ上には既にミサイルシーカーが表示され、獲物の姿を捕捉している。同時に、激しいポジションの奪い合いを繰り広げている2機の姿も。あそこに到達させるわけにはいかない。慣れた身体の感覚が自然とミサイルレリーズに指を乗せていく。ロックオン、ファイア。そこにほんの少しの力を入れるだけで、敵機と搭乗者を焼き尽くす道具を撃ち出す感覚。――ジャス坊、アンタを守ってやりたいのはあたいらだって同じなんだぜ。マスクの下で微笑を浮かべたグランディスは、選択兵装を素早く切り替えた。ある程度エネルギーさえ溜まっていれば何度も使用出来る戦術レーザーとは違い、腹の下に抱えてきたレールガンはしっかりと弾数制限がある。ハイレディン艦隊を守るべく敵艦隊に破壊の雨を降らした今、ある意味唯一強敵のコントロールを受けないはずの一撃は、最後の一発となっていた。本音を言えば、勿体無い。あのキチガイ本体にぶちこんで何もかも吹き飛ばしてやりたいのが真情。やや上方、上から下へと舞い降りながら尚もポジション獲りを続けるXRX-45。ジャスティンの腕前が尋常のものでないのは事実だ。だが、同時に複数方向から一斉に狙われたとしたら、あの坊やでもひとたまりも無いだろう。それに――あの二人の戦いは、喩えるなら宿命の対決というやつだ。ルシエンテスの方にその意識があるかどうかは知らないが、ジャスティンにとっては恋人の仇。さらに、未来へ進むためにはどうしても打ち倒さなければならない相手だ。悔しいが、あたいはお呼びでない。ならば、迷うことなど何も無い。障害は排除してやるだけのこと。モニターに表示された照準レティクルが変更される。残弾1、と表示されたモニターを確認し、グランディスは邪魔者たちの姿を睨み付ける。
一方的に指揮権を押し付けて、グランディスはスロットルを押し込んだ。GBXX-435Paエンジンが怒りの咆哮をあげる。ADF-01Sの大柄な機体が轟然と加速し、程なく音速へ到達。一瞬水蒸気の白い煙が機体の外を覆ったのも束の間、更に加速する愛機は前方を行く敵小型タイプの後ろを追う。XRX-45のように華麗に舞うことは出来なくとも、パワーという点ではADF-01Sにアドバンテージがあるくらいなのだ。コフィン・ディスプレイ上には既にミサイルシーカーが表示され、獲物の姿を捕捉している。同時に、激しいポジションの奪い合いを繰り広げている2機の姿も。あそこに到達させるわけにはいかない。慣れた身体の感覚が自然とミサイルレリーズに指を乗せていく。ロックオン、ファイア。そこにほんの少しの力を入れるだけで、敵機と搭乗者を焼き尽くす道具を撃ち出す感覚。――ジャス坊、アンタを守ってやりたいのはあたいらだって同じなんだぜ。マスクの下で微笑を浮かべたグランディスは、選択兵装を素早く切り替えた。ある程度エネルギーさえ溜まっていれば何度も使用出来る戦術レーザーとは違い、腹の下に抱えてきたレールガンはしっかりと弾数制限がある。ハイレディン艦隊を守るべく敵艦隊に破壊の雨を降らした今、ある意味唯一強敵のコントロールを受けないはずの一撃は、最後の一発となっていた。本音を言えば、勿体無い。あのキチガイ本体にぶちこんで何もかも吹き飛ばしてやりたいのが真情。やや上方、上から下へと舞い降りながら尚もポジション獲りを続けるXRX-45。ジャスティンの腕前が尋常のものでないのは事実だ。だが、同時に複数方向から一斉に狙われたとしたら、あの坊やでもひとたまりも無いだろう。それに――あの二人の戦いは、喩えるなら宿命の対決というやつだ。ルシエンテスの方にその意識があるかどうかは知らないが、ジャスティンにとっては恋人の仇。さらに、未来へ進むためにはどうしても打ち倒さなければならない相手だ。悔しいが、あたいはお呼びでない。ならば、迷うことなど何も無い。障害は排除してやるだけのこと。モニターに表示された照準レティクルが変更される。残弾1、と表示されたモニターを確認し、グランディスは邪魔者たちの姿を睨み付ける。 「取ったぞ、バトルアク……!!いない、どこだ!?」
「取ったぞ、バトルアク……!!いない、どこだ!?」